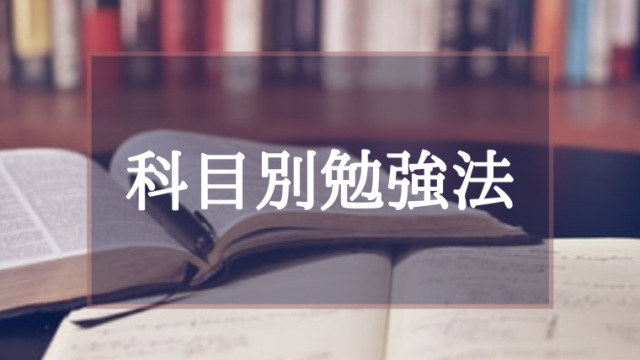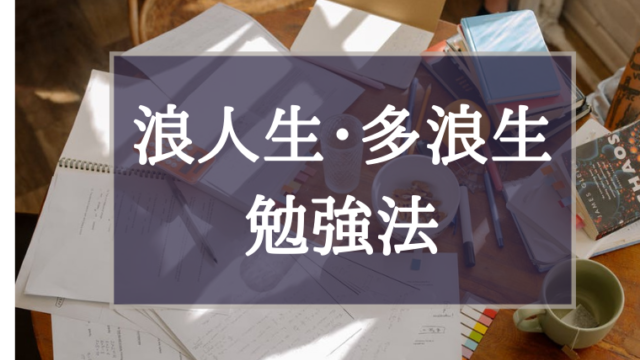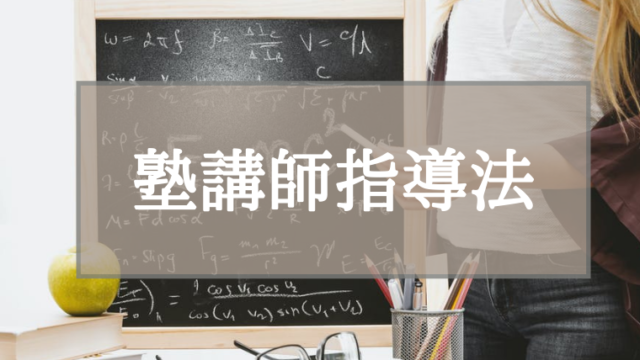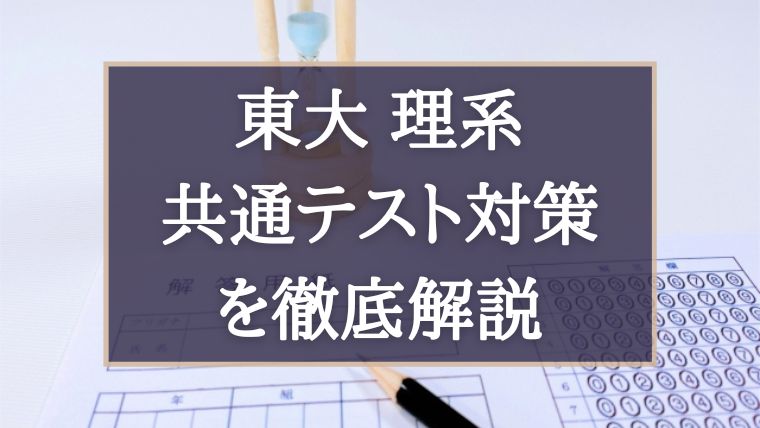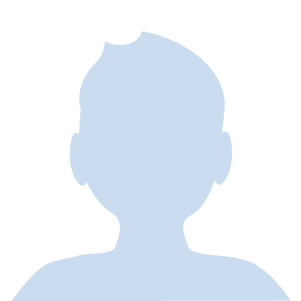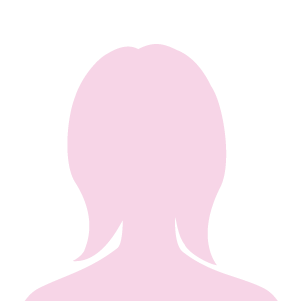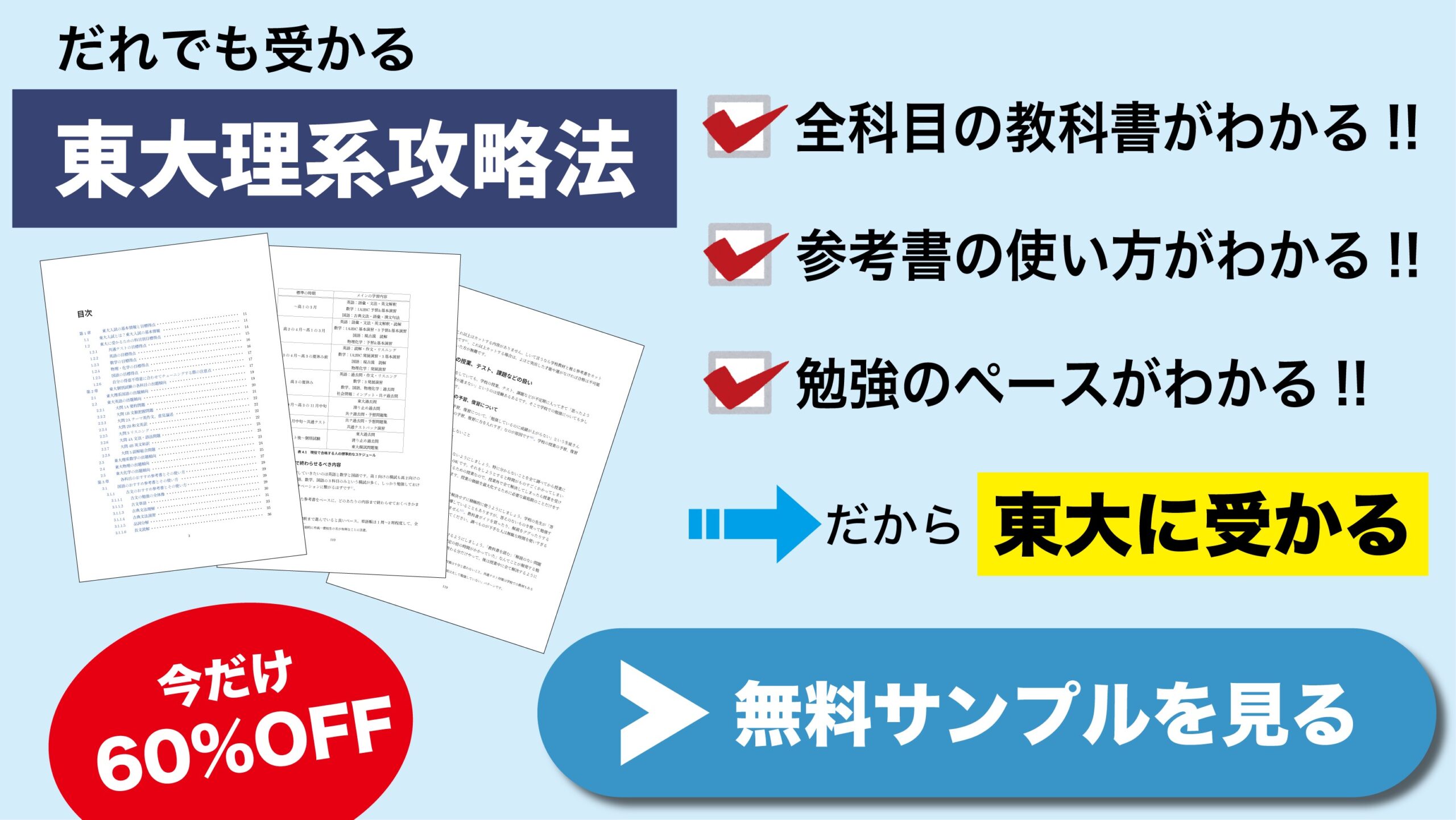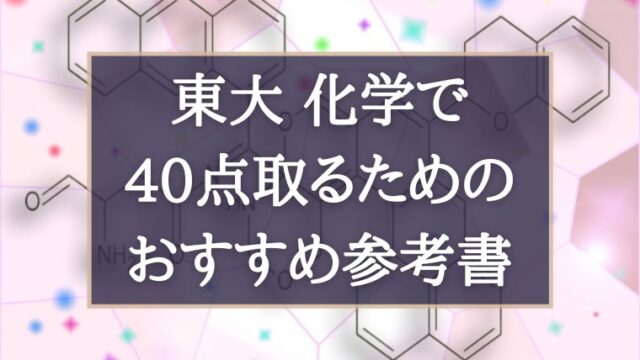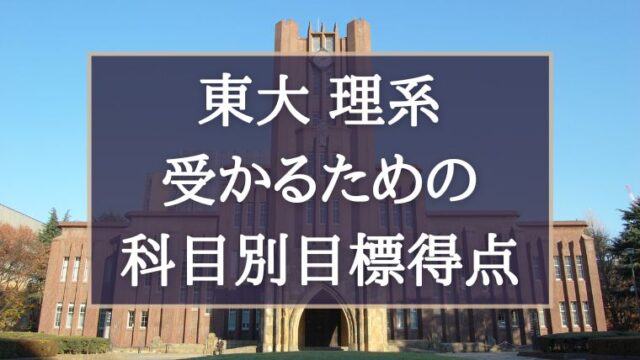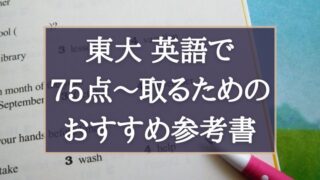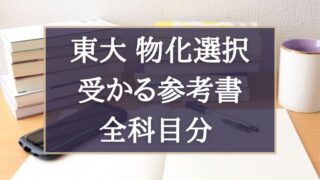ども、ぽこラボ所長です!
今回は東大理系志望の共通テスト対策について。
こんな風に思ったことはありませんか?
東大の合格ラインぎりぎりにいる人の多くが、共通テスト対策が不十分で失敗します。
この記事を読めば、共通テストで失敗しないために必要な対策を全科目分理解できます。
この記事の内容は次の通り。
- 共通テストで何点を取るべき?目標点は?
- 2次対策と共テ過去問以外に何をやるべきか?
- いつから本格的に対策を始めるべき?
それでは1つずつ見ていきましょう!
目次
共通テストで何点を取るべき?目標点は?
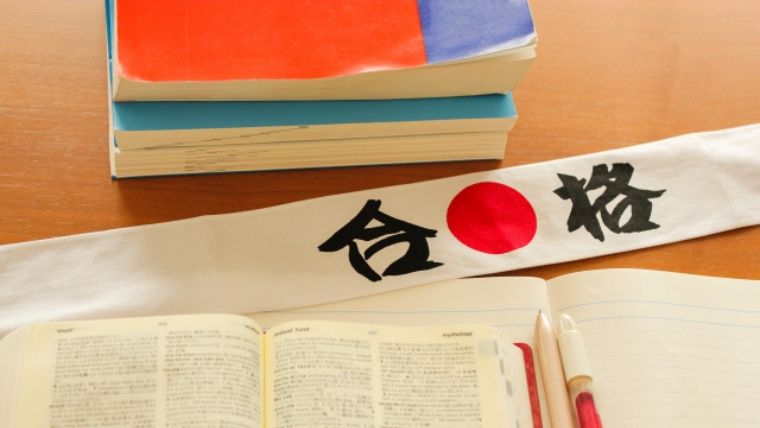
まずは共通テストで何点を取るべきか、東大志望の目標点を改めて整理しておきましょう。
東大志望の理系であれば、共通テストは
- 理1・2:85%
- 理3:90%
を目標にするといいでしょう。
2次試験も含めて、各科目の目標得点をこちらの記事にまとめているので参考に。

これも踏まえて共通テストの科目別の目標得点を表にまとめたものがこちらです。

※次の入試形式に合わせて数学は2BCとし、情報も入れた1000点満点で計算しています。ただし各科目の得点は執筆時点では発表されていないので、これまでの得点+情報100点としました。
まず英語、数学、理科は全て90%~95%を狙いましょう。
これらが全てクリアできれば8割くらい目標を達成したようなものです。
共通テストの国語はかなり難しいので、東大を狙う人でも150~160点取れれば十分。
社会と情報は勉強しても2次試験では出題されないので、80%程度でも大丈夫でしょう。
2次対策と共テ過去問以外に何をやるべきか?

次に共通テスト対策で「何をやるべきか」具体的な内容をまとめていきます!
東大は2次試験向けの学習をしっかり積んでおけば、共通テストを解くのに十分な学力を身につけることは可能ですが、対策をせずに失敗する人は毎年大勢います。
共通テスト対策は2次試験向けの学習とは別にしっかり取り組みましょう。
偏差値の高い高校に通っている人ほど、共通テストを甘く見る傾向が強いので要注意です!
英語・数学・理科・国語の共通テスト対策
まずは2次試験でも出題される英語、数学、理科、国語について。
これらの科目でやるべきことは「徹底的な実践演習」です。
特に共通テストはどの科目も「文章が長い」という特徴があるので、しっかり読みながらスピーディに解き続ける体力と技術が必要です。
具体的には
- 共通テスト過去問
- 共通テスト模試問題集 各社
- 共通テストパック 各社
あたりをできるだけ解きましょう。
各科目、「学校での演習とは別に」最低でも5回分は演習しましょう。
それで上述の目標点で安定しない科目は10回、20回と演習回数を増やしてください!
浪人生なら全科目20回ずつ演習して、確実に目標得点を超えられる状態を作りたいですね。
具体的な演習方法や、共通テスト対策にいたるまでにやっておくべき最低限の勉強などはこちらで解説しています!
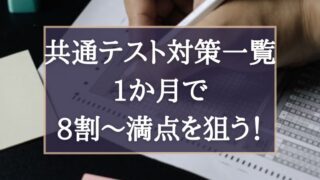
社会・情報の共通テスト対策
社会と情報は2次試験で出ないので、共通テストのためだけに勉強をしていく必要があります。
どちらも具体的には
- 共通テスト対策系の講義系参考書を読む
- 実践演習をくり返す
という流れで勉強することになるでしょう。
情報については、現時点ではまだ出版されていませんが、社会については共通テスト対策系の講義系参考書があるので、それをザっと読むようにしましょう。
※例年の感じであれば、情報についても参考書が近いうちに出版されるはずです。
例えば「面白いほどとれる本」シリーズなどがいいですね。
「黄色本」などと受験業界では言われています。
これを読んで最低限の知識をつけたら後は徹底的に実践演習です。
こちらは英語や数学などと同じく
- 共通テスト過去問
- 共通テスト模試問題集 各社
- 共通テストパック 各社
を演習してください。
社会や情報はふだん勉強していない分、最低でも10回ずつ、時間があれば15回でも20回でも通しで解くようにしてください。
※情報は20回分も問題集が確保できないかもしれませんが…。
センターの過去問は共通テスト対策として活用できるか?
という質問をときどきもらうので、それについても補足しておきます。
理科や社会は割とセンターと共通テストでの変更が小さかったのですが、社会は今後、科目編成が変わるのでセンターは使えなくなるでしょう。
- 国語:古いものは文章量が少なすぎる
- 英語、数学:問題傾向が違いすぎる
などの理由で、センターと共通テストは全く別物と考えるべきです。
基本的には数年分の共通テスト過去問と、各社の模試問題集を使って演習するのがいいでしょう。
いつから本格的に対策を始めるべき?

最も重要なのがいつから本格的に勉強を始めるべきかということ。
共通テスト対策は11月中旬(共通テスト2か月前)から
復習まで含めて1年分しっかりこなすには、丸3日くらいはかかります。
(解くだけで丸1日、復習しきるのにその倍くらいの時間が必要。)
10回分きっちり全てこなそうと思ったら、それだけで1か月丸々かかってしまうことになります。
しかし現役生は12月中はまだ学校があるので、1か月丸々分の演習時間を取ろうと思ったら、11月中旬には始めないと間に合いません。
11月中旬からは全体の50%は共通テスト対策を、12月に入ったら100%共通テスト対策で構いません。
11月から始めると2次試験の勉強が遅れてしまう…そんなときは?
という風に感じる人も多いでしょう。
正直、共通テストで上述の目標得点を取れないような人は、東大に合格するのはそもそも難しいですし、基礎学力が不足しています。
共通テストの演習をくり返せば、満遍なく全単元の基礎学力を伸ばすこともできるので、共通テストの対策をしているからと言って、2次試験向けの学力が伸びていないということはありません。
2次試験が心配であれば、「安定して目標得点に達することができる科目」から順に共通テスト対策の割合を減らして2次試験対策用の勉強に切り替えていけばいいでしょう。
基礎学力が十分であれば、共通テストの得点は安定するので、そこから2次試験の勉強を再開するようにしてください!
まとめ
今回は東大志望の理系の受験生向けに、共通テスト対策について解説しました。
目標得点はこちらの表の通りです。

この得点をとるために重要なのは徹底的な演習です。
英数理国は
- 共通テスト過去問
- 共通テスト模試問題集 各社
- 共通テストパック 各社
を使って最低でも学校の演習とは別に5回以上、目標得点に届かない場合は、10回でも20回でもこなしてください。
社会・情報あたりは「面白いほどとれる本」シリーズなどで学習をしたうえで、同じく過去問形式で演習を10回以上はこなしましょう。
共通テスト対策をすることで基礎学力を伸ばすことができるので、2次試験の学習を止めてでも、しっかり対策を行ってください!
それではまた、所長でした!