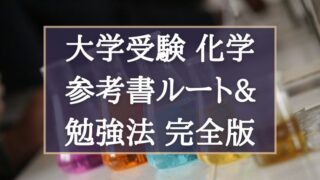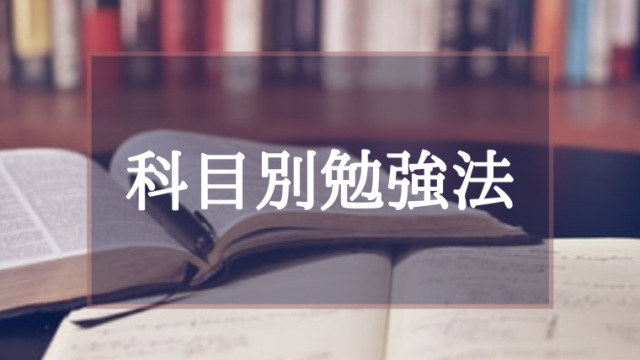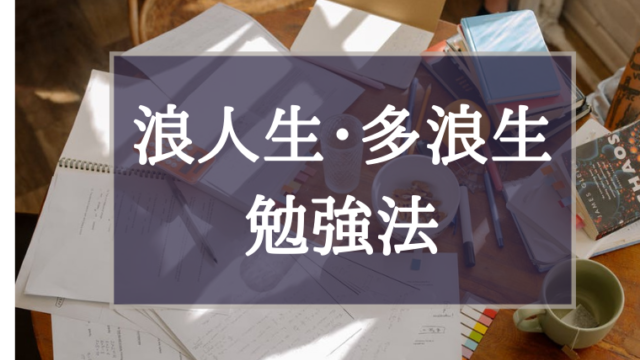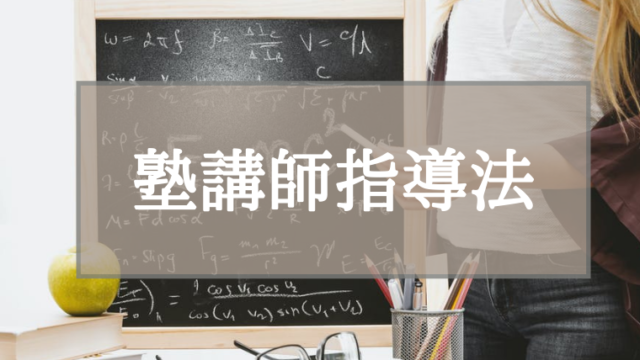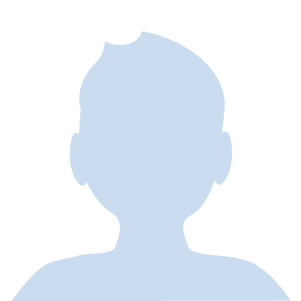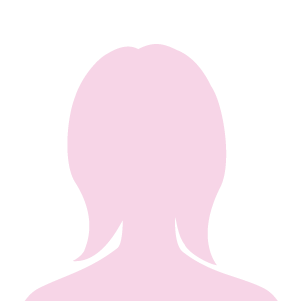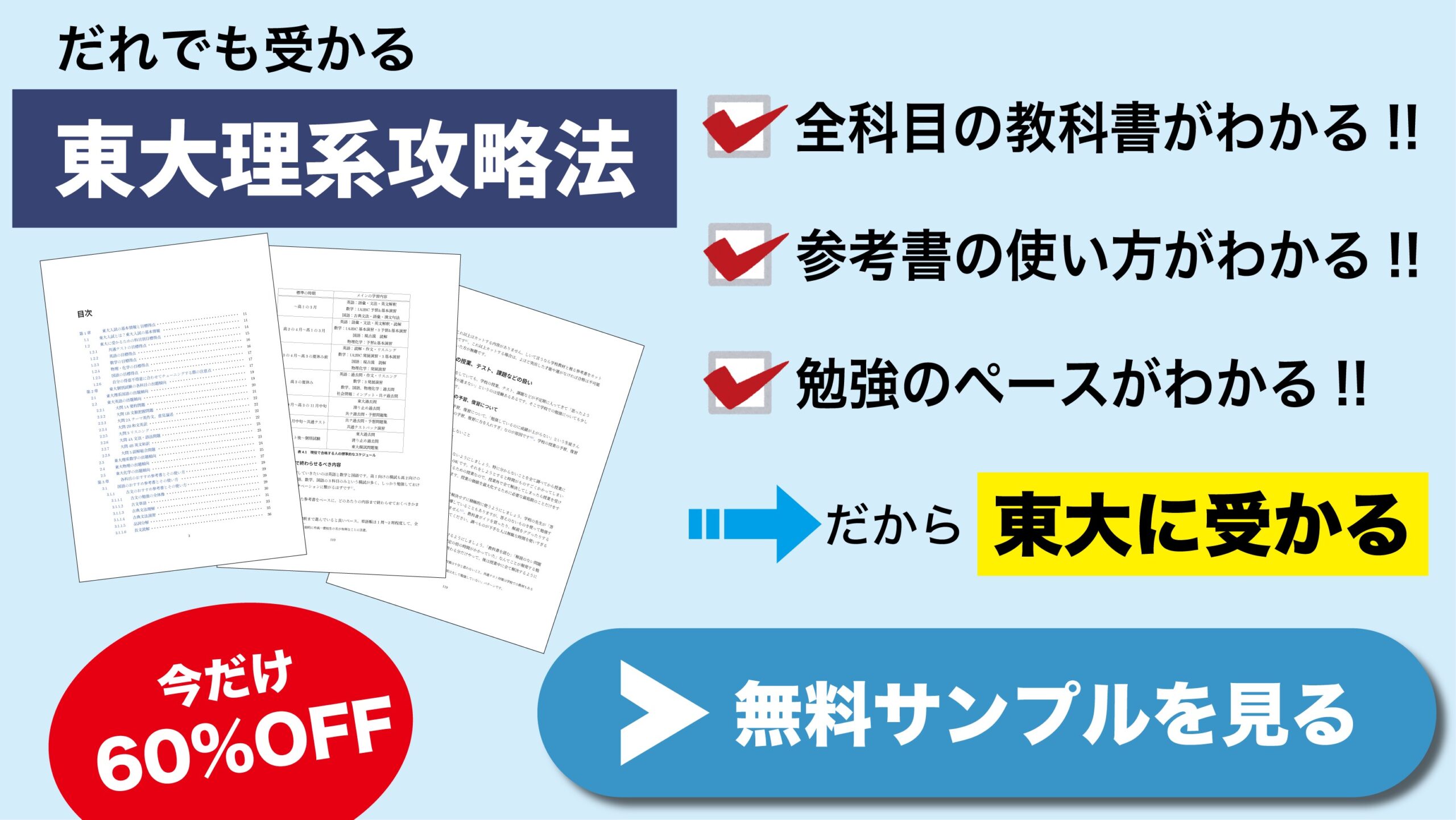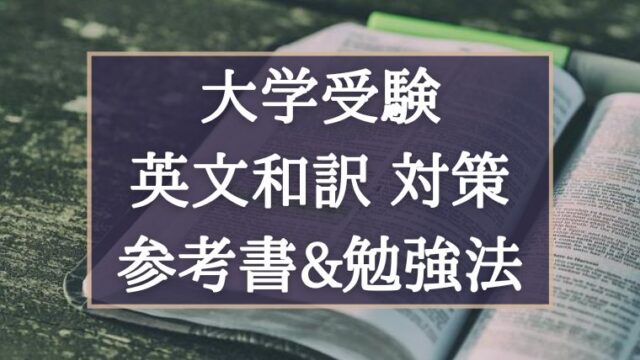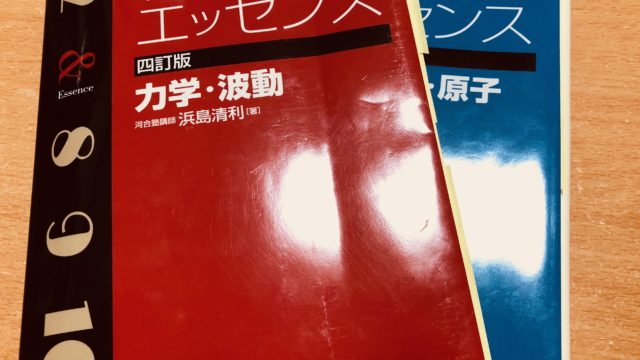ども、ぽこラボ所長です!
今回は、化学の過去問演習について。
と思ったことはありませんか?
この記事を読めば「正しい勉強手順」「いつから過去問を始めればいいのか?」「何年分やればいいのか」が全てわかります。
この記事の内容は次の通り。
- 化学の過去問はいつから始めるべきか
- 何年分やればいいのか
- 過去問演習でどれくらい伸びるのか
- どんな風に勉強すればいいのか
読み終えれば、過去問演習の勉強法で困ることは一切なくなります!
1つずつ見ていきましょう!
化学の過去問をいつから始めるべき?

過去問をいつから始めるべきか、から解説します。
みたいに色んな人が色んなことを言っている場合もあると思いますので、ここで改めて整理して理解しておくといいでしょう。
細かいことはこちらの記事で紹介していますので、ここでは簡単にまとめておきます!
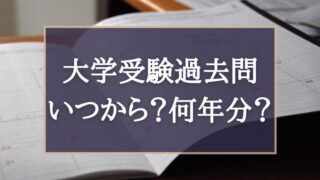
- 現役生で共通テストが必要でない場合:10月~11月
- 現役生で共通テストが必要な場合:10月~11月
- 浪人生の場合:4月~
現役生で共通テストが必要でない場合
現役生で共通テストが必要ない場合は、共通テスト対策の時間を取らなくてもいいので、11月頃から、過去問演習のメインに切り替えられれば間に合う人が多いでしょう。
可能であれば、10月くらいから進められるとライバルたちに差をつけることができますね。
特に受験する大学の数が多い場合(5校以上ある場合)は10月には始めておくのがおすすめです。
現役生で共通テストが必要な場合
現役生で共通テストが必要な場合には、共通テスト対策のメインの時期が11月最終週あたりから共通テスト本番までの1ヵ月半から2ヵ月程度欲しい所です。
それより前に、多少なりとも個別試験の過去問には取り組んでおきたいので、遅くとも10月末~11月頭には志望校の過去問を解き始めたいですね。
浪人は絶対にしない、という場合には、10月頭くらいからは滑り止めにする予定の過去問も始められる状態を目指すといいでしょう。
また時間のある夏休みには、共通テストでしか使わない科目や滑り止めの過去問もいくつかチャレンジできると尚よい状態です。
浪人生の場合
浪人生は本来、4月頭から週1くらいでは過去問を扱っていきたい所です。
現役生のときに散々な結果で、浪人の春の段階でA判定が出ていない場合はそれほど余裕がないかもしれませんが、それでも夏休みの時期までには過去問演習メインの勉強に以降できるよう計画を立てて勉強を進めていきましょう。
浪人生で実力がついているからと言って、滑り止め校や共通テスト対策をサボってしまうと足元をすくわれる可能性は十分あります。
どちらも現役生以上に抜かりなく進めてくださいね。
過去問を何年分勉強すべき?
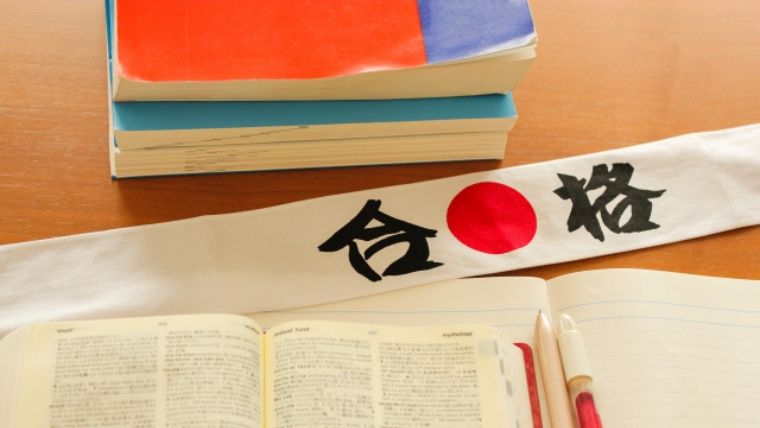
続いてよく聞かれるのが何年分勉強すべきかということ。
こちらも次の3パターンに分けて解説します。
- 現役生&浪人はしない場合:15年分~30年分
- 現役生&浪人覚悟の場合:10年分~
- 浪人生の場合:20年分~
詳しくは別の記事にまとめているので、そちらも参考に!
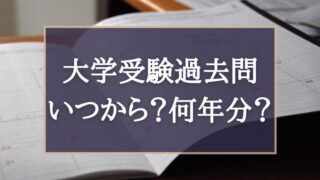
現役生&浪人はしない場合
私立専願であれば、科目数も多くないのでもう少しできる人もいます。
3校受けるのであれば、各大学5~6年分を基本と考えるといいでしょう。
ただし自分にとっては易しい大学(過去問1回目から合格最低点を余裕で超えるなど)の場合は、2年分~3年分にしてその分、志望校の過去問演習の年度数を増やすようにするなどの調整をするのもありでしょう。
現役生&浪人覚悟の場合
現役生で浪人覚悟の場合は、色んな大学の対策をしなくても済むので、浪人できない人よりは、1大学に集中して過去問演習できます。
最低でも10年分、できれば20年分以上を目標に過去問演習をしたい所です。
後述しますが、浪人生の場合は、滑り止めの大学ですら10年分くらいこなす余裕がある人もいるので、できるだけ負けないように準備してほしいですね。
浪人生の場合
浪人生の場合は4月からでも過去問演習ができますし、夏くらいからは過去問演習をメインにできるので、かなり演習可能です。
第一志望は、20年分以上を目安にしてください。
滑り止めも各大学5年分以上は満点を取れる状態にしたいですね。
過去問演習でどれくらい伸びる?
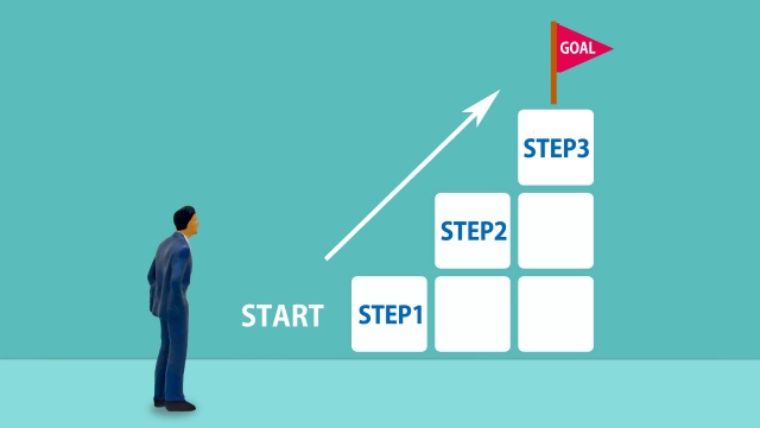
過去問演習でどれくらい伸びるのか、というのもよく聞かれる質問です。
合格に必要な得点が7割なら、5割くらいから過去問演習がスタートすれば十分合格を狙える範囲内です。
逆に7割必要なのに過去問1発目が2割〜3割程度しか取れていないのであれば、かなり厳しい状態と考えていいでしょう。
もちろんそこから大きく伸びて受かる人もゼロではありませんが、よほど特殊な状況でなければ難しいのは間違いないですね。
化学の過去問演習の具体的な手順

まずは超具体的に勉強の手順を書いておきますね!
- 問題用紙を印刷する(解答用紙がある場合は準備)
- 時間を計って解く
- 時間オーバーして解けそうな所はペンの色を変えて解く
- 丸付け&解説を読み込む
- 資料集などで覚えていなかったことをチェック
- 暗記すべきものを暗記する
- 解説を閉じてその場で間違えた問題を解きなおす
- 点数を記録する
- 類題を解く(時間に余裕があれば)
それぞれ補足していきます!
問題用紙を印刷する(解答用紙がある場合は準備)
過去問が載っている赤本は、本にする段階で実際の入試とは少し異なるレイアウトで問題が配置されている場合があります。
具体的には余白がなくなっていたり、1ページあたりの文章量が変わっていたりなどですね。
東進の過去問データベースでは、入試の形そのままの形で載っていることも多いので、そちらに掲載されている場合はダウンロードして印刷すると良いでしょう。
※ただし東進のサイトに全大学、全学部の全年度があるわけではないので、注意。
また、共通テストや記述が多い大学などは赤本のサイトで、解答用紙も入手できることがあるので、ぜひダウンロードして本番の形に近い状態で取り組みましょう。
時間を計って解く
過去問演習は必ず時間を計って解いてください。
本番同様に制限時間内に最高得点が出るように意識して解き進めましょう。
飛ばすべき問題があれば、時間的に飛ばすべきだなと思ったものはその場その場で判断しつつ飛ばしながら進めてください。
時間オーバーして解けそうな所はペンの色を変えて解く
過去問演習は練習なので、
と思う部分があれば、ペンの色を変えて解き続けてもかまいたせん。
ペンの色を変えて解くことで時間オーバーした部分とそうでない部分をはっきり区別することができます。
ただし試験時間の1.2倍までには終わらせてくださいね。
60分のテストを180分かけて解いても練習にはならないどころか他の科目の勉強に使う時間を削ってしまうことになります。
60分のテストなら72分で終わらせてください。
丸付け&解説を読み込む
丸付けをして解説を全て読み込みましょう。
解説は正解している問題も一応目を通してください。
特にマーク式の問題の場合は、たまたま正解していた可能性があります。
また正解はしていたけど、補足の解説に覚えていなかった内容が書かれてあるかもしれません。
隅から隅まで読むのは常識と思っておきましょう。
資料集などで覚えていなかったことをチェック
解説を読むと、覚えていなかった項目もいくつかは出てくるはずです。
資料集などで全てチェックするようにしましょう。
あまり時間対効率がよくないからですね。
ちなみに最難関の国公立や私立大学の過去問では、教科書や資料集では出てこないような内容が出題されることがあります。
そういった場合は「新研究」で調べるのもありです。
絶対必要というわけではありませんが、持っていて損はないでしょう。
暗記すべきものを暗記する
調べたものはその場で覚えてしまうのがベストです。
と思って放置するのが1番危険です。
その場で覚えて、また次回忘れていたらそのときにまたその場で覚えるを繰り返すのが最も失敗の少ない方法です。
解説を閉じてその場で間違えた問題を解きなおす
計算問題や記述問題などは、解説を閉じてその場で解き直しをしてみましょう。
ここで重要なのは手を動かすこと。
頭の中で、解き方の手順だけ思い出して終わりではダメです。
これをやっているうちは凡ミスが減りませんし、スピード感も上がりません。
必ず手を動かしてください。
点数を記録する

過去問に関しては点数を記録し続けることも重要です。
各問題の配点が書かれていない場合は、正答率を計算してそれを点数に換算してください。
徐々に上がってきているのか、それとも変わっていないのか、点数を記録しないと見えてきません。
推移が見られるように必ず記録してください。
類題を解く(時間に余裕があれば)
類題に関しては、他の科目の状況も鑑みて時間的に余裕があれば、解いておいた方がいいでしょう。
特に計算問題や、頻出問題(金属イオンの分離とか、有機の構造決定は頻出の大学が多い)で苦手分野が見つかれば、問題集でも復習しておいた方が確実に過去問の得点は上がっていきます。
化学の過去問演習をする際の注意点

手順を整理したので、次は注意点をまとめておきます。
注意点は以下の通りです。
- 記述、マークの形式は合わせる
- 2科目同時なら2科目同時に
- 時間に余裕がない場合は悩む時間をゼロに
- 復習の制限時間は試験時間の倍を目安に
それぞれ解説していきます!
記述、マークの形式は合わせる
記述式、マーク式など解答形式は大学によって異なりますが、必ず解答形式に合わせて解いていきましょう。
共通テストのようなマーク形式の問題の場合は、解答用紙を入手できるのであれば、印刷して使いましょう。
練習しておかないと本番でマークミスする可能性があります。
記述形式の場合はノートに必ず解答を見やすくまとめていってください。
ノートや裏紙にザッと解いていって終わりではダメです。
特に「理由を20文字で説明せよ」のような説明問題は字数制限があることも多いので、その場合には方眼ノートを使うのもありです。
2科目同時なら2科目同時に
化学は一部の大学は理科2科目で合わせて120分とか、150分とかの設定になっています。
そういった場合は必ず2科目同時に解きましょう。
ですので、時間の感覚を正しく掴むためには2科目同時に受ける形式になっているテストはその形式に合わせて問題を解きましょう。
時間に余裕がない場合は悩む時間をゼロに
2科目以上要求される大学の中には制限時間に悩むくらい時間がタイトな大学があります。
時間に余裕がない場合には基本的には「解ける問題を短時間で解けるようになる」という正攻法で攻めるのが1番大事です。
特に受験までまだ1ヶ月以上あるような時に、ヤマをはって何かの分野を捨てに行くような突飛な作戦は立てないようにしてください。
確実に解ける問題を増やして、苦手な単元は類題にもできるだけ時間を使うようにしましょう。
解けたけど、悩んで時間を使ってしまった問題に関しては、なんでそんなに悩む必要があったのかは確実にインプットして次からは問題を読んだ瞬間から手が動き始めるくらいのスピード感を目指していきましょう。
復習の制限時間は試験時間の倍を目安に

復習は丁寧にやるべきですが、他の科目もあるはずなので化学の過去問の復習だけに5時間も6時間も使うわけにはいかないですよね。
基本的には復習の時間は試験時間の倍の時間までを目安にしましょう。
60分のテストであれば、復習に使えるのは120分までと、復習にも制限時間を設定しておくと日々の時間管理が簡単になります。
特に過去問演習の時期は日々の時間割が少し狂うだけでもストレスになってしまうので、時間管理をしやすい形式で進めていくのは重要です。
また、復習にも制限時間をつけておかないと、のんびり暗記や調べ物に時間を使ってしまう可能性が高くなります。
その意味でも制限時間は重要です。
また試験時間の2倍以上の時間をかけないと復習が終わらないようなら、まだまだそのテストでは満点を狙えるレベルには到達していません。
満点を取ることが合格に必須な大学はないので、制限時間内にできる限りの復習をして、その部分だけ満点を取れるようになっておけば合格は十分可能です。
演習を何年分もくり返していくうちに、徐々に復習が時間内に終わるようになってくるので、そこから先は1度復習したものは満点を取れる状態にしていけばOKです。
復習が間に合わない人は、その制限時間内にどこから復習を始めるのが1番効率がいいのか考えることもでき、それが本番にどの問題から解くべきかを考えるのと状況が似ていて、ちょうどいい訓練にもなるはずです。
まとめ
今回は化学の過去問演習をするときの具体的な勉強法や、復習の仕方を丁寧に解説しました!
過去問を始める時期は次の通りでした。
- 現役生で共通テストが必要でない場合:10月~11月
- 現役生で共通テストが必要な場合:10月~11月
- 浪人生の場合:4月~
この時期から始められれば、2割程度は得点を伸ばすことができるでしょう。
ただし丁寧な勉強を心掛け、次のように進めるようにしてください。
- 問題用紙を印刷する(解答用紙がある場合は準備)
- 時間を計って解く
- 時間オーバーして解けそうな所はペンの色を変えて解く
- 丸付け&解説を読み込む
- 資料集などで覚えていなかったことをチェック
- 暗記すべきものを暗記する
- 解説を閉じてその場で間違えた問題を解きなおす
- 点数を記録する
- 類題を解く(時間に余裕があれば)
ここで紹介した方法で取り組めば、確実に成績は伸びるので、丁寧に取り組んでみてくださいね。
それではまた、所長でした!