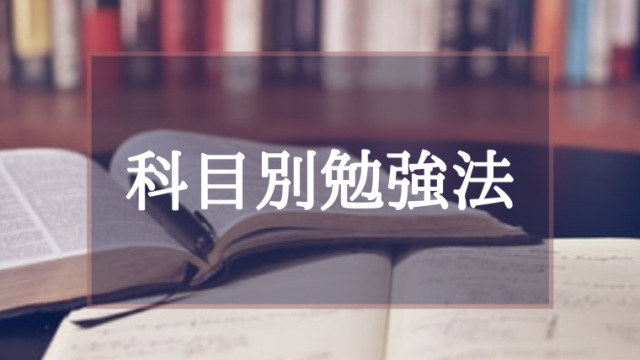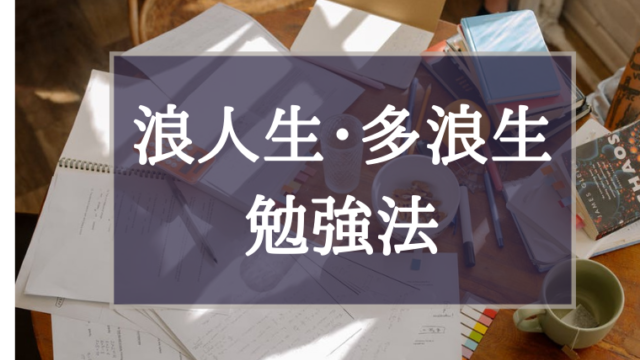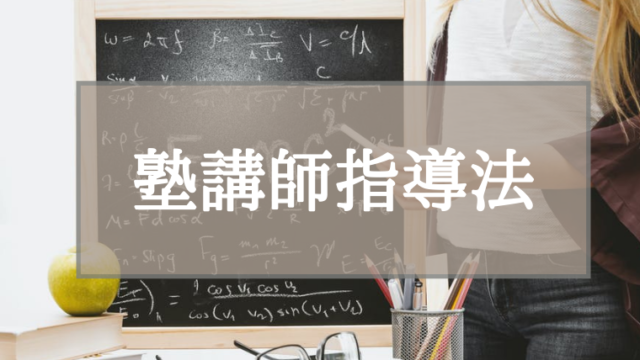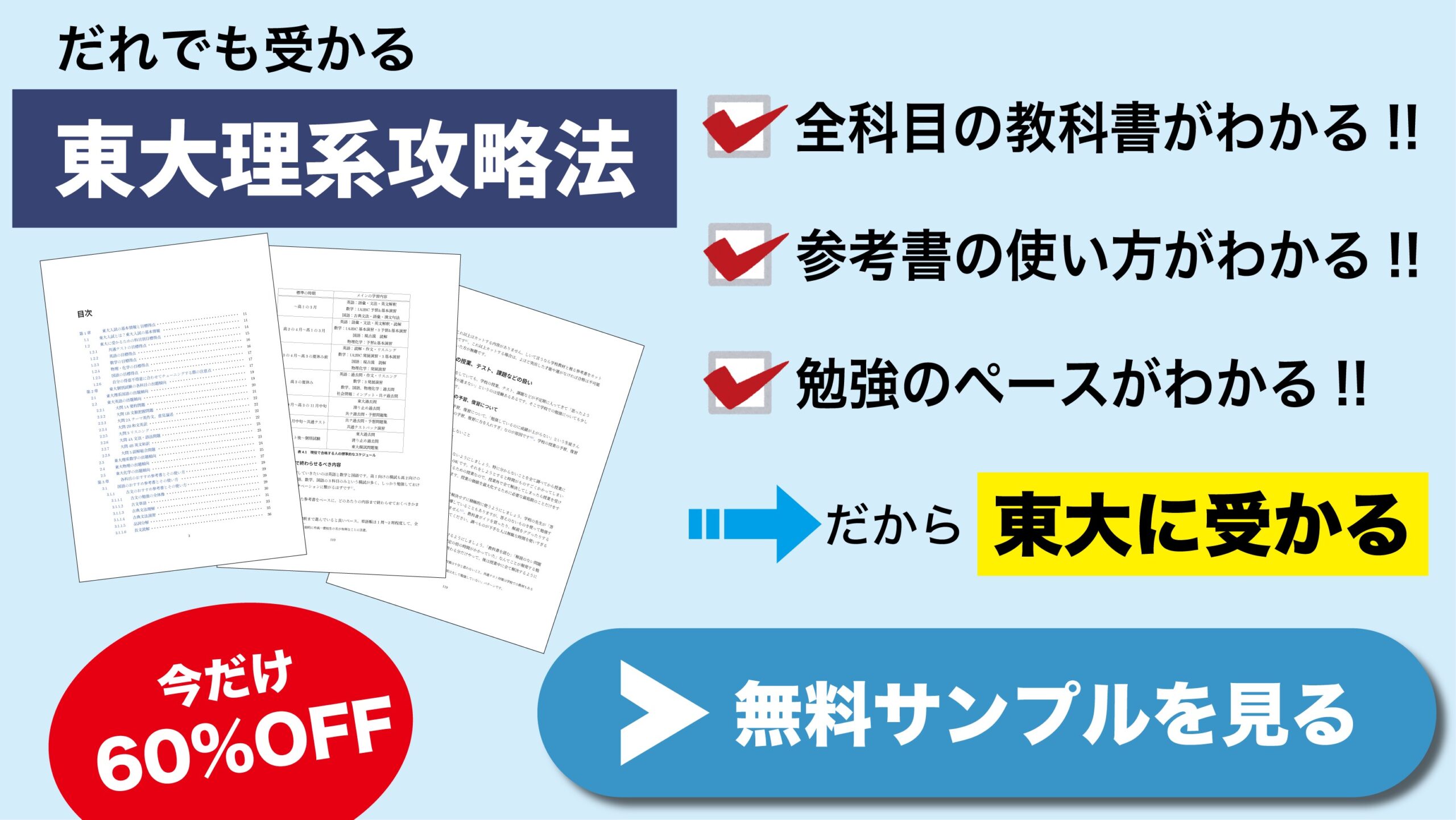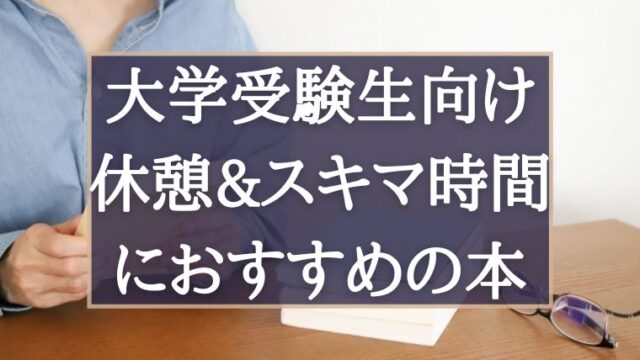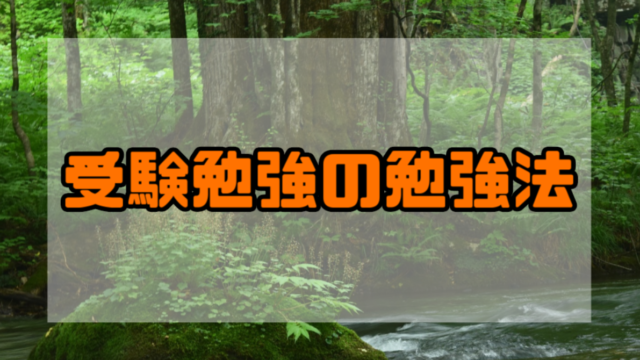ども、所長です!
今回はよく質問される
○○大に合格するためには何時間勉強すればいいんですか?
に関して、丁寧に説明していこうと思います。
正直な所、そんなの人によって全然違うのですが、一応の目安はあります。その目安を数字で説明されると
なるほどな、頑張るしかないか。。。
とある種あきらめの境地に近いものを持って勉強を頑張る受験生が多いこともこれまでに見てきたのでよーーく知っています。
あなたもその一員になれるように目安を説明していきますので、ぜひ参考にしてみてください!
目次
【大学受験】独学で合格するために必要な学習量・勉強時間はなぜ人によって違うか
まずは何で人によって必要な勉強時間が違うのかを改めて整理しておきましょう。
この作業は絶対に必要です。
あいつは大して勉強していないのに何であんなに良い判定もらってるの?
なんて思うことも少なくなるはず。他人をうらやましく思ったところで自分の成績は上がりませんから、ここで整理して納得しておきましょう。
志望校合格と現在の学力との差が違うから必要な勉強時間が違う
ものすごく当たり前のことを言いますが、人によって志望校合格と現在地点の距離が全く違います。
これはスタート地点だけの話をしているわけでもなく、ゴール地点だけの話をしているわけでもありません。
スタート地点とゴール地点との差が、あなたに必要な勉強量であり、勉強時間ですよね。
少し具体例を出してみます。
偏差値40のAさんが偏差値45の大学を目指しています。
一方、偏差値55のBさんが偏差値65の大学を目指しています。
どちらのほうがより多くの勉強時間が必要でしょうか?
そうです。Bさんのほうがより多く勉強する必要がありそうですよね?
スタート地点としては、AさんよりもBさんのほうが学力が高いですが、志望校までの偏差値の差を見ると、Aさんは5上げればいいだけなのに対してBさんは10上げなければなりません。
ちなみに「低い点数を普通くらいの点数にする」のと「普通くらいの点数をいい点数にする」のでは、後者の方が大変ということもこの状況をより一層はっきりさせてきますね。
というわけで、志望校合格との差を意識しないと必要な学習量は分からないし、必要な学力は身につかないということですね。
あなたに必要な学習量を調べる際には、各大学に合格する人がどのようなルートをたどっているかを知る必要があります。
そのルートの調べ方はこちらの記事に詳しくまとめていますので、ぜひ参考にしてくださいね!
>>【大学受験独学】あなたに必要な学習量は?調べる手順を解説します
勉強法・集中力・好き嫌いで勉強効率が違うから必要な勉強時間は違う
次に勉強効率に話を移していきましょう。
まったく同じ学力の人が全く同じ大学の全く同じ学部を目指す時でも、必要な勉強時間に差が出てきます。
というのは、人によって勉強効率に差があるからですね。
勉強効率の差は主に次の3つから出てくるものです。
- 各科目、各分野の勉強法の差
- 集中力の差
- 各科目、各分野の好き嫌いの差
説明するまでもないと思いますが、余計な勉強をしていれば、ゴールにたどり着くのは遅くなってしまいますし、
集中できていない状態で勉強すれば、勉強時間だけで見ればどんどん伸びていきます。
また好き嫌いによって、勉強した内容が頭に残る割合もかなり変わってきます。
ですので、「効率的な学習法」で「集中した状態」を保って「好きだな」と思いつつ勉強するのが最も勉強時間が少なく済むはずです。
最後の好き嫌いに関しては、どうしようもないところもありますが、前の2つはテクニックで解消できる部分も大いにありますので、ぜひ勉強しておきたいところ。
以下の記事にかなり詳しく勉強法については書きましたので、ぜひ参考にしてください!
完全にゼロからスタートした場合の合計勉強時間は2100時間~4500時間
というわけで
- 志望校合格と現在の学力の差
- 勉強効率の差
で人によって合格に必要な勉強時間が全然違うことがお分かりいただけたかと思います。
それでは具体的に「完全にゼロ」の状態からスタートして一般的な大学に受かるために必要な学習量がどれくらいかまとめておきましょう。
科目別の合格に必要な勉強時間の目安
まず科目別にまとめていきます。
大雑把に受験までに勉強すべき内容はこちらの記事にまとまっていますので、イメージがわいていない場合は確認してから続きを読んでいただいた方がいいかもしれません。
>>【独学向け】大学受験の勉強年間スケジュールを公開!勉強の進捗目安を学ぼう!
参考書に関しては、普通程度の厚さのものでしたらおよそ50時間くらいが1周目をクリアする目安に、難易度の高いものや、分厚いものなら100時間から150時間くらいが1周目をクリアする目安になります。
また各々の参考書を3周するとすると、2周目に0.5倍の時間、3周目に0.25倍の時間がかかるとしても大体1周にかかる時間の倍くらいがかかります。
それを踏まえて各科目ざっくりの目安を見ていきましょう。
英語
まずは英語からです。
英語は「英文法」「英単語・熟語」「英文解釈」「長文読解」「例文暗唱」「英作文」「リスニング」「過去問」が受験で必要になります。
参考書換算で言うと、
- 「英文法」は映像授業と問題演習で2冊分
- 「英文解釈」は1冊分
- 「長文読解」は2冊分
- 「例文暗唱」と「英作文」で1冊分
- 「リスニング」で1冊分
- 「過去問」で1冊分
程度の時間は必要なので、最低でも1周するのに400時間は必要になります。ここからさらに3周分かかるとすると、800時間程度ですね。
数学
数学は基本的に「インプットor予習」「問題演習」「過去問」の3段階ですね。
- 「インプットor予習」に参考書2冊分
- 「問題演習」は文系なら4冊分、理系なら8冊分
- 「過去問」は1冊分
程度の時間は必要なので、最低でも1周するのに文系なら350時間、理系なら550時間、3周するなら文系で700時間、理系なら1100時間です。
ちなみに問題演習とザックリ書きましたが、青チャートのような分厚いものは1冊で2冊分程度の重みはありますので、文系はそれが2冊。
理系ならそこからさらに1冊か2冊分程度の演習が必要になります。
国語
国語は「現代文読解」「古文文法」「古文読解」「古文単語」「漢文句法」「漢文読解」「過去問」が必要になります。
参考書で換算すると
- 「現代文読解」で2冊分
- 「古文文法」で1冊分
- 「古文読解」で1冊分
- 「古文単語」で0.5冊分
- 「漢文句法」で1冊分
- 「漢文読解」で1冊分
- 「過去問」で1冊分
程度の時間は必要で、合計すると375時間です。3周するなら750時間です。
理科
理科は数学と同じで基本的に「インプットor予習」「問題演習」「過去問」の3段階ですね。
参考書で換算すると
- 「インプットor予習」で2冊分
- 「問題演習」で3.5冊分
- 「過去問」で1冊分
程度の時間が必要で、合計すると325時間です。3周するなら650時間です。
ちなみに理科の問題演習はセミナーのような重い問題集で2冊分程度、1つレベルが上がって重要問題集でも1.5冊分程度の時間が必要になります。
社会
社会は「インプットor予習」「穴埋め系問題集」「一問一答」「問題演習」「過去問」が必要になります。
参考書で換算すると
- 「インプットor予習」で1.5冊分
- 「穴埋め系問題集」で1冊分
- 「一問一答」で1冊分
- 「問題演習」で1冊分
- 「過去問」で1冊分
程度の時間が必要で、合計275時間です。3周するなら550時間です。
ちなみに世界史と地理を比べると地理の方がだいぶ楽ではありますが、そのあたりの細かい部分は今回省きました。
あくまでも目安と思っておいてください。
全科目まとめ
全科目3周ずつしていく基準でまとめてみると次のようになります。
- 英語:800時間
- 数学:文系700時間、理系1100時間
- 国語:750時間
- 理科:650時間
- 社会:550時間
次にこれを受験科目数に分類して並べてみましょう。
受験科目数別に見ると?私立or国立/文系or理系
ここでは以下の4種類「私立文系(英語、国語、社会1科目)」「私立理系(英語、数学、理科1科目)」「国立文系(英語、数学、国語、理科1科目、社会2科目)」「国立理系(英語、数学、国語、理科2科目、社会1科目)」に分けて並べてみます。
国立文系は計算を簡単にするため理科基礎2科目分で理科1科目分としています。
本当は共通テストだけでしか使わない科目はもう少し短時間化できますが、最初の段階では多めに見積もっておいた方が失敗は少ないと思っておきましょう。
- 「私立文系(英語、国語、社会1科目)」:2100時間
- 「私立理系(英語、数学、理科1科目)」:2550時間
- 「国立文系(英語、数学、国語、理科1科目、社会2科目)」:4000時間
- 「国立理系(英語、数学、国語、理科2科目、社会1科目)」:4500時間
ちなみにこれらを1年間365日で割り算すると、
- 私立文系:5.75時間/日
- 私立理系:6.99時間/日
- 国立文系:11.0時間/日
- 国立理系:12.3時間/日
となります。
もちろん、ゼロからスタートしてこれくらいですから、高1高2から勉強を始めていると、もっと短時間で必要な学習は可能です。
しかし例えば、国立理系となると「受験勉強のみ」で毎日12時間の勉強が必要になるので、高3の1年間だけでゼロからスタートして間に合う可能性はまずありません。
学校の授業やテストなどを通して、「インプットor予習」、「問題演習」の部分をどれだけカットできるかも重要な要素になることが分かると思います。
【大学受験】独学だと結局、何時間を目標にすればいいのか?

ここまでである程度計算は行ったので、結局何時間を目標にしていけばいいのかの話に移ります。
とりあえず10時間を目標にしよう!
もちろん人によって必要な勉強時間が変わってくることは、ここまででも見てきた通りなのですが、それでも基本は毎日10時間を目標にしていただきたいと思います。
理由としては
- 10時間でも足りない人がかなり多い
- そもそも10時間勉強に持っていくのがかなり大変
ということです。
上で計算した科目ごとの勉強時間に関しては、参考書選びを間違えずに無駄な時間を使わずに勉強した場合の計算です。
そう考えると10時間でも足りない人は独学であれば、私立大の受験科目数が少ない場合でも全然ありえます。
また10時間毎日勉強するのだって、普通はかなり大変です。
習慣化は徐々にしかできないので、以下の記事を参考にしていただきつつ、今すぐにでも習慣化を始めてください。
>>平日6時間・休日10時間勉強するための5つのポイント【受験生・社会人必見】
例えば、
- 1か月目 6~7時間/日
- 2か月目 8~9時間/日
- 3か月目 10時間/日
と毎日の勉強時間を少しずつ延ばしていきましょう。
最初の1か月、毎日6時間は平日は学校と少しの自習でクリア、休日に学校のある日と同じくらい頑張ってみましょう。
そこから毎月2時間くらいずつ勉強時間を延ばせるといいですね。
場合によっては12時間、14時間とさらに勉強時間を延ばさないと間に合わないということもあり得るので、「まずは」10時間という感覚が大事です。
注意!易しい記事で必要な勉強時間を見積もりがちな自分になっていないか?
最後にものすごく大事な注意をしておきます。
10時間と書いていたからと言って実際に毎日10時間勉強してみても、本当に足りるとは限らないということです。
この記事よりも前に他の記事を見てからこの記事を見たかもしれませんし、この記事を見た後に他の記事を見ることもあるかもしれません。
そしてその中には
毎日6時間だけ勉強して東大に受かりました!
といった内容の記事があるかもしれません。
その中に
10時間なんて集中が続かないから無意味で6時間に集中しよう!
といった内容があったらあなたはどちらを選ぶでしょうか。
人間は基本的には楽な方を選択しがちです。
私が本当に知識のない状態で、この記事と6時間で大丈夫という記事と両方を見たら6時間の方を選ぶと思います。
塾講師として10年指導をしてきた経験上、6時間で十分必要な勉強をできる人はほんの一握りです。
まずいないと思っておいてください。
あなたはその記事を書いた東大生よりも賢く効率的に勉強を進める自信がありますか?
というわけで私から伝えたいこととしては、
勉強時間の目安は厳しいほうを基準にしろ!
ということです。おそらくこの記事よりも厳しいメッセージを伝えている方もいらっしゃることでしょう。
そんな場合には、そちらを勉強時間の目安にしてみてください。
厳しいほうで勉強して「余裕ができたら勉強のペースを緩める」ということは可能ですが、
「このままじゃ間に合わなそうだから勉強のペースを上げる」という作戦は受験までの残り時間的に不可能になっている可能性もあります。
ですので、勉強時間は厳しめに厳しめに考えていきましょう。
それではまた、所長でした!