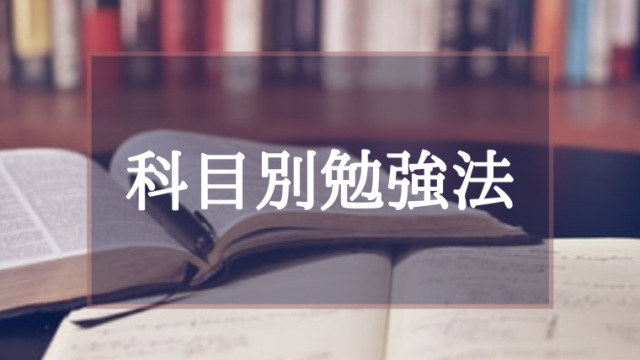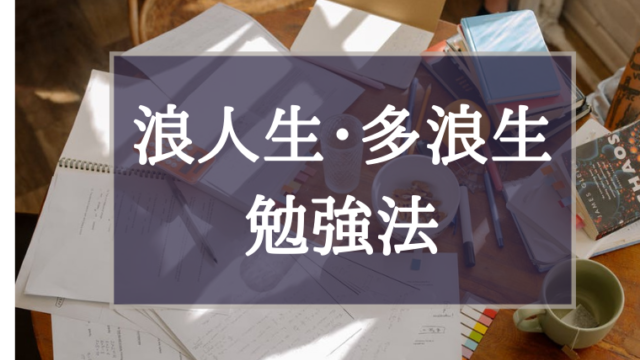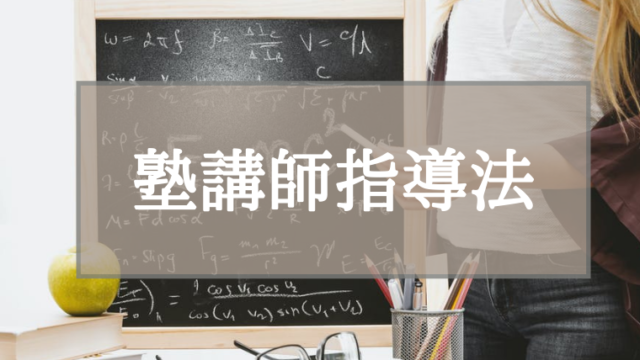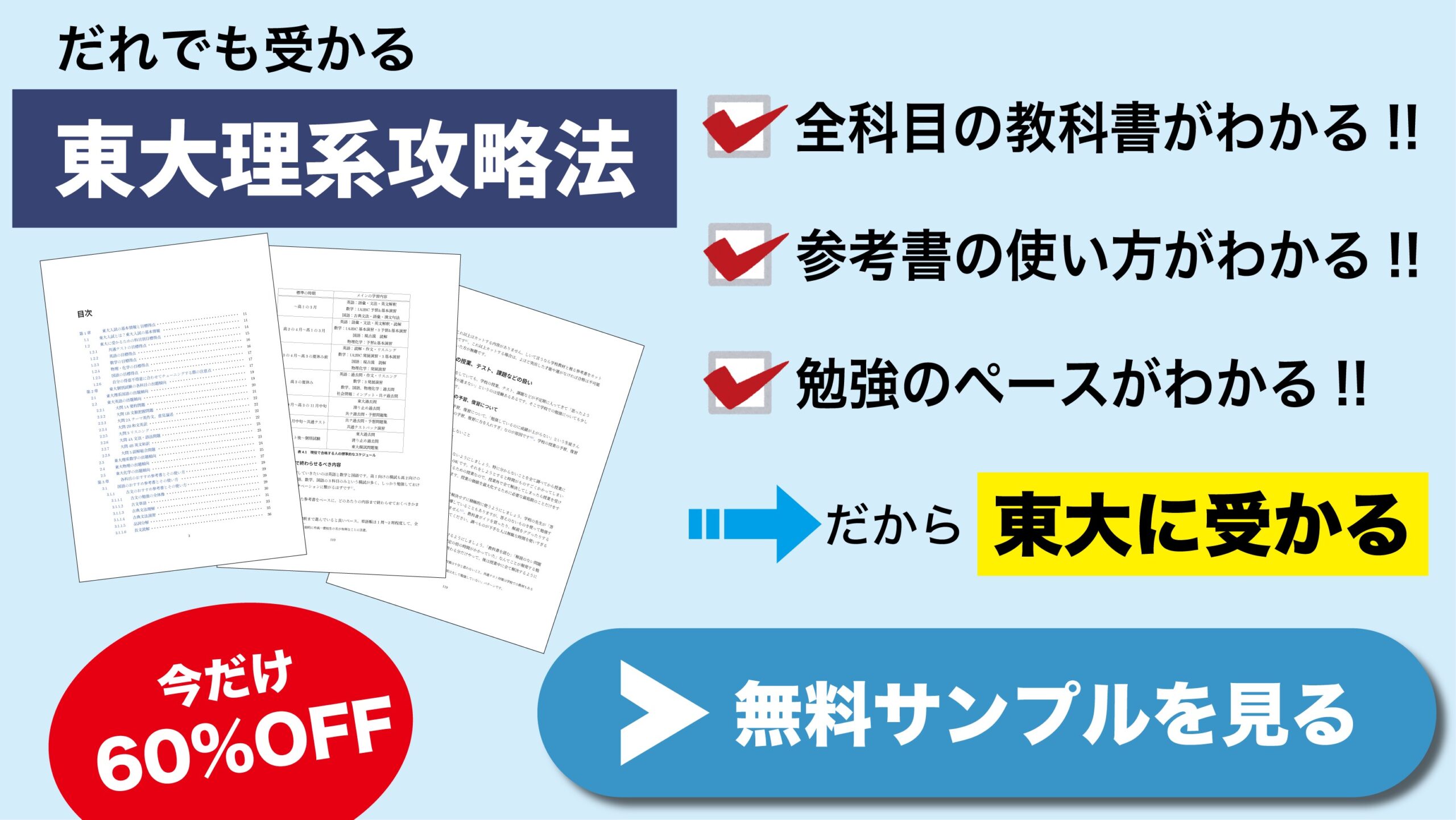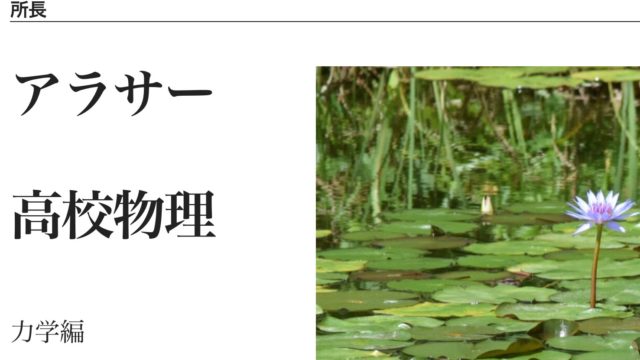親・保護者ができる【勉強しない子どものやる気を引き出す】一番易しい方法

ども、所長です!
突然ですが、こんな風に思ったことはないでしょうか。
「どうにか子供に勉強させたい」
「よその子は勉強しているのに、なんでウチの子は勉強しないんだろう」
「塾や家庭教師に頼る前に家庭で出来ることはないのかな」
今回はそんな保護者・親御さんへ送る記事となっています。
目次
本記事のテーマ
この記事のテーマはこちらです。
親・保護者ができる【勉強しない子どものやる気を引き出す】一番易しい方法
記事の信頼性
信頼できる記事であることを保障するために参考URLと参考図書をこちらに書き出しておきます。
参考URL
- 【親御さん向け】やってはいけない!小学生・中学生の子供が勉強のやる気をなくす6つのNG行動
- やる気アップ!小学生が勉強に対するモチベーションを上げる5つの方法
- 子どものやる気に”着火”させる2つの方法自分の中で「スパークする」何かと出会えるか
参考図書
- 「合格する親子のすごい勉強」松本亘正(かんき出版)
- 「マンガでよくわかる 子どもが勉強好きになる子育て」篠原菊紀(フォレスト出版)
- 「1日10分で大丈夫! 「自分から勉強する子」が育つお母さんの習慣 」村上綾一(ダイヤモンド社)
- 「最短の時間で最大の成果を手に入れる 超効率勉強法」メンタリストDaiGo(学研プラス )
執筆者のプロフィール
私は個別指導を約10年続けている塾講師です。
主に中学生、高校生、浪人生の受験指導を行っておりまして、地域の偏差値40台の公立高校受験も、東工大や一橋大などの難関大受験も担当しております。
本題の前にメッセージ
こちらの記事をご覧になる皆さんは、おそらくお子さんがいらっしゃって、その教育に熱心な方、はたまた何か困ったことがある方だと思います。
子育ての秘訣が書かれた書籍や、ブログ、インターネット上の解説記事は、いわゆる上等なテクニックや慣れが必要なことが非常に多いです。(「褒め方、叱り方」というものはその典型例です)
もちろんそれらを少しずつでもマスターしようとされる保護者の皆さんがいらっしゃるのは社会にとって、非常に喜ばしいことです。
一方で「そんな難しいことできない」と思われるテクニックや場数が必要な技術なども多いのではないでしょうか。
多くの子供の勉強を常日頃から拝見している私でさえ、これは難しいテクニックだなと思わされる指導法なども世の中には多いです。
この記事は明日からでもできるただ1つのことに関してだけ絞って解説しています。
読者の皆さんのもとにこのメッセージが届き、明日から皆さんの行動が少しでも変わると嬉しいです。
親が勉強すること、ただそれだけ。

結論から申し上げますと「親・保護者が家庭でも勉強すること」が最も行動に移しやすい方法です。
とはいえ、説明も何もなく親がただ勉強しろと言われても、
それで、行動に移してみようと思うほど、大人は暇ではないことは存じ上げています。
そこで科学的な理屈と、それに対応する経験論でこれをおすすめする根拠を説明してまいりましょう。
科学的な根拠
科学的に「親の勉強」という行動が「子供の勉強」につながる理屈を説明する際に意識すべきキーワードは
「ミラーニューロン」と「ピア効果」です。
ミラーニューロンとは
「マンガでよくわかる 子どもが勉強好きになる子育て」では以下のように語られています。
子どもは基本的に親の言うことを聞かないものですが、親の言葉には耳を貸さなくても、親の行動は無意識に真似してしまいます。
脳科学的では人間の脳には目の前にいる人の動作や意図、感情までも映し取る脳細胞があることが知られています。
グルメ番組で美味しそうなものを見て、同じものを食べたくなったり、
他人が痛い思いをしている所を見て、自分も痛い気がしたり、
こういうのもミラーニューロンの働きです。
この脳の働きによって「子は親の背中を見て育つ」という言葉を説明することができます。
親が勉強をしていれば、自然と子どもも勉強してしまうというわけですね。
ピア効果

ピアというのは同僚という意味です。
日本では、会社の上司がまだ帰っていないから帰れないなんていう、マイナスのイメージで使われることも多いですが、(負のピア効果といいます。)
周りが勉強する友達だらけだと、その子も勉強するようになったりするポジティブな効果もあります。
「最短の時間で最大の成果を手に入れる 超効率勉強法」では「ピアプレッシャー」という言葉を使って説明されています。
大人も図書館やコワーキングスペースのようにみんなが勉強や仕事をしている環境なら勉強ができるという経験をしたことは少なからずあるでしょう。
ご家庭でもこの効果を生み出すべく、家族が勉強を家庭でするのが当たり前になると
子供もそれを当たり前のように感じるようになるわけです。
経験論からサポートする
今度は経験論から親・保護者が家庭で勉強することの重要性をサポートしていきます。
子どもの指導をする塾講師なども経験で知っている事実
「合格する親子のすごい勉強」を書いていらっしゃる松本さんは塾を運営なさっている方らしいですが、
その著作の中で、親が何かに打ち込んでいる姿を見せたり、
親が探求心を持ち、調べる癖をつけたりすることの重要性を語っています。
「1日10分で大丈夫! 「自分から勉強する子」が育つお母さんの習慣 」を書いていらっしゃる村上さんも塾の代表をなさっていますが、
知識があるということがかっこいいという家庭文化が重要であると述べていたり、
調べる楽しさを親子で共有することの重要性を述べていたりします。
いずれにせよ、親が勉強にポジティブに関わっていき、
さらに自らも勉強を楽しむ姿勢を持つことが重要であるのは間違いありません。
まとめ
ここまでで一旦まとめておきます。
お子さんの勉強のやる気を引き出すためには、「保護者・親御さんが自ら勉強をする姿勢を見せること」が重要だと説明してきました。
記事冒頭でも述べましたが、世の中にはいわゆる「子育て本」というのが様々ありまして、
私も塾講師という仕事柄、それなりの数は読んできています。
その中には塾講師の私でも簡単には身に付かなかった
「ほめる技術」であったり、
「叱る技術」であったり、
はたまた、徹底するのがそれなりに難しい「家庭でのルール」
というのが書いてあったりします。
大人といえど、親も先生も人間ですから、感情的になるのは良くないと言われても感情的に叱ってしまったり、
ほめるのが少し下手だったり、
はたまた忙しさのせいでせっかく作ったルールを徹底できなかったりします。
そんな中、「勉強する姿勢を子どもに見せる」というのは
かなり具体的な案であると同時に
行動に移しやすく、
そしてテクニックを必要としないという面で優れた1つの方法であると私は考えています。
ですので、私の一押しの「家庭で出来る」子どもの勉強のやる気を引き出す方法としてご紹介することにしました。
参考になりましたでしょうか。
番外編【何を勉強すればいいの?】
ここまで読んでくださった読者の皆さんの中には
「じゃあ具体的に何を勉強すればいいのか」
といった問題が出てくる方がいらっしゃるでしょう。
世間一般には「お金に関連すること」「キャリアに関すること」「小中高で習うことの学び直し」など、
さまざまなブームがあり、それらに関する書籍は大量に出版されています。
今後新たに記事を書き足していく予定ではありますが、
私は塾講師という立場もありますので、
「小中高で習うことの学び直し」と「読書」
の2つをおすすめします。
今後少しずつ記事を追加していくので、お待ちくださいませ。
それではまた、所長でした!
参考図書リンク