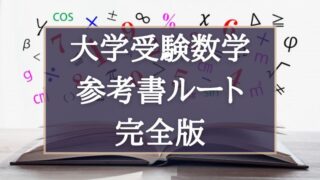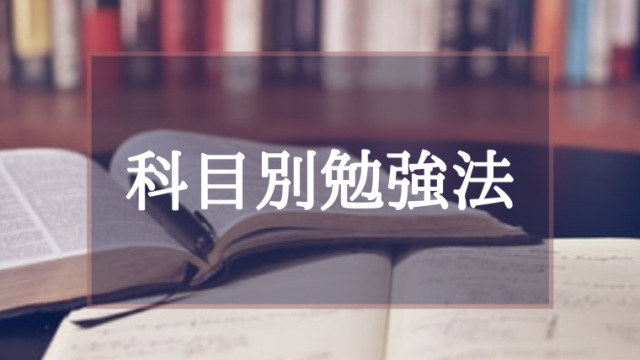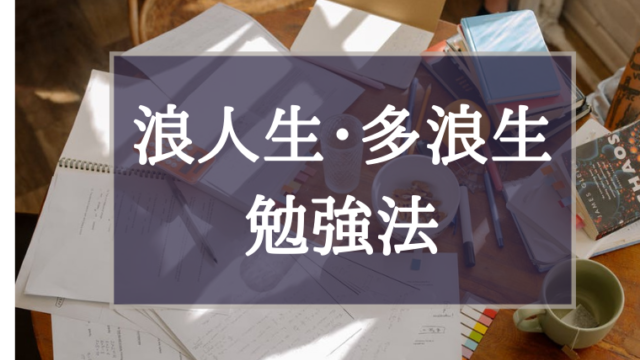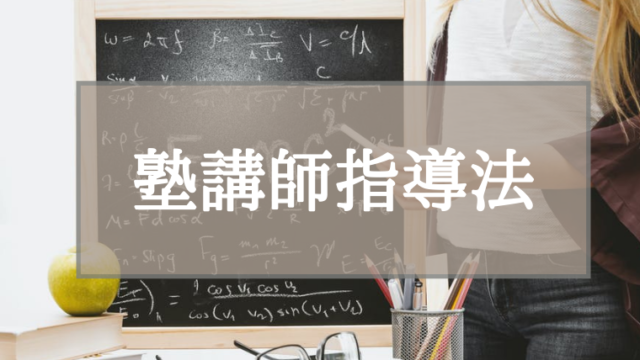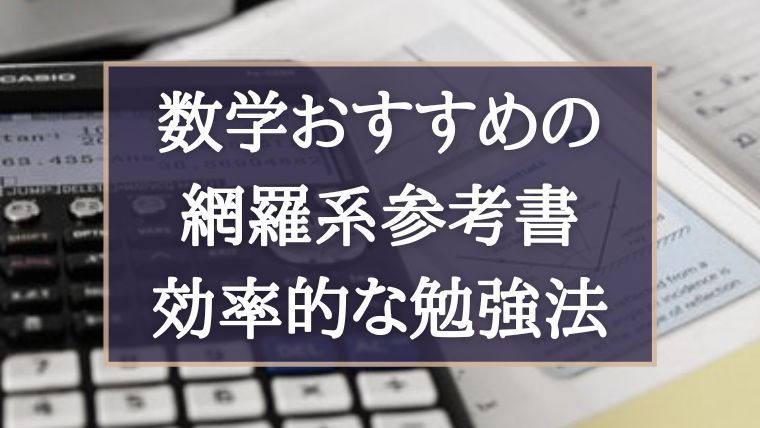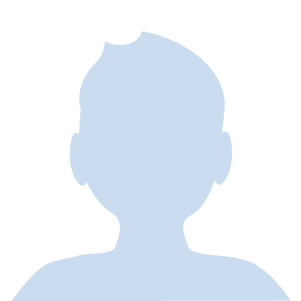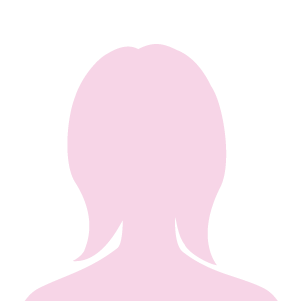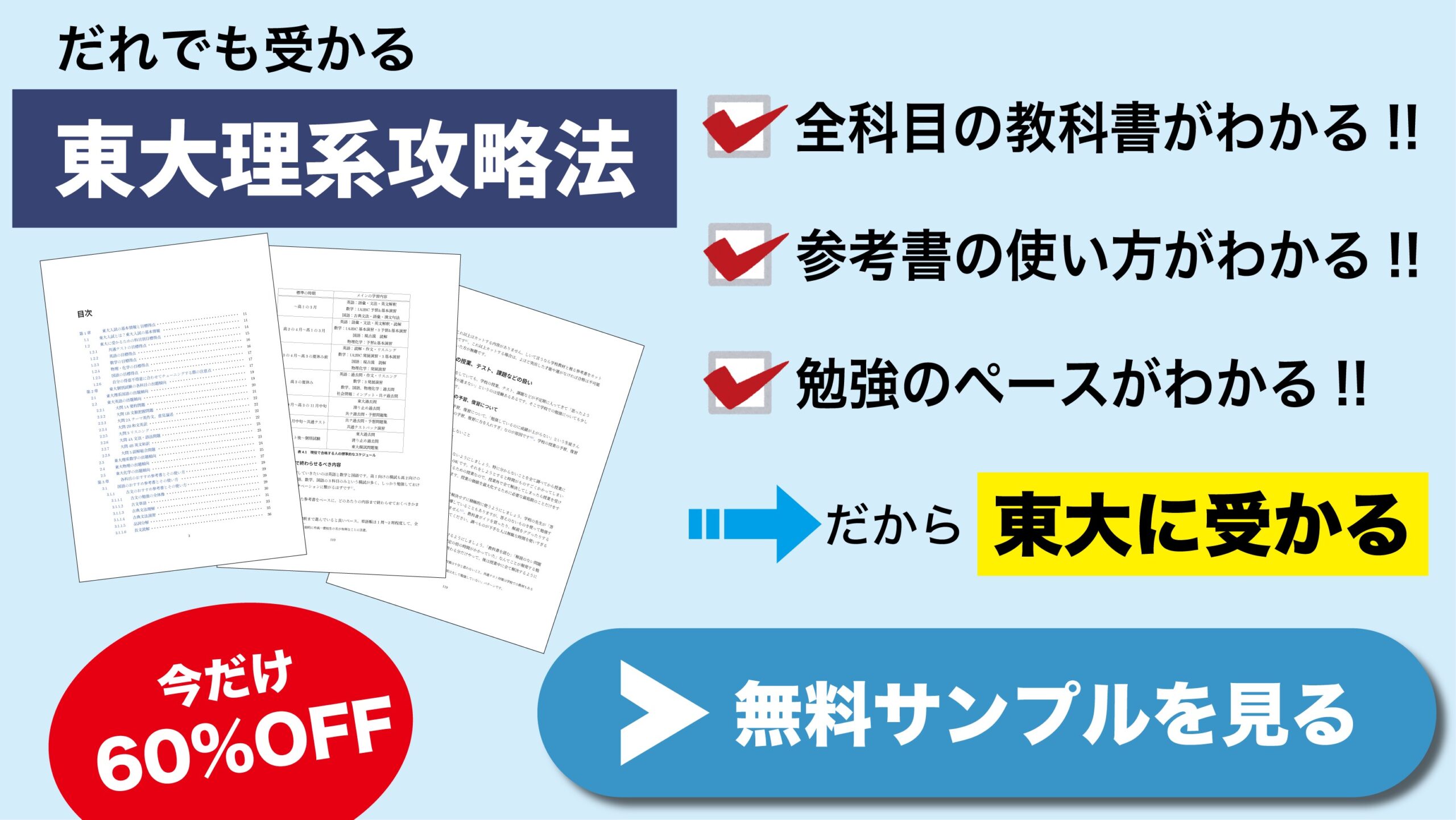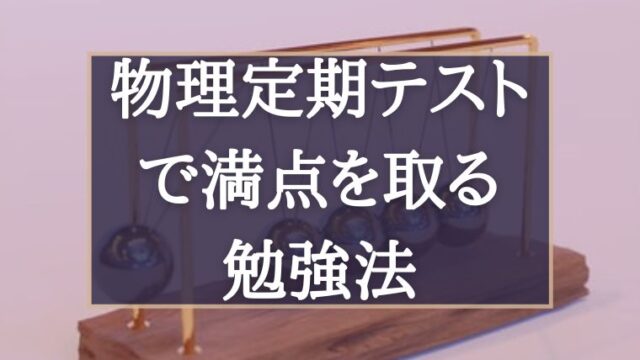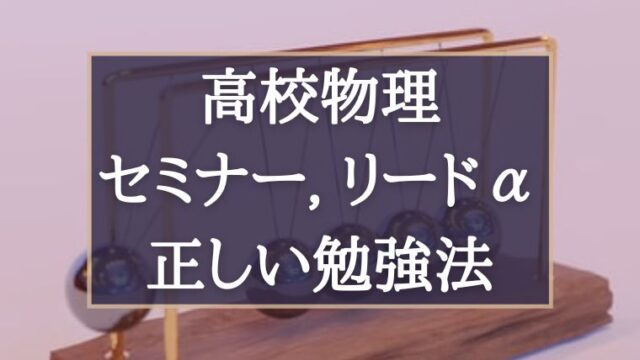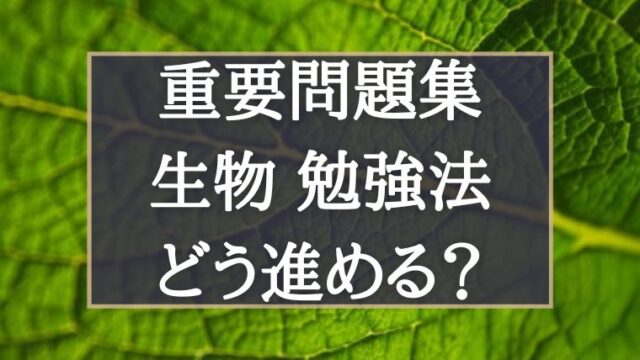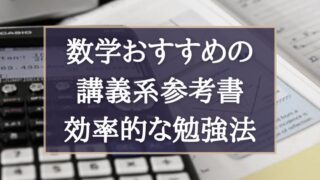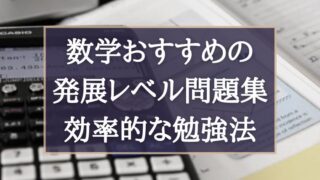ども、ぽこラボ所長です!
この記事では青チャートなどの網羅系参考書について解説します!
このように思ったことはありませんか?
この記事を読めば、「どの教材を選んで」「どう勉強すべきか」全て理解できます。
この記事の内容は次の通り。
- 参考書ごとのレベル比較
- どの問題レベルまで解くべきか
- おすすめの使い方・勉強法
「安心して選んで勉強したい」という人はぜひこの記事を読んでくださいね!
目次
網羅系参考書ごとのレベル比較、問題ごとのレベル比較

最初にレベルについて解説していきます。
基本的には次の2つに関して着目しておけば十分でしょう。
- 参考書ごとのレベル比較
- 問題ごとのレベル比較
参考書ごとの比較、どの参考書をやればいいか
網羅系参考書で有名なのは次の3シリーズです。
- 数研のチャート式シリーズ
- 啓林館のフォーカスゴールドシリーズ
- 東京書籍のニューアクションシリーズ
チャート式シリーズには易しい順に、白チャート、黄チャート、青チャート、赤チャートがあります。
2022年度の高1からは指導要領が新しくなるので、参考書も順次改定されているところです。
フォーカスゴールドシリーズは2022年の高1生からは無印のフォーカスゴールドと、フォーカスゴールドスマートの2種類あって、スマートの方が易しい問題集になっています。
ニューアクションシリーズは2022年の高1生からはニューアクションレジェンドと、ニューアクションフロンティアの2種類になっていて、フロンティアの方が易しい問題集になっています。
それぞれどれくらいのレベル感なのか、以下の5種類のレベルに分けて表にしてみます。
- 公式運用のみで解けるレベル
- 教科書練習問題レベル
- 共通テストレベル
- MARCHレベル
- 早慶旧帝大レベル
| 公式 | 教科書 | 共テ | MARCH | 早慶旧帝 | |
| 白チャート | 〇 | ◎ | 〇 | △ | △ |
| 黄チャート | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | △ |
| 青チャート | △ | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 |
| 赤チャート | × | △ | 〇 | ◎ | ◎ |
| FG | △ | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 |
| FGスマート | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | △ |
| NAレジェンド | △ | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 |
| NAフロンティア | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | △ |
それぞれの出版社の公式ページにも教材難易度の比較表があるので、正確なものが知りたい方はこちらからご覧ください。
チャート式の比較
https://www.chart.co.jp/goods/item/sugaku/level/level2.html#chart
フォーカスゴールドの比較
https://www.shinko-keirin.co.jp/keirinkan/kou/math/focus-series-lp.html
ニューアクションの比較
https://ten.tokyo-shoseki.co.jp/text/hs/pamphlet-kyozai/sugaku_kyozaipamph.pdf
多くの学校では、これらのどれかを副教材指定されて配られていると思います。
白チャートだけは志望大学によっては易しすぎるので、注意が必要ですがそれ以外は学校で指定されているものを使う形で問題ありません。
もしどれも持っていないのであれば、青チャートを使うのが1番おすすめです。
難関大学を狙う場合は、網羅系参考書以外の参考書も進めることになるので、ペースも意識したいですね。
数学の勉強全体の流れについてはこちらで解説しています。
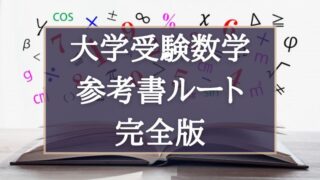
ペースについてはこの記事で後述します。
問題ごとのレベル比較、どのレベルまでやればいいか
上で紹介した各問題集は問題集の中で各問題にレベル分けがなされています。
多くの方におすすめなのは、青チャート、フォーカスゴールド、ニューアクションレジェンドあたりなので、その3つに関して問題のレベルを見ていきます。
青チャートとニューアクションレジェンドは各問題がそれぞれ5段階にわかれていて、それらのレベルが大体以下の通りです。
レベル3まで
日東駒専合格圏内、共通テスト8割まで
レベル4まで
共通テスト8割以上、MARCH合格圏内
レベル5まで
地方国公立・早慶合格圏内
たとえば、レベル4まで全ての問題を解ける状態(ランダムに小テストしても解ける状態)になっていれば、共通テスト8割以上を狙えるようなイメージで見てください。
実際のところレベル4まで完璧にしようと思って進めていてもなかなかレベル4まで「完璧」になる人はいないので、他の参考書や過去問などでもしっかりトレーニングを積むことが必要になることが多いですね。
フォーカスゴールドの場合は4段階に分かれています。
レベル2まで
共通テスト6割まで
レベル3まで
共通テスト8割以上、MARCH合格圏内
レベル4まで
地方国公立・早慶合格圏内
フォーカスゴールドは、上で紹介した他のシリーズと違ってレベルが4段階に分かれているので、レベル2~3あたりが少し幅が広いイメージです。
おすすめの使い方、勉強法

続いておすすめの使い方、勉強法について解説していきます。
次の2つに分けて説明していきますね!
- 具体的な勉強手順
- 周回の手順
具体的な勉強手順
最初は勉強の手順です。
具体的には以下の手順で進めていきます。
- 時間を計りながら問題を解く
- 解説を丁寧に全て読む
- 間違えた問題は解説を閉じて解き直す
- 印をつけて2周目に備える
時間を計りながら問題を解く
問題を解くときには必ず時間を計りながら解くようにしましょう。
時間に縛りなく考え続けられることは悪いことではありませんが、大学受験を意識する上ではテンポ良く先に進んでいくことも重要です。
例題1つあたり10分~15分くらいを目安に解き進めるといいでしょう。
数3など一部の問題では解き方は分かっても時間がかかる場合もあると思います。
そういった場合のみ例外的に20分くらいまで伸ばしてもいいですね。
このときに計算などを飛ばして「解き方をインプットしていくだけ」といった勉強は絶対にしないように。
雑でも構わないので、紙に計算や解いた結果を残していくようにしてください。
手を動かす練習が少ないと計算力が最後までネックになってしまいますのでご注意を。
解説を丁寧に全て読む
解説は飛ばすことなく全て丁寧に読みましょう。
※バツ直しなどで、解説を読むのが2回目以降になる場合は問題が解けていたらパスでもかまいません。
特に例題のすぐ下にあるヒント・考え方の部分や、欄外のメモのようなものも絶対に読み飛ばさないようにしてください。
そこに書いてあることが実は1番重要だったりします。
間違えた問題は解説を閉じて解き直す
間違えた問題も解説を読んで理解できたら、解説を閉じて自力で解けるかチェックしましょう。
理解したつもりになっていたけど、解説を閉じて手を動かしてみると意外と解けないということもよくあります。
解答の流れを理解できていない場合や、細かい計算の方法を忘れてしまった場合など、原因は様々ですが、その場で解き直すことで「分かったつもり」を防ぐことが可能です。
印をつけて2周目に備える
しっかり理解したら、印をつけて終わりです。
以下のように分けて印をつけるのがおすすめなので、試してみてください!
◎自力で解答できた
◯凡ミスした
△解説を読んで理解した
×解説が理解できなかった
2周目以降は◎以外を解き進めて、印を更新していくと良いでしょう。
網羅系参考書1冊まるまる◎にできれば、一部の最難関の問題を除いて、ほとんどの問題に対応できるようになっているはずです。
(補足)解説を読んでも分からなかった場合
独学で進めていると、解説を読んでも理解できないということもあるはずです。
そういった場合には次のようなアクションを取りましょう。
- 問題文と解説をイチから読み返す
- 分からなかった部分だけ置いておいて続きが理解できるか確認する
- (先生や友達に質問する)
- それでも分からなかったら2周目に回す
まずは問題文と解説を最初から読み返します。
「問題文に書いてある条件を忘れていただけ」というのはあるあるです。
解説も計算式は力を入れて読んでいるけど、日本語の説明部分は軽く読み流しているという人が経験上多いですね。
注意してください。
また、部分的に分からなくてもその続きを読み進めるのは重要です。
1つのイコールが分からなくても続きは理解できる可能性は十分あります。
それでも分からなければ先生や友達に質問するのもありですね。
質問する相手がいなかったら2周目以降に回してもOK。
分からなかった箇所よりも前の問題で勉強した知識が十分に定着していない場合には、2周目で改善することがあります。
ちなみに解説を読んでも理解できない問題が3割を超えるようならレベルが合っていません。
簡単な問題に集中して周回するか、簡単な問題集に変えるかした方がいいでしょう。
周回の手順
続いては周回の手順です。
網羅系問題集は1周した所で全然身につかないので、何周もして徐々に定着させていくのが基本です。
周回ごとに勉強内容を少しずつ発展させていくのが良いでしょう。
ここでは例を示します。
例↓
1周目
例題のレベル1〜3のみ
2周目
1周目で間違えた問題
レベル1〜3の練習問題
3周目
2周目で間違えた問題
レベル4〜5の例題
4周目
3周目で間違えた問題文
レベル4〜5の練習問題
5周目
4周目で間違えた問題
章末問題
6周目
5周目で間違えた問題
この例のように周回ごとに扱う内容を少しずつ発展させて、勉強していくのがおすすめです。
1周の間に扱う内容を絞ることで、周回のスピードを速めることができます。
スピードを速くする方がモチベーションも続きやすいので、参考にしてみてくださいね!
例題だけでも大丈夫?
よくある質問として、
というものがあります。
結論から言えば大丈夫です。
というのも、網羅系参考書を全てしっかり解けるようになるには現実的に時間が足りないという人の方が圧倒的に多いからですね。
それをするくらいなら最初から過去問演習をした方がよほどマシです。
数学に限らず理系科目に関しては読んで勉強した所で、手を動かしていないと何も身に付かないので、読めば読むだけ時間を無駄にしてしまいます。
例題だけに集中的に取り組むのであれば、しっかり手を動かして1つ1つの問題をその場で覚え切るくらいの意気込みで進めていきましょう!
受験を意識したスケジュール

最後に受験を意識したスケジュールについて解説していきます。
次の3つのパターンに分けて解説していきますね。
- 1A2Bまででいい場合
- 数3も必要な場合
- 理系最難関大を目指す場合
1A2Bまででいい場合
文系受験生や、理系の中でも薬学部や獣医学部、看護学部などの一部は1A2Bまでで受験可能です。
この場合はそれほど焦って勉強する必要はありません。
高2の終わりまでに青チャートのレベル3の問題あたりまで出来ていればかなり順調と言っていいでしょう。
必要に応じて高3の夏休みまでにレベル4以降もしっかり学習するので十分間に合います。
数3も必要な場合
数3も必要な場合はペースが非常に重要になってきます。
大学受験を考えるのであれば、高3の夏休み前までには全範囲習い終えておきたいのですが、学校の授業は10月以降になってようやく習い終えるというのもよくあるからですね。
必要に応じて、映像授業や講義系参考書を使って、独学で予習をし、該当する単元を網羅系参考書でも進めていきたいところです。
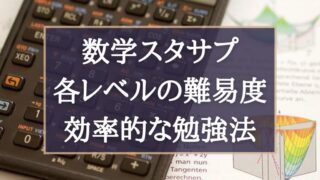
高3の夏休み前までには数3も含めて、青チャートのレベル3相当の問題までは一通り解けるようになっておきたいところです。
理系最難関大を目指す場合
東大、京大、東工大などの理系最難関大を目指す場合にはさらに速いペースで勉強しておくべきです。
具体的には、高3のGWまでには数3も含めて、青チャートのレベル3相当の問題までは一通り解けるようになっておきたいところ。
できれば1A2Bはレベル5まで解ける方が好ましいですね。
学校で習っている範囲は、学校のペースに合わせて進めていき、定期テストあたりではレベル5まで解ける状態にするとともに、高2のうちに独学で予習を始められると安心です。
高3の夏休み前には網羅系参考書は数3まで含めてどのページを開いても解ける状態にしておけるといいでしょう。
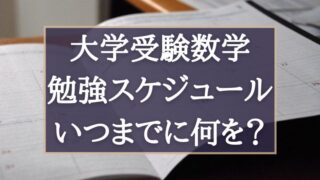
まとめ
この記事では、
- 問題集ごとの比較
- 問題ごとの比較
- 使い方についてのアドバイス
- スケジュールについてのアドバイス
をしていきました。
どの問題集を選んだかでは、それほど大きな差は開きませんが、勉強法やペースを間違えると大きな差が開くので注意してください!
それではまた、所長でした!