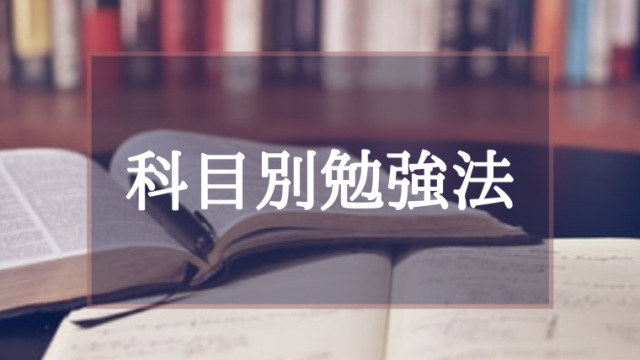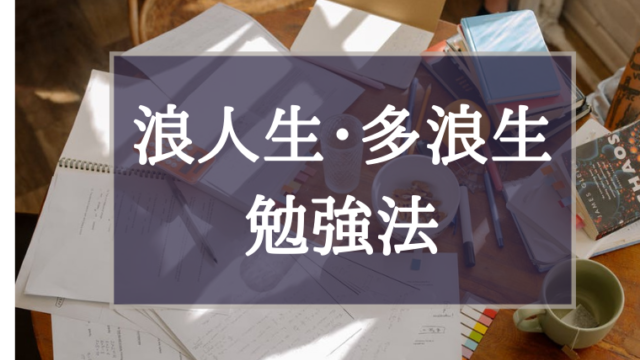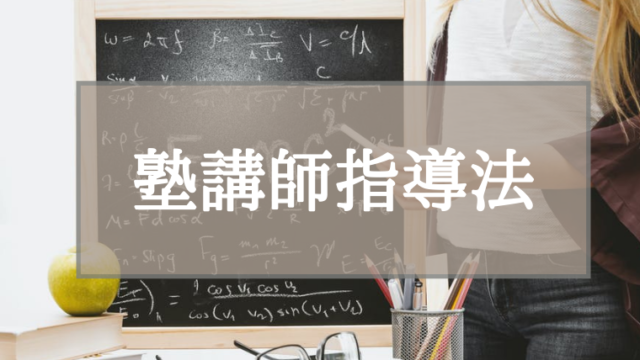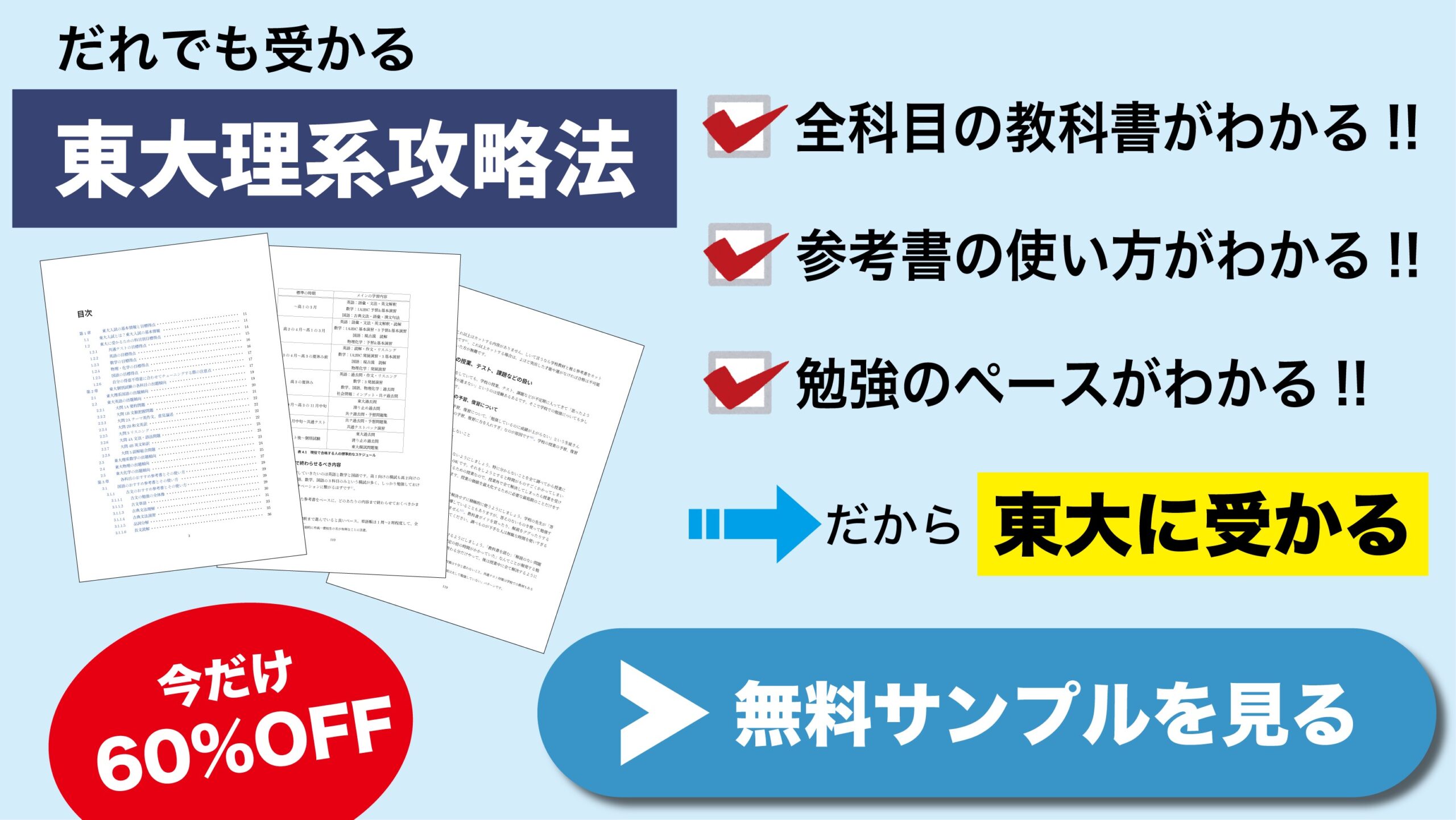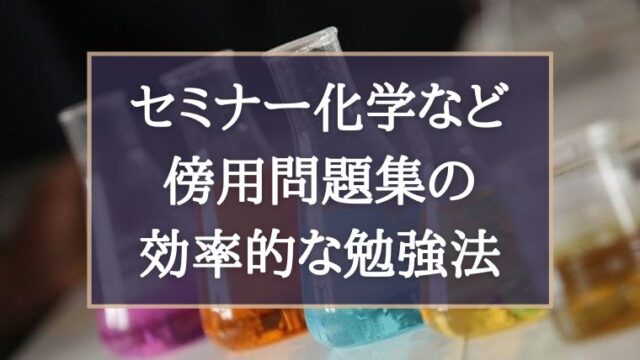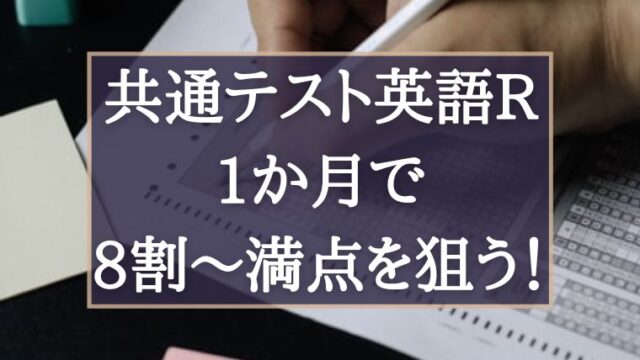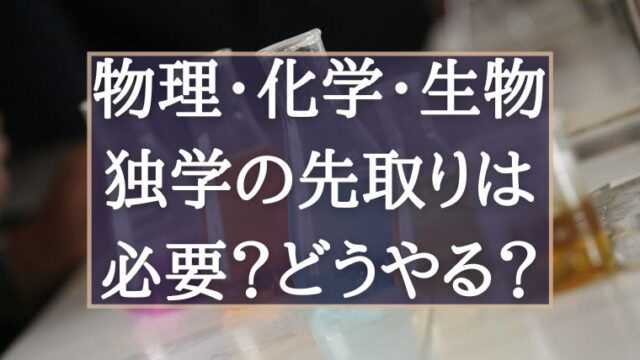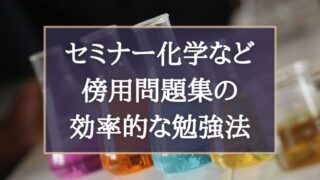化学入門・基礎・標準問題精講の使い方と注意点|どれを使えばいいかなど

ども、ぽこラボ所長です!
今回は化学の問題精講シリーズについて。
セミナーをやるのはしんどすぎるから、少し薄い問題精講シリーズってどうなの?
どのレベルから始めればいいの?
そんな風に思っているあなた向けの記事になっています。
この記事を読めば、問題精講シリーズのどのレベルから始めるのが最適か分かりますし、正しい勉強法も分かります!
ぜひ参考にしてくださいね!
この記事の内容は以下の通り。
- 問題精講シリーズのレベル感、到達点
- 正しい使い方、勉強の手順
- 勉強する際の注意点
それぞれ解説していきます!
目次
問題精講シリーズのレベル感、到達点
まずは化学の問題精講シリーズのどれがどのくらいのレベル感なのかを説明していきます。
順に見て行きましょう。
入門問題精講のレベルと到達点について
入門問題精講に関しては、未習範囲がまだ残っている高1高2、受験生などが使うのにピッタリのレベルです。
新単元を講義系参考書や映像授業で学習した後、問題で確認するときに使うと丁度いいでしょう。
これを完璧に出来るようになると学校のテストレベルであれば、かなり高得点を狙えるようになるはず。
※偏差値70くらいの高校に通っている人は、これだけだと厳しいですが、、、
また過去問演習さえすれば、共通テストでも60%くらいまでならギリギリ狙えるような所までは到達可能なはずです。
もちろんこれは、共通テストの過去問・センターの過去問をキッチリやること前提ですので、問題集だけでは難しいことは断っておきます。
基礎問題精講のレベルと到達点について
基礎問題精講に関しては、授業や参考書で未習範囲を全て習い終え、入門問題精講レベルの簡単な確認問題レベルは完璧に出来るようになった人にピッタリのレベル感です。
ここから問題演習がメインになる受験生がメインの参考書として選んで学習することが可能でしょう。
この問題集を全て解ける状態にして、過去問演習もすると共通テストでは80%くらいまでなら狙えるはずです。
同様に日東駒専くらいの偏差値帯から、ギリギリMARCHくらいまでなら、ここまでやれば過去問演習に入っても大丈夫でしょう。
標準問題精講のレベルと到達点について
標準問題精講に関しては、基礎からレベルがグッと上がって、共通テストレベルであれば、満点近い点数を取れる人でないとおすすめはしません。
共通テスト満点レベルから、早慶や旧帝大レベルの過去問までは、かなりギャップがあるのですが、そのギャップを埋めるのに丁度いいのが、標準問題精講のレベルです。
数学の標準問題精講よりは難しめで、物理の標準問題精講よりは簡単めなので、このシリーズは科目ごとに難易度が違うのは注意が必要です。
レベル感のまとめ
レベル感をまとめた表が以下の通りです。
| シリーズ | 使用者のレベル | 到達点 |
| 入門 | 未習範囲がまだ残っている高1~受験生 | 受験超基本、共通テスト60%くらいまで |
| 基礎 | 一通り習い終わって演習中心の学習となる受験生 | 共通テスト80%くらいまで。日東駒専~ギリギリMARCHの過去問演習の手前まで |
| 標準 | 共通テスト満点近い点数&ここから最難関大の過去問演習の準備に入る受験生 | 早慶、旧帝大レベルの過去問演習の手前まで |
正しい使い方、勉強の手順
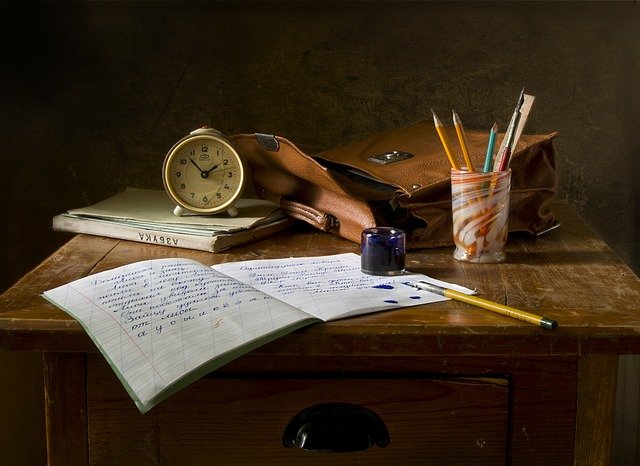
レベル感を理解したうえで、次に具体的な勉強の手順について解説していきましょう!
具体的な手順は以下の通りです。
- 問題を時間を計って解く
- 解説を隅から隅まで読み込む
- 覚えていなかったものを資料集でチェックする
- 解説を閉じて解きなおす
- バツ印をつけて次に進む
- 1周終わったらバツ印の所の2周目、3周目と繰り返す
1つずつ補足していきます。
問題を時間を計って解く
まず問題を解くときに時間を計るのは常識と思っておきましょう。
のんびりやりすぎても受験では不利になりますし、1時間で何問くらい進むのかを知らないと計画的に勉強することができません。
入門については1問5分、基礎については1問10分、標準については1問15分程度を目安に解きましょう。
それ以上かける必要はありませんし、1周目に関しては、2~3分解き方が思い浮かばなければ、すぐに解説に移ってしまってかまいません。
解説を隅から隅まで読み込む
問題精講シリーズに関しては、解説が非常に充実しています。
解説を読み飛ばしていては正直、問題精講シリーズを利用する意味がありません。
隅から隅まで全て一言一句読み飛ばすことなく読みましょう。
解説が充実している分、問題数は他の問題集と比べて多くないので、ここをサボっていてはただただ楽をしてしまって、成績が伸びにくくなってしまいます。
覚えていなかったものを資料集でチェックする
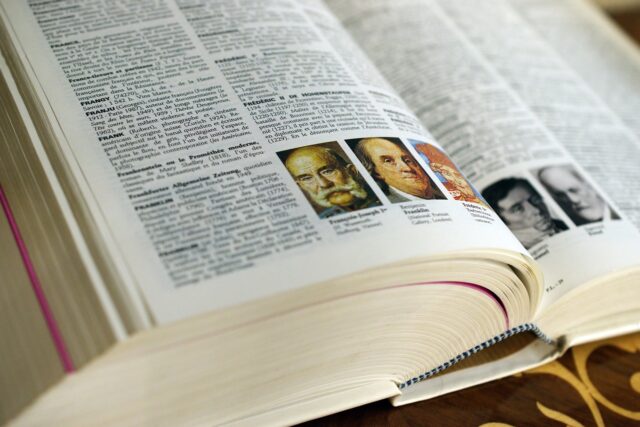
解説中に覚えていなかった内容がちょこちょこと出てくることがあるでしょう。
覚えていなかった内容に関しては、確実に資料集で調べるようにしてください。
正直、問題精講シリーズであれば、資料集に目を通さなくても問題を理解出来るだけの解説は書いていますが、そこだけに頼っていてはいつまで経っても細かい部分が覚えられません。
セミナーのような問題数の多い問題集であれば、「暗記してもらうためだけに作られた問題」のようなものもあるのですが、問題精講シリーズに関しては、そういった問題は多くはありません。
ですので、情報は自分で増やしにいく姿勢が重要です。
解説を閉じて解きなおす
解説を読んで理解したら、解説を閉じて自分の力だけで解きなおすことが出来るか確認です。
これをやっておかないと「分かったつもり」になってしまう方が大勢います。
特に、「頭の中で計算方法だけ思い起こす」といったサボり気味の復習は何の意味もありません。
確実にその場で手を動かして解きなおしをしましょう。
これをすることで2周目、3周目のペースがだいぶ上がります。
バツ印をつけて次に進む
その場での解きなおしまで終わったら、間違えた問題にはバツ印をつけて2周目以降に進んでいきます。
こういった問題集に関しては、2周目3周目の負担を少しでも減らしていくことが重要です。
バツ印がついていなければ、2周目も全ての問題を解かなければならないので、無駄な時間をずいぶんと費やさなければなりません。
1周終わったらバツ印の所の2周目、3周目と繰り返す
2周目は1周目で間違えたもの、3周目は2周目で間違えたものだけを解いていけばOKです。
自信がないからと言って、前の周で解けたものまで解いていては他の受験生よりも進むペースが遅くなってしまって差をつけられてしまいます。
注意しましょう。
勉強する際の注意点

化学の問題精講シリーズを使うときの注意点についても補足しておきましょう。
注意点は以下の3つです。
- 薄い分、レベル感に要注意
- 問題数が少ないので、網羅度は他の問題集より低い
- 1冊で完璧になったと思わないこと
それぞれ解説していきます!
薄い分、レベル感に要注意
他の問題数と比べると1冊あたりは薄くできているので、適切なレベル感を外してしまうと使う意味が一気になくなってしまいます。
セミナーなどは問題数が多い分、広いレベル感をカバーしているので、それとは全然タイプが違うということだけは覚えておきましょう。
問題数が少ないので、網羅度は他の問題集より低い
問題数が他の問題集より少ないので、網羅度という意味では問題精講シリーズはそれほど高くはありません。
もちろん解説の中に必要な内容はほとんど書かれているのですが、「問題を通して」でないと覚えにくい内容も解説にしかないことがあるので、その点だけは注意が必要です。
特に有機や無機などの覚えることが多い分野に関しては、若干物足りなさはあります。
1冊で完璧になったと思わないこと
他の問題集でも同じことは言えますが、1冊完璧にしたところで、受験で満点を取れるわけではないことは最初から理解しておきましょう。
どこの大学を受験する場合でも、最低限、過去問は必要ですし、過去問までに数冊必要になる大学も少なくはありません。
まとめ
今回は化学の入門問題精講、基礎問題精講、標準問題精講について解説しました。
解説が厚くて良い問題集なので、ぜひこの記事を参考に取り組んでみてください!
それではまた、所長でした!
こちらの記事もぜひ参考にしてください!