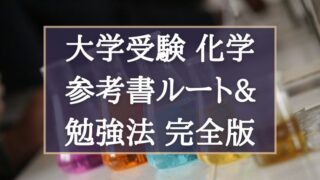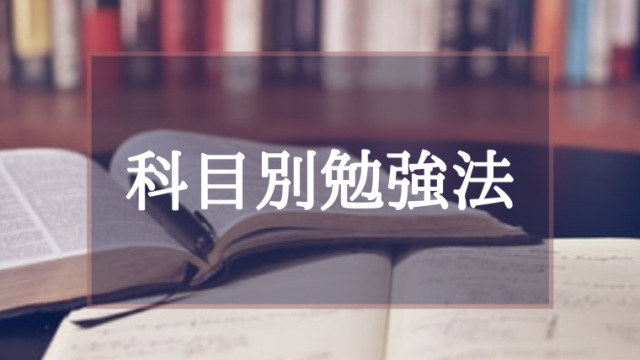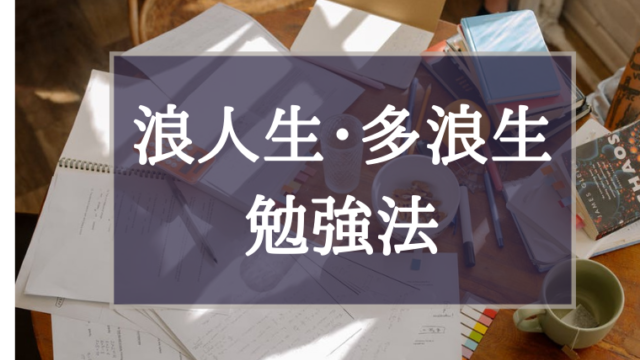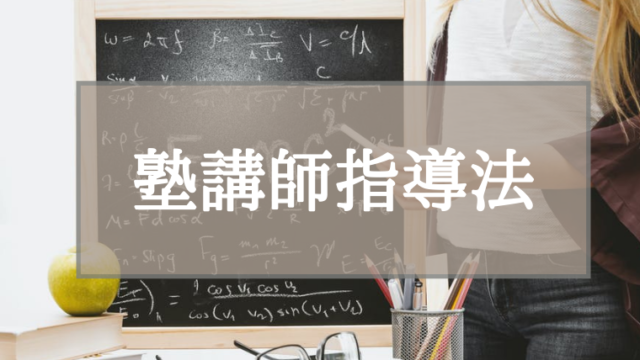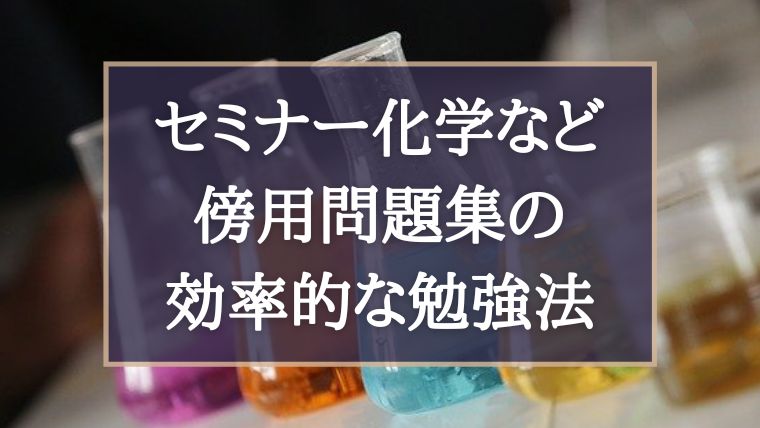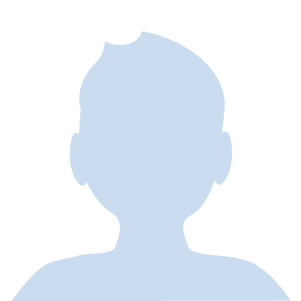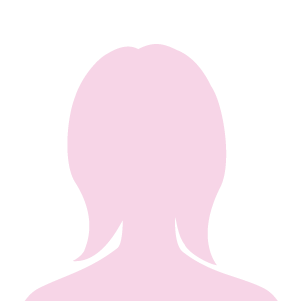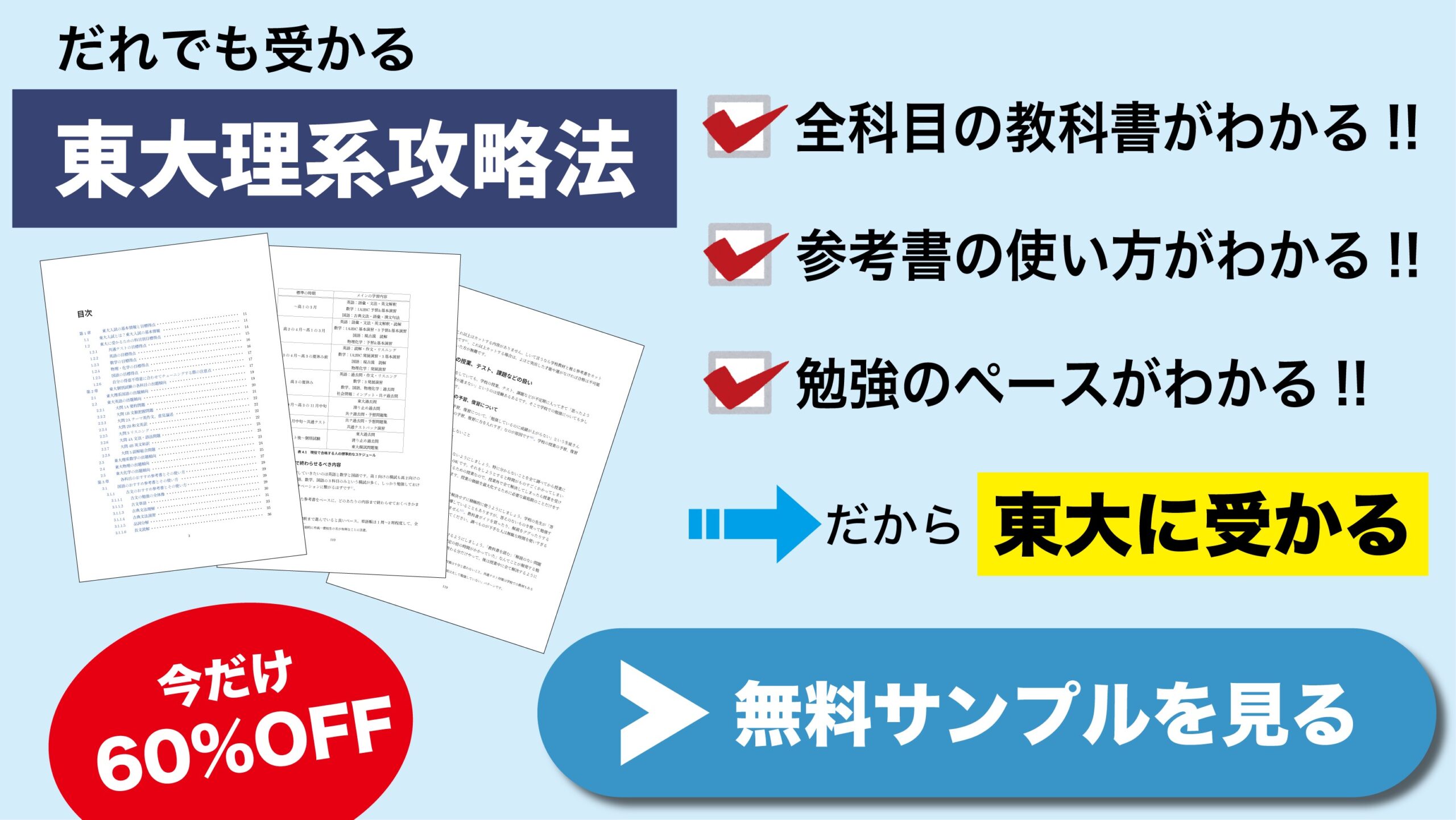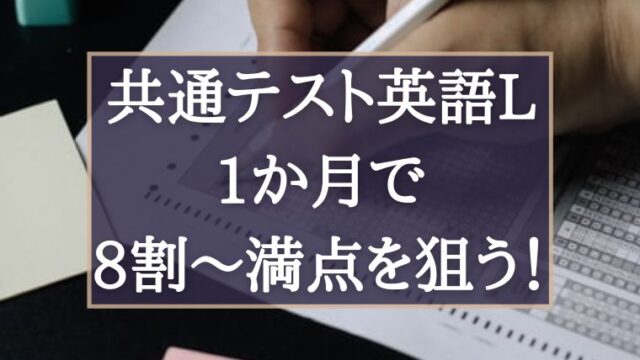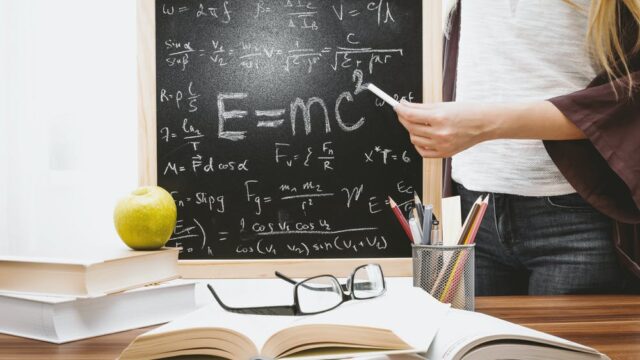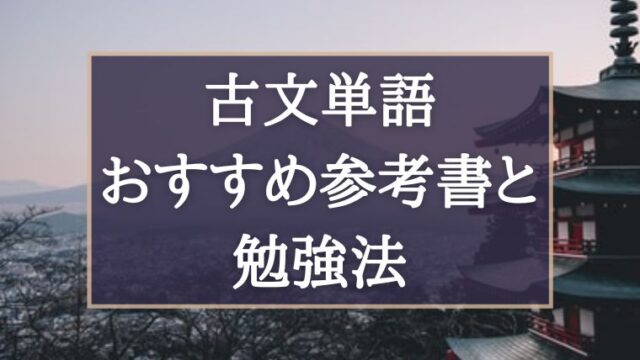ども、ぽこラボ所長です!
今回はセミナー化学、リードα、センサー、エクセルなどの学校採用系の化学の教科書傍用問題集について。
そんな風にお悩みではありませんか?
この記事を読めば、「どうやって進めるのがベストなのか」「どのレベルの大学まで行けるのか」「どんなペースで進めればいいのか」 すべて理解できます!
この記事の内容は以下の通り。
- セミナー化学の効率的な使い方
- セミナー化学の理想のペース
- セミナー化学でどのレベルの大学まで到達できるか
※代表的な参考書としてセミナーを選んでいますが、「リードα」「センサー」「ニューグローバル」「エクセル」などでも勉強法は基本的に同じです!
読み終えたころには、「これなら頑張れる!」とモチベーションが少し上がっているはずですよ!
それぞれ解説していきます!
目次
セミナー化学の効率的な使い方・勉強法

まずは使い方から。
手順は以下の通りです。
- 進めるべき単元を授業や参考書で習う
- 時間を計って解く(基本は1問5分、発展は1問5~10分)
- 解説を丁寧に読む
- 資料集に目を通す
- 間違えた問題、理解できなかった問題に印をつける
- 暗記すべきものを暗記する
それぞれ簡単に説明していきますね!
進めるべき単元を授業や参考書で習う
まずは問題集ではなく授業や参考書で基本的なことをインプットしてください。
さすがにインプットゼロ状態から始めても解けなすぎて嫌になってくるはずなので。
もちろん学校の授業で習っている範囲に関しては問題を解く所から始めてもOKですが、「習っていない範囲」や、「習ったけど授業についていけていない範囲」は、映像授業や講義系参考書で勉強することができます。
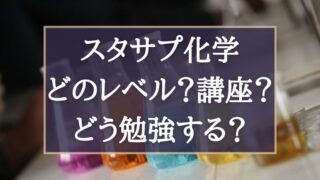
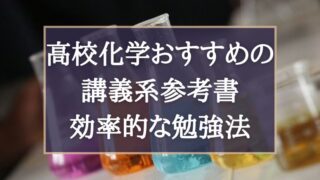
時間を計って解く(基本は1問5分、発展は1問5~10分)

問題を解くときには時間を計りながら解き進めましょう。
基本問題レベルは5分、発展問題でも最大10分程度考えて分からなければ、飛ばしてしまってOKです。
紙でもタブレットでも良いですが、確実に解いた痕跡を残してください。
もちろん計算問題は計算を自分の手で行ってください。
セミナーなどの中にそれほど手間のかかる「めんどくさい計算」はありません。
もし面倒に感じるのであれば、自分の常識を問題集側(入試側)にフィットさせていく必要があります。
実際の入試問題にはもっともっと手間のかかる計算もありますし、大学に入ったらさらにその傾向は強くなります。
解説を丁寧に読む
1周目に関しては正解している問題も解説は丁寧に全て読みましょう。
特に化学の場合は、暗記していなければ解けない問題も多いので、正解している問題も1周目は確実に解説を読んでおくほうが良いでしょう。
その方が頭に残ります。
また選択問題に関しては、たまたま正解していただけのこともあります。
資料集に目を通す
さらに資料集も該当範囲にザっとで良いので目を通すようにしましょう。
資料集に載っている程度のことは入試でも普通に出てくることなので、「学校で習わなかった」のような言い訳をせずに覚えるべきことは覚えるスタンスが重要です。
問題集、資料集に書いてある程度のことは全暗記が正しいスタンスです。
間違えた問題、理解できなかった解説に印をつける
間違えた問題には印をつけて2周目に備えましょう。
解説を読んでも理解できなかった問題もあるかもしれません。
資料集を確認しても理解できなかった場合は、そこにも印をつけておいてパスしてしまってOKです。
2周目には自分の力も上がっていて、解決することが多いので、気楽にパスする癖も大事です。
この場合は、先に1度単元ごとの復習をしつつ、復習をした単元から進めていく方針の方がいいでしょう。
映像授業や講義系参考書で勉強し直すことができます。
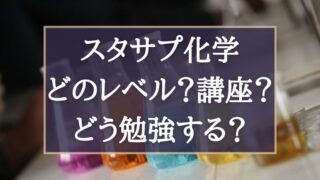
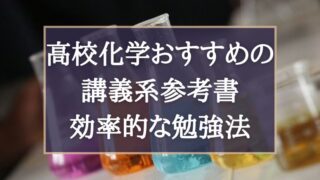
暗記すべきものを暗記する
化学は答えを理解してそれで終わりではありません。
暗記が足りなかったなと思うところもあるでしょうから、そこに関しては暗記にも時間を使いましょう。
特に有機や無機に関しては、暗記すべきことも多数ありますので、時間をかけるのも大事です。
1単元につき、暗記に使う時間としては、20~30分程度は取って、その時間内に覚えられることを覚えきってしまいましょう。
それ以上の時間を取らないことも重要ですが、それは後で説明します。
周回の手順
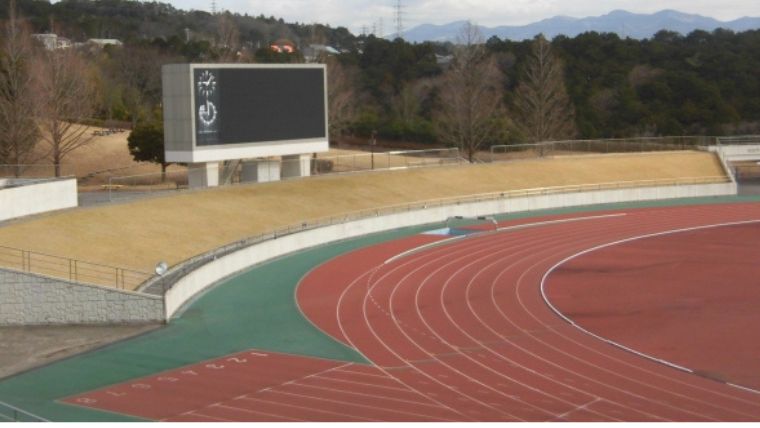
セミナーに限らず問題集は何周もすることで確実に実力がついていきます。
次のような手順で進めていくといいでしょう。
- 1周目:基本例題・問題
- 2周目:1周目で間違えた問題、発展例題・問題
- 3周目:2周目で間違えた問題、実践・総合・論述問題
- 4周目:3周目で間違えた問題
- 5周目:4周目で間違えた問題、以下同様
1周目は基本例題と基本問題だけを進めていきます。
問題数を絞ることで少し楽に1周を終えることができます。
2周目は、1周目で間違えた問題と、発展例題・問題を。
2周目が1番重いと思いますが、1周目で間違えた問題を解くこと単元ごとの内容を思い出しながら発展問題を解けるはずです。
3周目は、2周目で間違えた問題と残った難しめの問題を。
以降は間違えた問題のみに絞って進めるだけでOKです。
セミナー化学で勉強するときの注意点

問題集を解くときに注意することも並べておきます。それが以下の3点です。
- 暗記に使う時間が長くなりすぎないように
- 1周程度で出来るようになるとは思わないこと
- ペースを意識すること
順に解説していきます。
暗記に使う時間が長くなりすぎないように
まずは暗記に使う時間を長くとりすぎないことです。
特に浪人生とかにその傾向が強いのですが、完璧を目指して暗記を行ったところで、実際のテストや模試、入試の得点はさほど上がりません。
また「暗記をしてやるぞ」という気持ちで暗記するよりも、問題を解く回数を増やす方が効率的です。
もちろん暗記も重要なのですが、暗記に時間を割きすぎると、大して出題されない所にも時間を使いすぎてしまう傾向が強くなってしまいます。
イメージとしては、暗記:問題演習=1:4以上、といった所でしょう。
1周程度で出来るようになるとは思わないこと
問題集を1周した程度では基本的にテスト、模試、入試の得点は上がりません。
1周終わった段階でかなり達成感はありますし、それだけでも時間がかなりかかるので、賢くなった気分にはなります。
ですが、その気分のままテストに挑むと、
とモチベーションが下がってしまうことがあるので、そこだけ注意しておきましょう。
何周も進めていくうちに、ビックリするほどいろんな問題が解けるようになるので、そこまでは勉強し続けてください。
ペースを意識すること
今回紹介している、セミナー、リードα、センサー、エクセルなどは問題数が何100問、あるいは1000問を超えることもあるはずなので、1周するだけでもかなり時間がかかります。
こういったぶ厚い問題集を扱っているときは、1時間くらいで何問進んでいて、その結果として、何か月で何周できるのか、といった計算をするのが大事です。
受験を意識した理想のスケジュール

具体的にセミナーを進める理想のスケジュールについても見ておきましょう。
こちらは化学全体のスケジュールです。

この表の傍用問題集と書かれているところがセミナーやリードαに対応するところです。
できれば高3の夏前には終わりたいのですが、現実的には夏休み中に必死に進める人も多い印象です。
それではやはり遅れているので、この記事を読んだ時点ですでに遅れている場合は、「寝る時間以外は全て勉強」くらいで遅れを取り返していきましょう。
こちらも参考に!
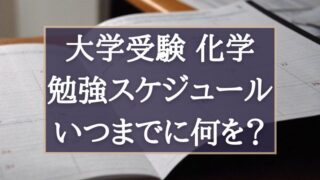
セミナー化学でどのレベルの大学まで到達できるか
セミナー化学は問題数が多い分、1冊こなすだけでも十分多くの大学に対応できます。
基本例題・問題のレベルが完璧に解けるようになれば、共通テストレベルの問題は安定して解けるようになります。
発展例題や発展問題も含めて全ての問題を自力で解けるようになれば、MARCHや関関同立、地方国公立大のレベルは十分解けるでしょう。
早慶や旧帝大などの問題はセミナーより厄介なので、重要問題集などのさらにレベルの高い問題集で演習をしてから過去問演習に入りたいですね。
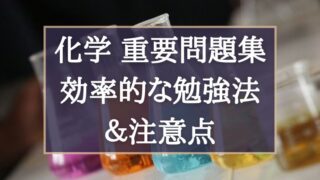
まとめ
今回はセミナー、リードα、センサー、エクセルなどの学校採用系の問題集の効率的な勉強法について解説しました。
次のような勉強法で進めてください。
- 進めるべき単元を授業や参考書で習う
- 時間を計って解く(基本は1問5分、発展は1問5~10分)
- 解説を丁寧に読む
- 資料集に目を通す
- 間違えた問題、理解できなかった問題に印をつける
- 暗記すべきものを暗記する
また周回の手順は次の通りです。
- 1周目:基本例題・問題
- 2周目:1周目で間違えた問題、発展例題・問題
- 3周目:2周目で間違えた問題、実践・総合・論述問題
- 4周目:3周目で間違えた問題
- 5周目:4周目で間違えた問題、以下同様
徐々にレベルを上げつつ、間違えた問題をくり返し解くことで実力を伸ばしていけます。
かなり大変なのは間違いないですが、MARCHや関関同立レベルであれば、こういった問題集を1冊解けるようにしておくと、あとは過去問だけで十分な大学も多いので、ぜひそのつもりで何周もチャレンジしてみてください!
それではまた、所長でした!