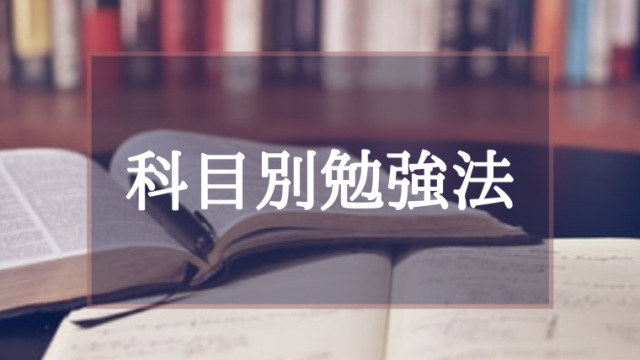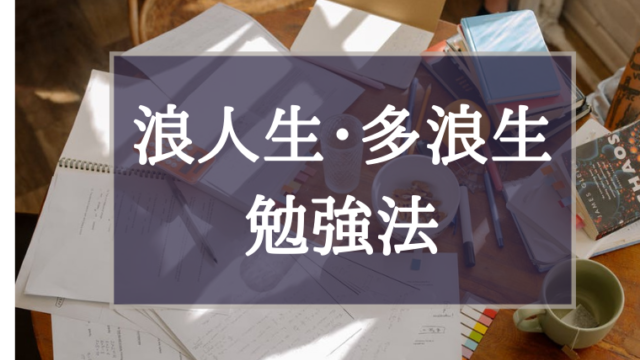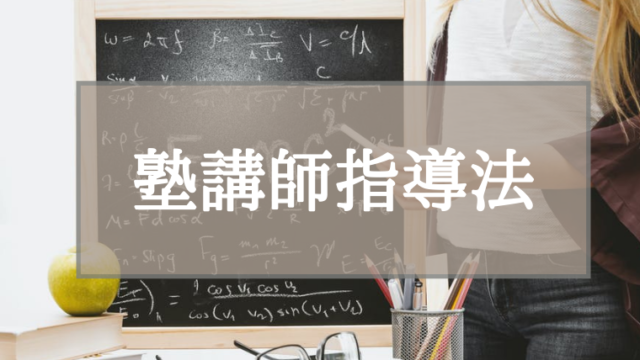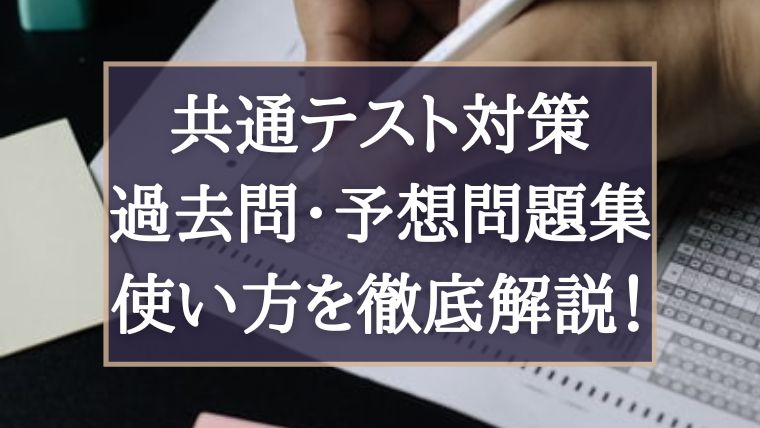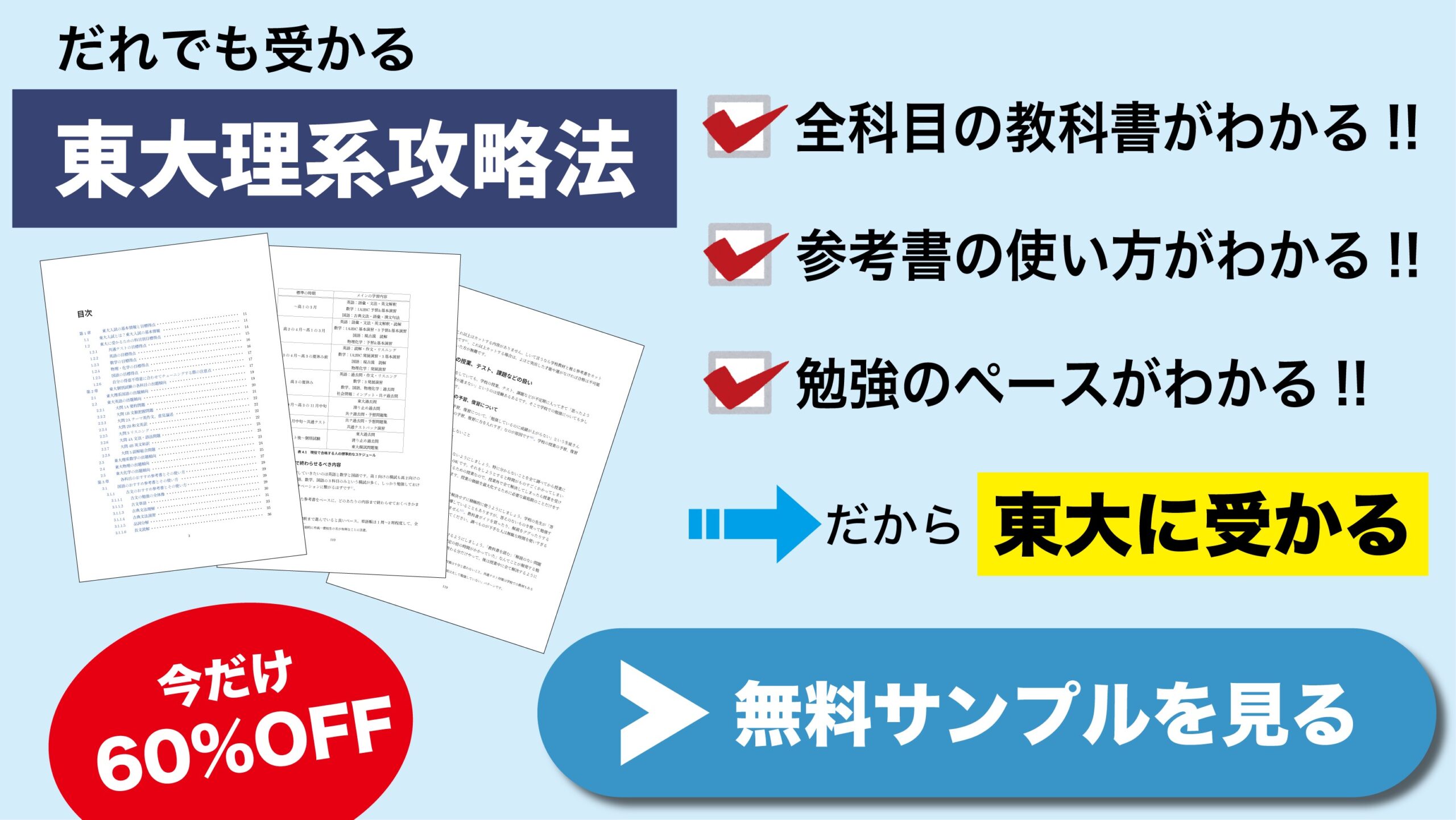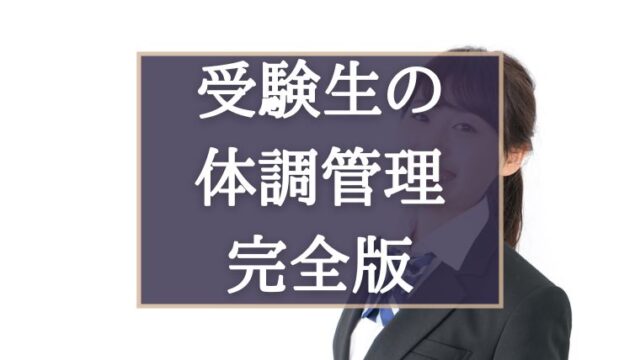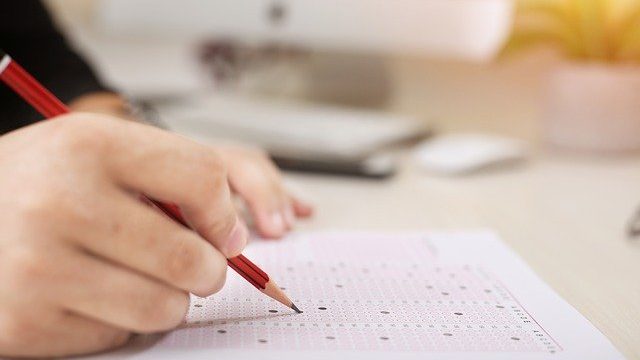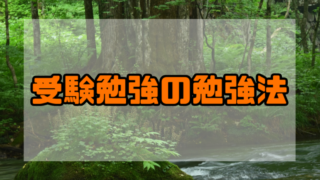ども、所長です!
「共通テストの過去問買ってみたけど、使い方で注意すべきことってある?」
「予想問題集をやってるけど、伸びないのは使い方が間違ってるから?」
こんなお悩みをお持ちではないでしょうか?
こちらの記事では、共通テストの過去問や予想問題集の効果的な使い方を1から10まで手取り足取り全て解説します!
この記事を読むメリットは以下の通りです。
- 共通テスト過去問・予想問題の解き方と、復習の仕方が全て理解できる
ぜひ最後までご覧ください。
目次
過去問の解き方は?本番を想定して解くこと!
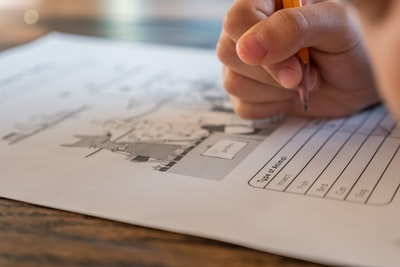
解き方は現役生だろうが浪人生だろうが基本的には同じです。
- マークシート、鉛筆、時計を準備する
- 試験時間を計りながら解く
- 問題用紙と解答用紙どちらにも記入しながら解く
- 時間配分を最初に考えてから解く
- 時間切れになって、解けていない部分があったらペンの色を変えて追加の時間で解く(受験までに余裕がある場合)
以下で詳しく説明します。
マークシート、鉛筆、時計を準備する
共通テスト演習は徹底的に本番を想定した解き方をするのが重要です。
マークシートと鉛筆は必ず準備しましょう。
マークシートは過去問の場合はダウンロードできますし、予想問題集を使う場合には付属されているはずです。
また鉛筆でマークするのが一般的なので、鉛筆でマークすることに慣れておきましょう。
※本番はシャーペンと鉛筆を持ち替えながら解く人もいれば、鉛筆のみでやり切る人もいます。これはお好みに合わせてどうぞ。
時計についても本番に机に置くものを利用するのがいいでしょう。
スマホは本番は使えません。
試験時間を計りながら解く
最も大事なことは「時間を計って解く」ことです。
これを外しては何の意味もありませんから、確実に押さえなければなりません。
特に共通テストの英語・国語・数学は他の入試問題と比べてもかなり制限時間厳しめのテストなので、時間内に解き終わるようになるだけでもかなり苦労することはよくあります。
徹底的に時間の感覚を身につけてください。
もちろん大問1問ごとに休憩を入れるなどはNG。
細切れにせず本番と同じ時間だけ「通し」で解くのも当たり前と思っておきましょう。
問題用紙と解答用紙どちらにも記入しながら解く
共通テスト本番はマークシートに記入するのはもちろん、問題用紙の方にも自分の選んだものをメモしておく必要があります。
大学の出願の際には、共通テストの本当の得点は知ることができず(受験が終わってから開示される)、自己採点の得点を信じて出願する必要があります。
自己採点を正確に行うためには、持ち帰り可能な問題用紙にも自分の選んだ番号を全てメモしておかなければなりません。
問題用紙と解答用紙どちらにもマークすると、それだけでも数分の時間はかかりますし、慣れておかないと両者に違うマークを残してしまい自己採点と実際の得点がずれてしまうことも。
演習の段階でしっかり練習しておいてください。
時間配分を最初に考えてから解く
共通テストはまだ実施されて数年しか経っていないので、問題傾向が変わる可能性があります。
つまり本番はまず最初に問題をザっと見て、「時間配分が練習の通りで大丈夫か、それとも少し修正しておくべきか」を最初に判断する必要があります。
必ず試験時間の最初に問題を最初から最後までザっと見て、時間配分を考える癖をつけておいてください。
時間切れになって解けていない問題があったらペンの色を変えて解く(受験までに時間がある場合)
受験までに余裕がある場合には、時間不足分がどれだけなのか確認するためにペンの色を変えて限界まで解き進めてみると良いでしょう。
ペンの色を変えて解ける部分が大きく増えるなら、その分、速く解くことを意識しなければなりません。
時間制限を外して解ける設問が30%増えるなら、解くスピードを1.3倍にしなければなりません。
具体的にどれくらいスピードアップしなければならないかを意識して、練習できると効果的に過去問演習の時間を使えます。
時間を増やしても解ける場所が増えないなら単純に実力不足ということも理解できます。
ちなみに、受験まで時間がない場合には、制限時間内に解いた分だけで納得して、復習に時間を使いましょう。
その方が効率的に時間を使えます。
後述する目標の過去問演習量を目安に時間に余裕があるかどうかを判断してください。
共通テスト過去問・予想問題っていつからやるべきなの?

次にいつからやるべきなのかについて解説しましょう!
共通テスト対策は遅くとも11月末くらいからは始めたい所。
センター試験のときは1か月頑張れば十分な人も多かったですが、やはりそれよりも難易度が上がってきているので、余裕を持って11月末くらいからは始めたいですね。
他の過去問も合わせていつ頃から始めるべきかはこちらの記事に詳しく書いているので、参考にしてください!
共通テスト過去問・予想問題って何年分やるべきなの?現役生・浪人生に分けて解説!
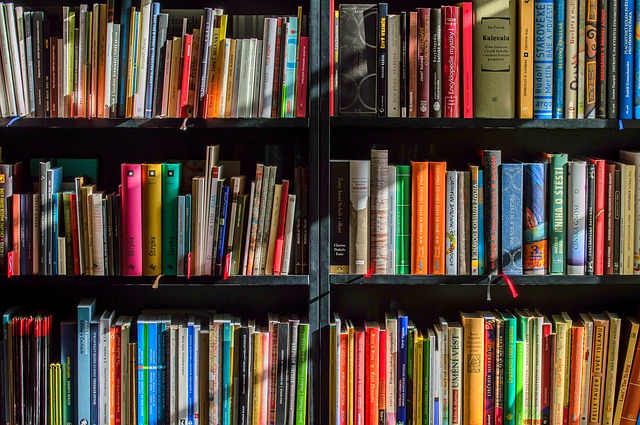
現役生と浪人生で使える時間が違うので、場合分けして解説します。
現役生の場合は?
現役生は順調に勉強が進んでいれば、10回分くらいは共通テスト系の演習をすることができるでしょう。
※学校での演習を除いて自力で10回分くらいはやりたい所。
それくらいの回数分、満点を取れる状態を作っておけば本番でも8割以上は固いはずです。
もちろんそんなにする余裕がない人も多いと思いますが、その場合でも学校の演習を除いて5回は確実にこなしておきたいですね。
浪人生の場合は?志望校は20年分・滑り止めは5年分!
浪人生の場合は滑り止めも準備する必要がありますが、使える時間も多いのでかなりの年度数の過去問・共通テスト演習をすることができます。
共通テスト系の演習も最低ラインが15回、可能ならばもっとやってもいいですね。
ただし、9割以上が5回連続で続くような場合は、あまり共通テスト演習から学ぶことがないので、そのレベルまで行ったら他の科目に集中したり2次の対策に時間を割いたりするのがおすすめです。
共通テスト過去問・予想問題集の復習の仕方は?

続いて復習の仕方を説明します。
手順は以下の通りです。
- 丸つけをする&解説を全て読み込む
- 解説を閉じて解答を再現できることを確認する
- 暗記すべき部分を暗記する
丸つけをする&解説を全て読み込む
解いたら解きっぱなし、丸つけして点数を出して終わり、となっていませんか?
過去問を解く目的は「問題に慣れること」もありますが、「解けない問題を解けるようになること」にもあります。
解けなかった問題を解けるようにしない限りは永遠に点数は上がりません。
解説は解けていた問題も含めて全てしっかり読み込みましょう。たまたま正解しているだけの問題も取りこぼしてはいけません。
共通テストの過去問や予想問題集に関しては、解説がかなり充実しているので、しっかり読めば(&実力が足りていれば)、それだけで全ての問題を理解できます。
それだけでなく、周辺事項まで合わせてまとめてくれているので、「欄外」とか「まとめ」とかになっている所も含めて隅から隅まで読むようにしましょう。
解説を閉じて解答を再現できることを確認する
計算系の問題は、解説を読んで納得して終わりではありません。
必ず解説を閉じた状態で解答を再現してみましょう。
再現できなければ、理解が不十分だったということです。
この練習を繰り返せば、凡ミスが減りますし、記述力も伸びていきます。
計算ミスをする人の多くは、解答を見て納得して終わりにしていますが、解答を閉じて、同じ答えが自分の計算から導かれなくては何の意味もありません。
計算はサボらないようにしましょう。
暗記すべきところを暗記する
暗記はどの科目にも必要です。
単語や文法を覚えるのは当たり前ですが、一見すると暗記が重要ではなさそうな所が最も暗記が必要な部分だったりします。
その点を詳しく解説します。
文系科目
文系科目の場合は、単語や文法などを覚えるのは国語でも英語でも当たり前ですし、社会についても一問一答形式で覚えるべきものはほとんどの人が意識的に覚えています。
英語や国語の長文に関しては背景知識を意識的にインプットしましょう。
新しく参考書を準備する必要はありませんが、過去問に出た話は、復習以降あなたの常識として話せるようにしておきましょう。
桃太郎の話くらいには、何も見ずに説明できるようになっておいてください
というのが私がよく使う説明です。
ちなみに、注釈に書いてある内容も頭に入れるようにしておくと、1回の過去問から得るものが増えて実力アップの効率が上がります。
理系科目
理系科目に関しては、生物や化学で暗記すべきものを認識して覚えるのは普通のこと。
それだけでなく数学や物理、化学に関しては「解き方」を暗記しましょう。
この問題はこう解く
というパターンを暗記すれば解ける問題がほとんどです。
あなたが応用問題だと思っている問題も、あなたよりももっと勉強している人から見れば、ただの典型問題です。
典型問題は覚えるもの。
とにかく全ての問題の解答の流れは暗記するようにしましょう。
ただし復習に使う時間にも注意!
復習は徹底的にやり込む必要がありますが、とはいえ、無限に時間を使えるわけではありません。
復習に使う時間は「試験時間の2倍」を目安にしましょう。
共通テストの演習なら80分が試験時間なので、復習パートは80分の倍の160分を目安にする形ですね。
最初のうちはそれでは全然最後まで復習が終わらないかもしれませんが、その時間内に音読まで終わる大問だけを集中的に扱っていきましょう。
逆に言えば、倍の時間くらいはかけるべきとも言えます。(9割以上取れるような人なら、もっと短時間で全て復習を終えられるはずですが、、、)
時間がないからといって、手を抜くのだけはやめましょう。
まとめ
共通テスト過去問・予想問題集の使い方に関しては全てまとめましたが、より細かい科目ごとの勉強法は以下の記事に書いていますので、興味があれば、苦手科目だけでも見てみることをおすすめします。
それではまた、所長でした!