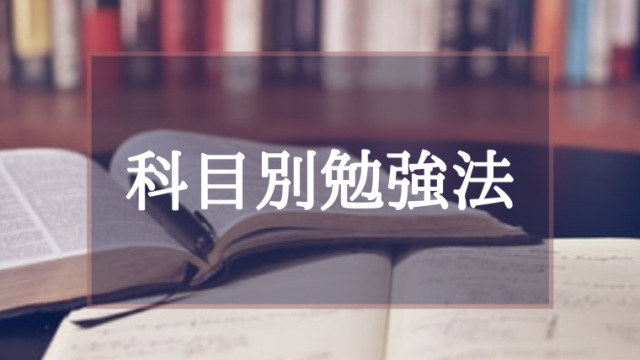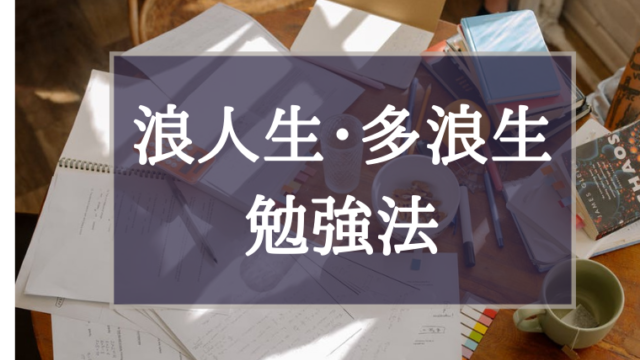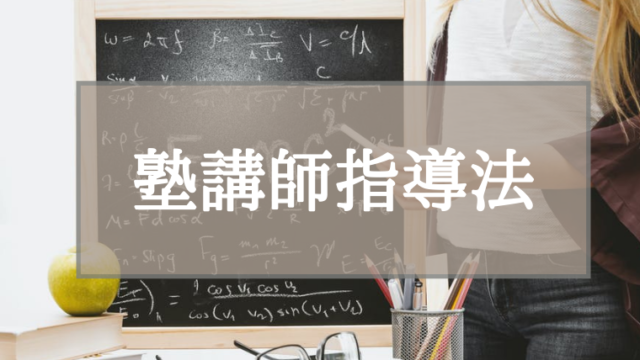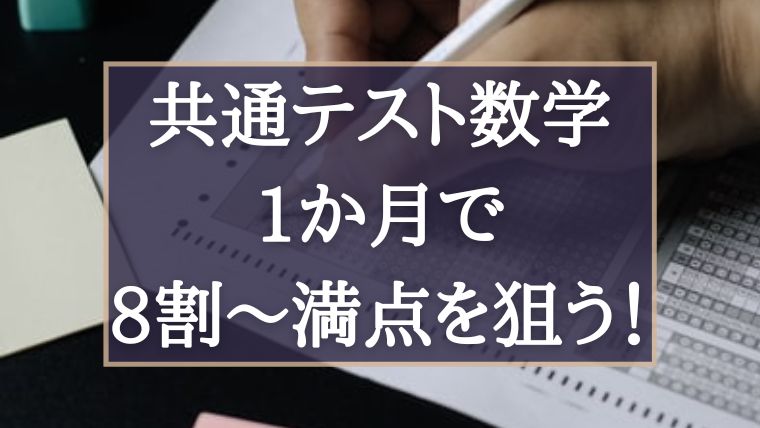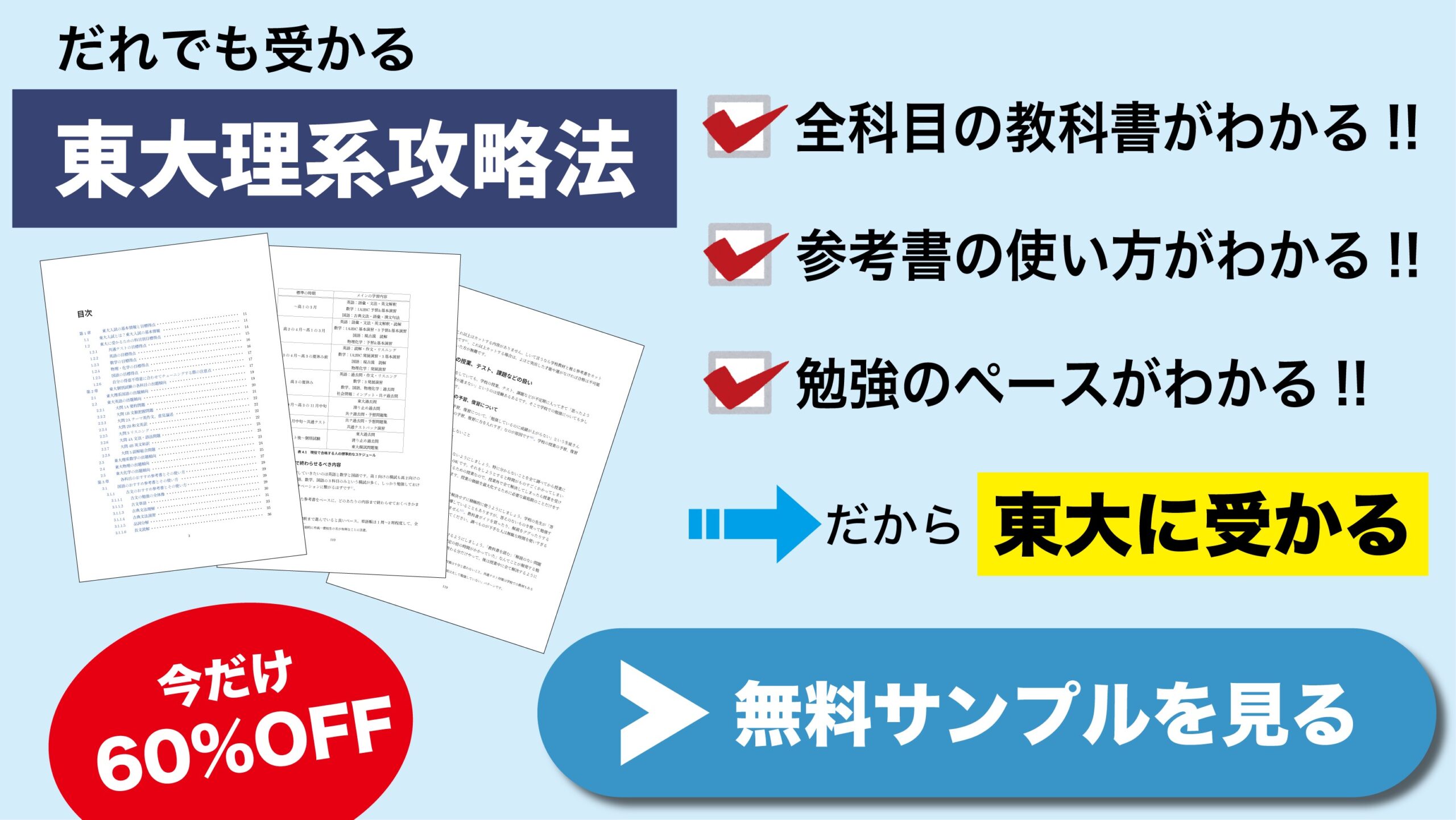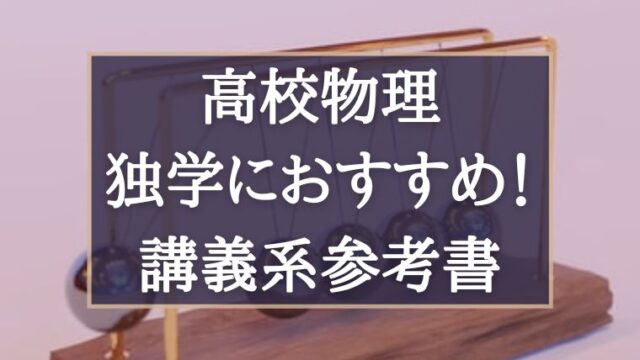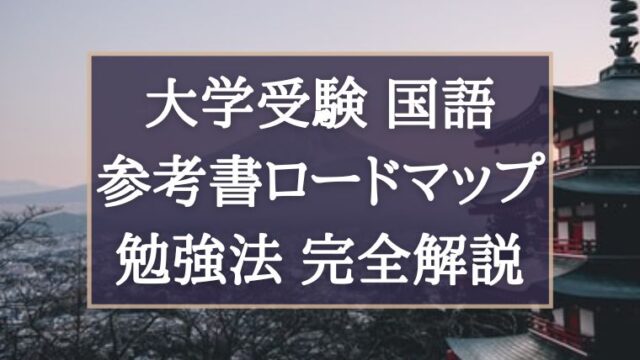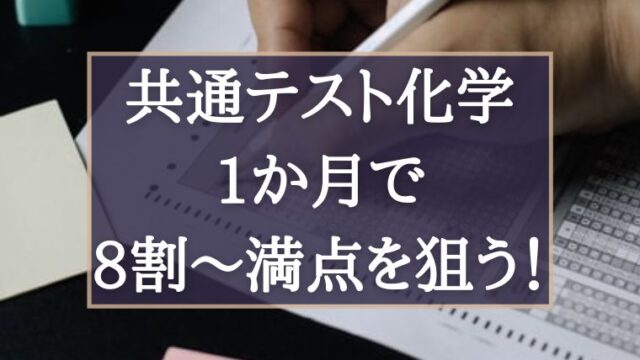ども、ぽこラボ所長です!
今回は共通テスト数学の対策について。
「共通テスト数学でどうしても8割以上狙いたいんだけど、あとちょっと足りない」
「取れるときは結構いくけど、全然安定しない」
と思ったことはありませんか?
この記事ではそんな悩みを全て解決すべく、徹底的に共通テスト数学対策を解説していきます。
どんな参考書を使ってどんな風に勉強すれば、8割以上~満点まで狙えるのか全てわかるように説明したので、1か月本気で取り組めばかなり伸ばすことができます!
ぜひ参考にしてください!
目次
共通テスト数学対策の全貌
共通テストの数学で8割~満点を狙う場合の、勉強の流れを把握しておきましょう。
具体的には次の通りになります。
- 現状のチェック
- 基本知識のインプット
- 基本知識を問題演習で定着
- 過去問or予想問題で徹底対策
現状をチェックし、必要に応じて基本知識をインプットしたり、演習を通してその知識を定着させたりしていきます。
そして最終的に過去問や予想問題集を使って、徹底的に問題形式を意識した対策をすることで得点を大きく伸ばすことが可能です。
まずは現状のチェック|知識が足りない?or時間が足りない?
共通テストの予想問題などを利用して、現状のチェックをしてみましょう。
※予想問題集については、この記事の後半で詳しく紹介します。
手順としては次の通り。
- (大問構成や配点を把握する)
- 問題用紙と解答用紙を準備する
- 試験時間通りに解く
- まだ解けそうな部分があればペンの色を変えて時間を延長して解く
- 採点&分析する
それぞれ補足していきます!
大問構成や配点を把握する
まずは大問構成や配点を把握するところからです。
というのも、実際本番はどちらも把握している状態で受験するので、学力以外の部分をできるだけ本番と合わせて実力を計るためですね。
共通テスト数学の大問の構成と配点は次の通りです。
共通テスト数学1A↓
| 大問 | 出題範囲 | 配点 | 必答 or 選択 |
| 大問1 | 数学1から | 30点 | 必答 |
| 大問2 | 数学1から | 30点 | 必答 |
| 大問3 | 数学Aから | 20点 | 選択 |
| 大問4 | 数学Aから | 20点 | 選択 |
| 大問5 | 数学Aから | 20点 | 選択 |
共通テスト数学2B↓
| 大問 | 出題範囲 | 配点 | 必答 or 選択 |
| 大問1 | 数学2から | 30点 | 必答 |
| 大問2 | 数学2から | 30点 | 必答 |
| 大問3 | 数学Bから | 20点 | 選択 |
| 大問4 | 数学Bから | 20点 | 選択 |
| 大問5 | 数学Bから | 20点 | 選択 |
1Aも2Bも大問1と2は必答問題で、それぞれ数学1と数学2からの出題になります。
数学1の範囲には「集合・命題」「2次方程式・2次関数」「三角関数」「データの分析」などがあります。
数学2の範囲には「整式・恒等式」「剰余定理」「円の方程式」「三角・指数・対数関数、方程式」「微分積分」などがあります。
大問3~5は数学Aから、あるいは数学Bからの出題になっていて、大問3つ中2つを選んで解答する形式です。
数学Aの範囲には「場合の数、確率」「整数」「図形」があり、数学Bの範囲には「ベクトル」「数列、漸化式」「確率分布と統計」があります。
この表を参考に過去問を眺めるだけ眺めてみて、全体の構成を頭に入れましょう。
まだ数回しか行われていないので、今後全体の構成や配点が少しずつ変更される可能性が高いです。
また2025年1月の現役生からは指導要領が変わっているので、数学に限らず各科目ともに修正が入ってくることは把握しておきましょう。
問題用紙と解答用紙を準備する
本番に合わせるためには問題用紙と解答用紙を準備します。
共通テストの過去問を利用する場合であれば、東進の過去問データベースで無料ダウンロードできるので、そちらを利用しましょう。
予想問題の場合は、そのまま利用する形でもかまいません。
ただし、解答用紙はいずれの場合でも準備して使うようにします。
というのも、試験時間にはマークシートにマークする時間も必要だからですね。
また解答用紙にマークするだけでなく、問題用紙の方にも自分の選んだものをマークしておく必要があります。
※共通テスト本番では、問題用紙にメモしたものから自己採点をして、その採点を信じて出願する形になっています。
解答用紙は画像検索したら出てくるので、適当にどこかからダウンロードして来れば大丈夫です。
試験時間通りに解く
問題用紙と解答用紙が準備できたら、試験時間通りに解いていきます。
できなさすぎて時間が余る場合を除いて、途中でやめずに時間いっぱいまで解いたり、見直しをしたりしてください。
まだ解けそうな部分があればペンの色を変えて時間を延長して解く
数学でそこそこ高得点を狙える人は、時間が足りずに最後まで解けないということもよく起こるので、その場合はペンの色を変えて一旦満足できるまで解いてみましょう。
このときにもやはり時間は測っておくといいですね。
色違いで解いた部分に何分かかったのか把握できれば、どれくらいスピードアップすればいいのかハッキリします。
採点&分析する
解き終えたら、採点をして分析をしていきます。
採点は時間内に解けた部分と時間外に解けた部分を別枠でおこなってください。
分析については以下の3つのパターンに分けて解説しますね。
- 時間無制限で6割に満たない場合
- 時間無制限で6割〜8割の場合
- 時間無制限で80点以上の場合
時間無制限で6割に満たない場合
時間無制限でも6割に満たない場合は知識不足or問題演習不足のどちらかです。
「見たことない問題だな」と思ったり、「見たことあるけど、どうやるんだっけ?」と思ったりしているのではないでしょうか。
こういう風に思っているうちは8割以上の得点には程遠いので基本から勉強し直しましょう。
単元ごとにつぶしていくのがおすすめです。
見たことない問題が多い単元は、映像授業や講義系参考書を使ってインプットから。
見たことあるけど、どうやって解くんだっけ?という問題が多い単元は網羅系参考書や共通テスト対策系の問題集を使いましょう。
それぞれおすすめの教材はこの後紹介します。
そして、2単元つぶすごとくらいに過去問や予想問題を解いて、成長度合いを見つつ、次の苦手単元に移って、というのをくり返していってください。
安定して6割を超えられるようになってきたら過去問や予想問題の演習メインの勉強に移って大丈夫です。
時間無制限で6割~8割の場合
6割〜8割くらい取れる人であれば、基本知識はある程度インプットできていて、問題演習が足りない単元が部分的にあるパターンが多いでしょう。
単元別に弱い部分の補強をしていきましょう。
網羅系参考書や共通テスト対策系の問題集を使い、単元別に苦手分野をつぶしていき、1つつぶす度に過去問や予想問題を解き、新たに見つけた苦手単元をつぶし、という風にくり返していくのがおすすめです。
最初からこのレベルの場合は、時間無制限で8割超えるところまで持っていくのは難しくないので、そこまでいったらあとは時間内に少しでも高得点を取るのを目標に、過去問や予想問題の演習メインの学習に進んでください。
時間無制限で8割以上の場合
最初から8割以上取れる人は、時間内に、正確に解くのが最も重要になります。
過去問や予想問題を解いて、できなかった部分を完璧にして次に進むといった学習をガンガン進めるといいですね。
基本知識のインプットの勉強法とおすすめ参考書
基本知識のインプットは映像授業や、講義系参考書と言われるものを使うのがおすすめです。
映像授業で1番おすすめなのはスタディサプリです。
映像授業の勉強の手順は次の通りです。
- テキストを準備する
- 視聴する(ノートは最低限)
- 例題を自力で解く
- 確認問題を解く
- 問題集で同じ単元を学習する
こちらにより詳しく書いてあるので参考にしてください!
一方で、映像授業はイマイチ合わないという方は講義系参考書と言われる参考書を使って勉強することも可能です。
例えば、
などを使うといいでしょう。
勉強の手順は次の通りです。
- 時間を計りながら頭から飛ばさず読む
- 解説を隠して例題を自力で解く
- 確認問題を解いて解説を読む
- 問題集の該当単元を解く
こちらの記事でより詳しく解説しているので、参考にしてください。
基本知識を問題演習で定着させるための勉強法とおすすめ参考書
問題演習は網羅系参考書と言われる分厚い参考書を使うか、共通テスト向けの問題集を使うのがいいでしょう。
網羅系参考書だと青チャートが有名ですね。
具体的には次の手順で進めるといいでしょう。
- 時間を計りながら問題を解く
- 解説を丁寧に全て読む
- 間違えた問題は解説を閉じて解き直す
- 印をつけて2周目に備える
より詳しい解説はこちらの記事をご覧ください!
また共通テスト向けの教材としては、以下のようなものがあります。
使い方は基本的に上述した網羅系参考書と同様です。
過去問or予想問題の勉強法とおすすめ参考書
共通テストはまだ数回しか実施されていないので、過去問だけでなく、予想問題集も活用したい所です。
どちらを使ってもそれほど差はありません。
予想問題集には次のようなものがあります。
こちらも必要な回数分だけ買って練習するといいでしょう。
どちらの場合も勉強法は次の通りです。
- 問題用紙を印刷する(解答用紙もある場合は準備)
- 時間を測って解く
- できなさすぎて時間が余ったら見直しを完璧にして切り上げる
- 時間を計りながら解説を全て読む
- 間違えた問題を解説を閉じて解きなおす
- 各問題に印をつけて2周目以降に備える
- (添削が必要なものは添削をお願いする)
- 類題を解いて弱点補強する
こちらの記事でより詳しいことを書いているので、参考にしてください!
過去問 or 予想問題を何回分練習をすればいい?
続いて何回分、過去問や予想問題で演習をすればいいかについてです。
現役生の場合は学校で共通テスト対策をしたり、模試で演習をすることもあるはずですが、それに加えて自習として5〜10年分は最低でもこなしておきたいところ。
5年分程度では全然点数の良い時と悪い時の差が激しいままな人も多いのですが、模試なども合わせて15回くらいできているとだいぶ安定する人も多くなってきます。
とはいえ、全部で15回分も勉強する余裕がない人が多いので、あとは時間と相談して自分で決めていく形になりますね。
浪人生の場合は、各科目20回分ずつくらいは余裕で演習できるはずです。
1つの目安にしてください。
いつから対策をする?11月?12月?1月?
現役生の場合は学校が冬休みに入ったらフリーでできるようになるので、3日で1回分くらいは復習まで含めて演習できますが、それでも1ヶ月かけて10回分程度が限界です。
それに加えて弱点補強もしようと思うのであれば、遅くとも11月末〜12月頭くらいからは共通テスト対策に取り組みたいですね。
現状チェックの段階で4割くらいしか取れないようであれば、もっと早くてもいいくらいです。
共通テスト数学特有のよくある質問&高得点を取るコツ
共通テストの数学に特有のよくある質問や、高得点を取るコツをまとめておきます。
- 速く解くためのコツは?
- どの大問を選択すべき?
速く解くためのコツは?
速く解くコツは正直ありません。
正攻法は「迷う時間をゼロにする」作戦ですね。
実際、計算が多少遅くても、全ての問題を迷うことなく解き進めることができれば十分時間内に解ききることが出来ます。
「時間があればもっと解けるのに」
という方は確実に頻繁に手が止まっているはずです。
まず迷うことなく、最後まで走り切れるようにしましょう。
速く解こうとすることももちろん大事ですが、それよりも解き方をパッと思い出せるくらいの「くり返し練習」が必要です。
どの大問を選択すべき?
大問の選択に関しては「好きにしてください」が正直な答えなんですけど、それでは突き放しすぎかなという感じなので、個人的には、、という感覚でいくつかお伝えしておきます。
まず数学IAに関しては、私だったら「場合の数・確率」と「整数」を選んで「図形」を捨てるかなと。
図形に関しては、補助線を見つけないと解けない問題がときどき出てきてそれが厄介なことが多いのと、自分の描いた図のせいで、思いもよらない勘違いが生じやすいからですね。
ただし「場合の数・確率」に関しては、計算ミスや場合分けミスをする人にとっては苦しいですし、整数に関しては、勉強不足だと手も足も出ない可能性は出てくるので、何度も過去問を解いて、得意なものにチャレンジするといいでしょう。
正直、頑張ってセンターや共通テストの過去問を15~20年分くらい満点を取れる状態にしておけば、選択問題も全て時間内に解くことができて、そのうち自信のあるものをマークすることも可能です。
数学2Bに関しては、ほとんどの方がベクトルと、数列を選んでいると思いますが、それでいいと思います。
現状、共通テスト以降の個別試験に関しては、その2つしか出ない(確率分布と統計は出題外になっていることが多い)ので、数列とベクトルを勉強しておくのが無難です。
確率分布と統計の方が簡単なことも多いのですが、参考書的にも学校の授業的にもあまり充実していないことも多いはずなので、独学が少ししにくいという側面もあります。
調べてもちゃんと勉強しない
ここまでに書いたことを実践すれば、実際に8割以上で安定させるくらいなら十分できるようになりますが、ほとんどの人は勉強法を調べても、参考書を買ってもちゃんと勉強しません。
塾講師として、受験生指導をしていると、ただただ勉強をしていないだけの人もいれば、共通テストを甘く見ている人も大勢見かけます。
絶対に甘く見ずに本気で取り組んでくださいね!
まとめ
今回は共通テスト数学の対策について、徹底的に解説しました!
実際にこの記事で紹介した方法で勉強すれば、確実に点数は伸びていきますので、焦らず着実に勉強を進めていってください。
それではまた、所長でした!