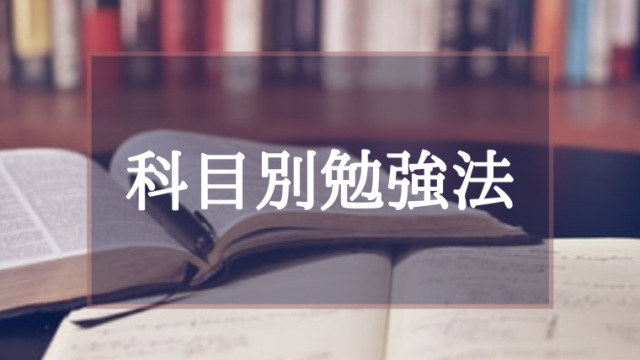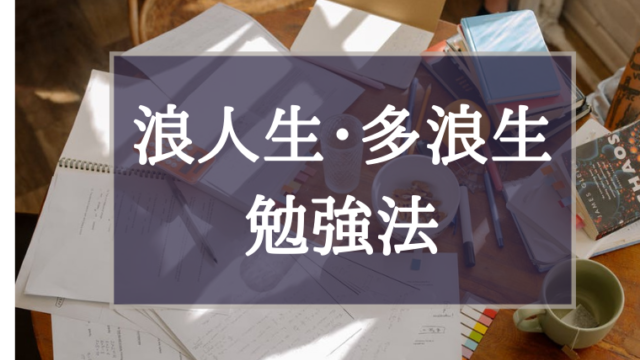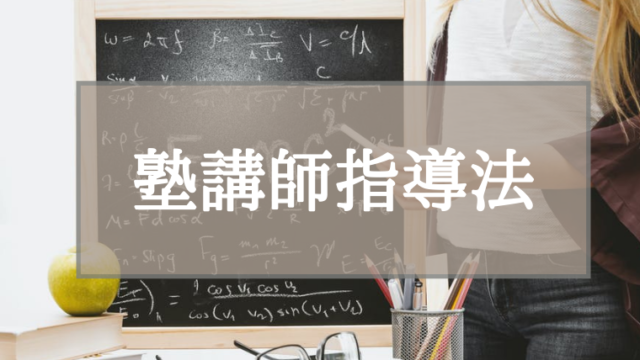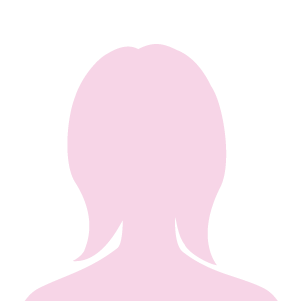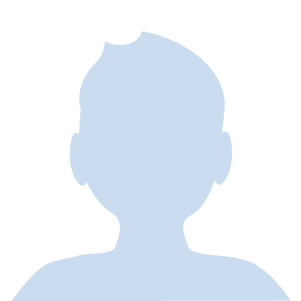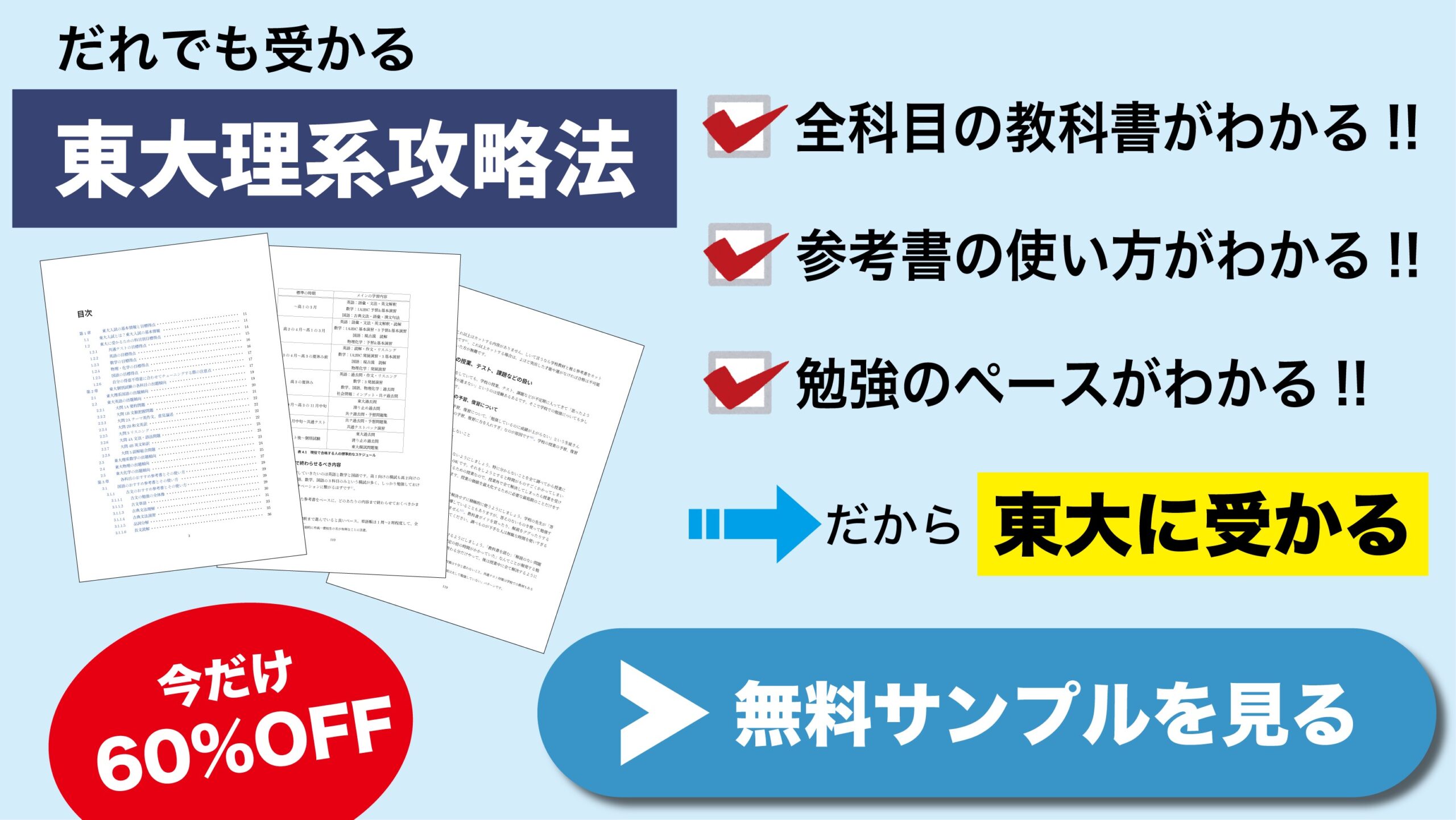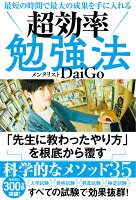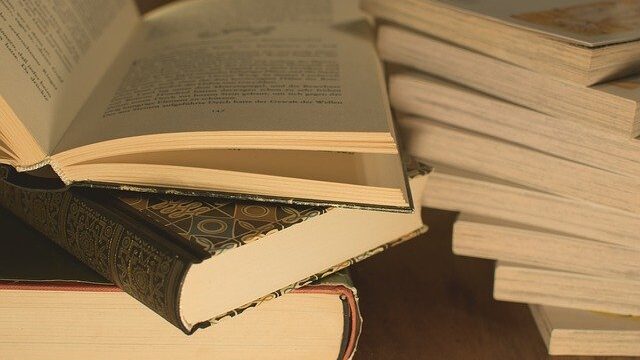社会人・フリーター・主婦が大学入試を独学合格は可能?【完全攻略ロードマップ2025】

ども、ぽこラボ所長です!
今回は社会人が「大学の一般入試」で受かるにはどうすればいいのか、超具体的な手順を紹介します。
こんな悩みをお持ちではありませんか?
最初に言っておきますが、社会人でも大学の一般入試に合格することは出来ます。
少なくとも、合格するまでに何をしなければならないかは、この記事を読めばハッキリわかります!
社会人が大学一般入試に受かるための超具体的な手順

まずはめちゃくちゃ具体的に、一般入試に受かるまでの手順を紹介します。
手順は以下の通りです。
- 試しに勉強する
- 入試情報の徹底的な調査する
- 作戦、計画を立てる
- 周りの理解を得る
- 勉強法の勉強をする
- 勉強する&改善する
ここで簡単に流れを説明してこの後、1つずつを詳細に解説していきますね。
まず大学に行きたいと思い立ったら、モチベーションは十分か、勉強を続けられそうかどうか、軽く自分自身の意気込みをテストしてみます。
2週間程度で良いので、簡単に勉強してみて、やる気が下がってこないならあなたのやる気は本物です。
やる気が本物と判断できたら、次は入試情報の徹底的な調査です。
- 何大学に受かりたいのか
- 何の科目を勉強すればいいのか
- 何点必要なのか
- どれくらい勉強しないといけないのか
- 受かったとしていくらくらいお金が必要なのか(塾などが必要ならその費用も)
諸々を含めて調査していきます。
入試情報をある程度まとめることが出来れば、今度は具体的に勉強内容を調べて計画を立てていきます。
最初から難しい問題をやっても手も足も出ませんし、いつまでも簡単なものを勉強しても合格はできません。
何をどの手順で勉強しなければならないのか、科目ごとに調べて、まとめて作戦を立てます。
作戦を立てるときには、自分が1日何時間だったら勉強できるのか、そういった時間の情報も合わせて確認して、受かるまでの全体像をここでつかむ必要があります。
場合によっては、周りの理解を得ないと、十分な勉強時間を確保できない可能性もあるでしょう。
親やパートナー、子どもの説得、上司への説明などが必要な場合もあるはずです。
社会人が独学で受かるのは、高校生や浪人生と比べて大変なのは間違いないので、手伝ってもらうことは悪いことではありません。
ですが、手伝ってもらうにも、計画も作戦も無しに手伝ってもらうのは難しいですよね。
最初から周りに話をするのは少し気が引ける方も多いと思いますが、その場合は、少し勉強をしてからでも大丈夫です。
と説明できれば、周りの理解も得やすいでしょう。
次は、勉強法の勉強です。
勉強法と言っても、単に「暗記するコツ」のようなものだけでなく、勉強のモチベーションを維持する方法なども一緒に学習しておくといいでしょう。
ここまで学べばあとは、本気で勉強するだけ。
「勉強するだけ」なんですけど、勉強を単に続けるよりは、反省や改善も同時に行っていく方が合格の可能性はグッと高まります。
- 勉強法は正しかったか?
- 勉強時間の確保の仕方で改善できるところはないか?
- 勉強内容はこのまま続けて大丈夫か?
など、反省と改善をくりかえしてもらえればと思います。
これが大まかな攻略方法の流れになります。
ここからは1つ1つのパートをかなり細かく解説していきますから、1回で読み切るのは少し大変かもしれません。
試しに勉強する

社会人受験最初の一歩は「試しに勉強すること」です。
と思ったとしても、そのやる気が本物でなければ、そもそも受験するところまでたどり着くことがめちゃくちゃ難しいのが社会人受験の特徴です。
あなたのモチベーションが十分か、自分をテストしてみましょう。
まずは毎日1時間の勉強を2週間続けてみてください。
この記事を読み終わってからで構いません。
途中まで読み進めれば、何から勉強を始めればいいかは分かるはずなので、
- 文系の方は「英語」「古文」をそれぞれ30分ずつ2週間
- 理系の方は「英語」「数学」をそれぞれ30分ずつ2週間
勉強してみましょう。
テストしてほしいのは
「5時間勉強を365日休まずに続けろ」を言い渡されても、「どうにかなりそう」と思えるかどうか
です。
もちろんたった1時間の勉強でも2週間続けるのは、簡単ではありません。
※運動習慣ゼロの人が毎日1時間のジョギングを2週間続けるのと同じくらいの難易度はあります。
途中途中で辛いなと思いながらでも
とポジティブに感じられれば、テストとしては十分です。
迷ったらまずは試す
高校生・浪人生の大学受験生も
といくらでも迷うことはあります。社会人受験生でもそれは同じでしょう。
覚えておいてほしいのは、
のが大事ということ。
この記事を読んでいる時点で「調べよう」という意志は十分です。
ですから、これからは「試しにやってみる」という感覚を養っていってください。
迷っている暇があったら、試しに勉強してみる。
ですが、試すことなく、迷うだけ迷って、全然前に進まないのは時間がもったいないのでやめましょう。
入試情報の徹底的な調査する

試しに2週間程度、勉強を続けてみて、それでも大学受験を続けるモチベーションが下がらなければ、次は「入試情報の徹底的な調査」です。
具体的には、
- 志望校&学部を調べつつ決める
- 必要なお金を調べてまとめる
- 入試のシステムについて調べてまとめる
- 必要な勉強時間を調べる
この4つを順につぶしていきましょう。
※ちなみに、ここはめちゃめちゃ大変なので、もし自分でやるのが辛かったら有料でもプロに相談するのがおすすめです。
私も大人のための大学受験相談サービスを始めたので、興味があればこちらをご覧ください。
志望校&学部を調べつつ決める
まずは志望校と学部を決めていきます。
志望校と学部を決めないと、入試の仕組みについても調べられませんし、勉強の作戦を立てていくことも出来ません。
ですが、早い段階で3つか4つくらいの大学に絞っておくのがおすすめです。
決めるときの要素は以下の3つがメインになるはずです。
- 興味や適性
- 難易度
- 学費などの資金面
それぞれ見ていきましょう。
興味や適性
まずは興味や適性から考えていきます。
この際に、大学に行かないと本当に学べないこと、得られないことなのか考えてみるのは重要です。
たとえば、英語の勉強だけなら大学に行かなくても、資格試験の勉強をすればいいだけ。塾に通えばいいだけです。
今ならビジネススクールだってありますし、動画編集のスクールだってありますし、他にもいろいろあります。
めちゃくちゃ大変な大学受験&大学生活を選ばなくてもいいのであれば、それに越したことはありません。
もちろん、
といった動機も全然OKですが、この場合は「何を学びたい」みたいなことはあまりない方も多いと思います。
例えば、「学部 適性」などのようにググって、出てきたサイトをいくつか見てみて、適性診断をしてみてください。以下は参考になるサイトです。
≫https://www.eibi-navi.com/tekisei/
≫https://manabi.benesse.ne.jp/op/g45_tekikensa/jk01/
ここで出てきた学部でどんなことを勉強するのか調べてみて、「まあ悪くないかな」と思えたら、その学部に決めてしまってOKです。
難易度
次に大学の難易度についてです。
「文学部 偏差値 ランキング」のように「学部名 偏差値 ランキング」でググると、偏差値順に並んだ表がいくらでも出てきますので、そちらを参考にするといいでしょう。
難易度に関しては、勉強をし始めた段階では
という人がほとんどだと思います。
興味・適性を満たしている学部があって、費用面もクリアしている大学のHPを偏差値の高いところから順に見ていくといいでしょう。
まだ勉強していないのに
などと考える必要は全くありません。
後から難易度の低い大学に目標を下げることはできても、逆に目標を上げられる人はまずいませんからね。
また一旦、学費などの費用面も忘れておいて、行きたい大学をいくつか絞ってみましょう。
学費に関しては、貯金を頑張ったり、奨学金を使ったりすれば、クリアできることが多いですし、
特に私立の場合は、1校1校必要なお金が変わってくるので、全部調べようとすると1週間やそこらでは時間が足りません。
志望校を絞ってから細かく調べていくのがおすすめです。
学費などの資金面
最後に、学費などの資金面について検討していきます。
調べておくべきなのは、次の3つあたりでしょう。
- 受験費用・塾費用
- 卒業までの授業料(いちおう留年の可能性も検討する)
- 1人暮らしなどするなら新生活の費用
特に授業料に関しては、国公立大と私立大で全然違います。詳しく調べておくのがおすすめです。
必要なお金を調べてまとめる

前の節でも解説しましたが、学費だけでなく必要になるお金を全て計算しておくのがおすすめです。
具体的にはこちらの記事に詳しく書いていますので、参考にしてみてください。
仕事を続けながら大学にも通うつもりであれば、4年で卒業するのは最初から諦めておいた方がいいでしょう。
(留年の覚悟だけはしておいて、4年で卒業できたらラッキーくらいの心持の方が無難です。)
また今住んでいる家から通えるのか、それとも引っ越しが必要なのかなどによっても費用面の計算は変わってきます。
進学した後、どういう風に過ごすかも含めて費用面は丁寧に見積もっておきましょう。
入試のシステムについて調べてまとめる
志望校と必要なお金について、まとめたら次は入試のシステムについて調べる必要があります。
入試の形式は大きく分けて、以下の10パターンあります。
- 国公立大学の一般入試
- 私立大学の一般入試
- 共通テスト利用入試
- 共通テスト併用入試
- 外部試験利用入試
- 指定校推薦
- 公募推薦
- 総合選抜型入試
- 社会人入試
- 帰国生入試
って思いますよね。塾講師でもめちゃくちゃ多いと思います。
ですが、このうち社会人が大学入試で利用する可能性が高いのは、以下の5種類だけです。
- 国公立大学の一般入試
- 私立大学の一般入試
- 共通テスト利用入試
- 共通テスト併用入試
- 社会人入試
余裕があれば、この5種類の入試形式の違いを意識して、どのスタイルで受験するのかを考えるのがおすすめです。
以下の記事を参考にこの5種類の入試形式の特徴をまずは把握しましょう。
そのうえで、志望校ごとに募集要項をチェックして、A大学はどの入試形式を使うか、B大学はどの入試形式を使うか、などと作戦を立てていく必要があります。
とはいえ、勉強がある程度進まないと、どの入試形式がどれくらい難しいのかなどの判断も難しいのは間違いないですから、最初はひとまず一般入試に受かるだけの学力を身につけるという方針でも構いません。
その場合でも、各志望校ごとに「どの科目が受験で必要になるか」は最初から把握しておきましょう。
必要な勉強時間を調べる
志望校を絞って、入試形式も把握出来たら、次は必要になる勉強時間を調べてみましょう。
スタート地点とゴール地点の差が大きい人ほど勉強時間が必要になりますし、
勉強慣れしているかどうか、好きかどうか、効率的に勉強を進められるかどうか、でも必要な勉強時間は全然違う値が出てきます。
ものすごく大雑把に言えば、大学受験までに必要な勉強時間は、
- 私立文系→4000時間
- 私立理系→6000時間
- 国公立文系→8000時間
- 国公立理系→9000時間
くらいになるでしょう。
以下の記事に詳しいことは書いています。
これに関しては、サイトによってはもっと短時間で合格可能と書いているところもあると思いますし、逆にもっと大変と言っているサイトもあると思います。
いくつか調べてみて、自分なりに納得できたものを信用すればいいでしょう。
作戦、計画を立てる

まだまだ勉強を本格的にスタートするまでには先が長いですが、頑張りましょう。
ここまでで、
- 志望校の決定(絞り込み)
- 費用面の調査
- 入試形式の基礎知識の調査
- 必要な勉強時間の調査
までが終わったので、次は作戦・計画を立てる段階です。
上述のように、高校生や浪人生と違って、勉強時間の確保が難しい社会人なので、作戦を丁寧に立てて効率的に勉強を進めないと、志望校に受かるのは非常に難しくなってしまいます。
作戦立ての具体的な手順は以下の通りです。
- スタート地点の把握
- 1週間の最大勉強時間の計算&必要勉強時間をクリアするのに何年かかるかの計算
- 合格最低点、各科目の配点、過去問のチェック
- どういう参考書ルートをたどるか調べる
- 年間計画、週間計画を作る
それでは1つずつ解説していきます。
ここで、この記事の3分の1くらいなので、まだまだ続きます。
時間がかかりそうならブックマークをして後で読むのもありです。
あと、
と思った人は有料ですけど、単発の受験相談をやってますので、こちらもご覧ください。
スタート地点の把握
作戦を立てようにも、勉強を始めた時点での学力が正確に把握できていなければ、自分のレベルに合った正しい教材を選ぶことはできません。
かと言って簡単すぎるのをやって無駄に時間を使いたくもないですよね。
そこで、スタート地点を把握するために以下の2つのテストを解いてみるのがおすすめです。
- 高校入試
- センター試験過去問
勉強からたった数年離れるだけでも、中学レベルの内容すら忘れているというのは割と普通のこと。
まずは高校入試がまともに解けるか確認してみましょう。
どこの高校入試でも構いませんが、例えば、お住まいの都道府県の公立高校の入試問題を解くのでOKです。
「90%も取ったことない!」っていう人もいったん解いてみてください。
まずは実力を把握することが大事。勉強すれば、90%くらいは誰でも取れるようになります。
志望校が私立大の場合は、「受験で使う科目だけ」で構わないので、90%超えられるか確認してみてください。
※例えば、私立文系なら英国社のみで十分です。
もし90%を超えられないなら、中学レベルの復習から勉強を始めるような計画を立てるのがおすすめです!
高校入試レベルであれば、問題なく解けるという方は、センター試験を解いてみてください。
2021年の入試からセンター試験ではなく、共通テストに変わって難易度が上がったので、センター試験を使うのがいいでしょう。
センター試験の2020年のものを受験に使う科目だけでいいので、全科目解いてみましょう。
この段階では全然解けなくても構いません。
スタート地点をしっかり把握したうえで、勉強を開始するための準備をしていると思って、手を動かしてください。
1週間の最大勉強時間の計算&必要勉強時間をクリアするのに何年かかるかの計算
スタート地点を把握したら、次は「勉強時間」について詳細に検討していきます。
まずは1週間の最大勉強時間を計算してみましょう。
「平日~時間、土日祝~時間だから1週間で最大~時間は勉強できる」
ということを計算するだけです。
ここで注意するのは
「出来るだけ細かく計算する」
ということ。
朝起きてから、夜寝るまでの行動パターンを全て書き出して計算を進めてください。
仕事の昼休みももちろん、食べながら勉強できますし、食後の休憩なども勉強可能時間です。
実際の所、全ての時間を勉強に充てるのはハードすぎますが、いったん最大値を計算しておくのが大事です!
そのうえで、「最大勉強可能時間を100%使いきれる」として、1年で何時間勉強可能か計算してみてください。
計算方法としては、「1週間の最大勉強可能時間を50倍するだけ」でOKです。
1週間で最大50時間くらい勉強できそうな人なら、1年間で2500時間勉強できます。
※1年は52週間ちょっとありますが、実際に勉強できるのは、そこから少し引き算した50週とみなしておいた方が無難です。
ここまで計算できたら、少し上で調べておいた「必要な勉強時間」の値を使って、合格するまでに何年必要か計算してみましょう。
具体例をここでは出しておきます。
- 平日4時間、土日8時間勉強可能→1週間で36時間
- 1年で36時間×50=1800時間勉強できる
- つまり「私立文系なら2年と少し」「国公立理系なら5年」
実際に計算してみてください!
ちなみにこの計算は最大勉強可能時間をフルで生かし切った場合の計算なので、この数字の1.2~1.5倍くらいの時間がかかる人は大勢いらっしゃいます。
と思ったのであれば、ここでやめるのも全然アリです。
実際、仕事をしながら勉強のモチベーションを保ち続けるのは、それほど簡単なものではありませんし、
3年もあれば、生活環境が変わって、勉強に使える時間も変わってしまう可能性も出てきてしまいます。
ですので、この時点で
と思った方は、大学受験などせずに、もっと有益なことに時間を使ってみることをおすすめします。
大学に行かなくても、ここで計算した分の時間を使えば、いろんなスキルを身につけることが可能なはずです。
逆に、
と思えた人は続きを読んでもらえればと思います。
この後の内容に、毎日の自習時間を伸ばすためのコツもまとめているので、確認してくださいね!
1週間の最大勉強可能時間を少しでも伸ばせれば、何年かかるか計算した結果も変わってきます。
そして、効率的に勉強を進められれば、もう少し短時間でも合格する人は大勢いるので、勉強法についても後半で解説していきますね。
合格最低点、各科目の配点、過去問をチェックする
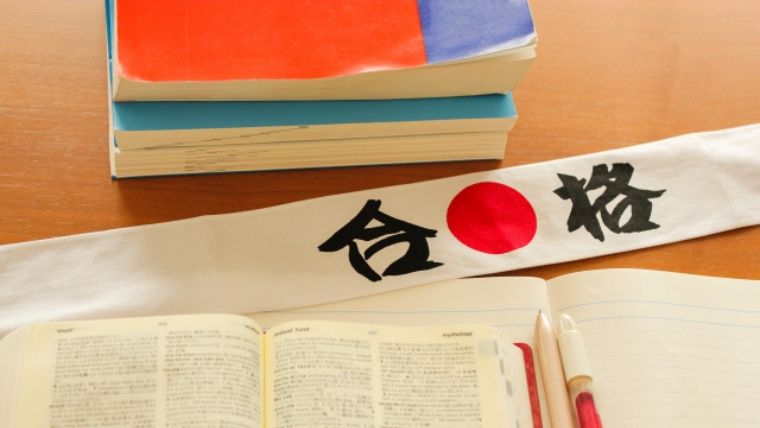
次はゴール地点の把握です。
大学受験ではゴール地点の把握も非常に重要です。
ちゃんとした場所が理解できていないと、勉強が違う方向に進んでしまったり、たどり着いたと思っていても、距離が足りていなかったり、
と失敗する要因に直結するのがゴール地点の把握の有無です。
具体的には
- 合格最低点
- 各科目の配点
- 過去問の出題傾向
をチェックしましょう。
合格最低点
合格最低点はパスナビというサイトを確認するのが見やすいでしょう。
最新の合格最低点などは、パスナビに反映されていないこともあるので、その場合は、大学のHPを確認するといいですね。
公立高校の高校受験の場合だと、レベルの高い高校は8割~9割得点しないと合格できないこともありますが、大学の場合は、そこまで高得点が必要な大学はほとんどありません。
過去3年分くらい確認してみて、1番合格最低点が高い年でも受かるように目標を立てておくのが大事です。
とはいえ、こういった大学でも8割以上の合格最低点になることは少ないので、ひとまず合格最低点が公表されていない大学は8割~8.5割あたりを目標点にしておくといいでしょう。
各科目の配点
つづいて、各科目ごとの配点も確認しましょう。
私立大学の一般入試であれば、個別試験の配点だけ確認すればOKです。
英語200、国語150、社会150
のような配点が、パスナビで確認できます。
こちらも、最新版は大学HPで確認することをおすすめします。
この例くらいの配点比なら割と普通ですが、大学によっては「英語:国語=2:1」でそれだけで決まるということもあって、
この場合は明らかに英語の勉強時間の比率を上げる必要がありますよね。
国公立大の場合は、科目ごとの配点だけでなく、共通テストと個別試験の配点の割合が違う場合もあります。
例えば、東大などは少し厄介で、共通テスト900点満点を110点に圧縮換算して、個別試験の440点と合わせた配点で合格最低点を考える必要があります。
また共通テストの得点が低かった人は「足切り」されて、個別試験に臨むことすらできない大学もあります。
東大もその例の1つです。
過去問の出題傾向
ここまでで合格最低点や科目ごとの配点を調べる方法を伝えました。
配点的には、数学がものすごく高くても、数学の問題が他の科目よりも圧倒的に難しいのであれば、勉強の方針を考える必要も出てきます。
なので、過去問の出題傾向についても初めからある程度把握しておいた方がいいでしょう。
ただし、「過去問の難易度」に関しては、かなり勉強をして実力がつかないと分からない部分が大きいので、もっと後になってからでもかまいません。
ここで把握しておきたいのは「出題形式」や「頻出分野」などがあるかどうか。
例えば、英語のリスニングが出題されない大学を目指しているのにリスニングを勉強するのは時間の無駄ですよね?
リスニングは受験が終わってからでも勉強できますからね。
このように、過去問の出題形式や頻出の分野を知っているかどうかで、効率的に勉強できるかどうかは変わってきます。
過去問を早めに確認しておくようにしましょう。
科目ごとに、どんな内容をチェックしておくべきかは以下の記事にまとめていますので、確認してみてください。
※ちなみに、中学レベルの勉強内容も怪しいという人は先に中学内容は勉強し終えてから、チェックする方が無難ですので、その点だけご注意を。
どういうルートで勉強するのか調べる
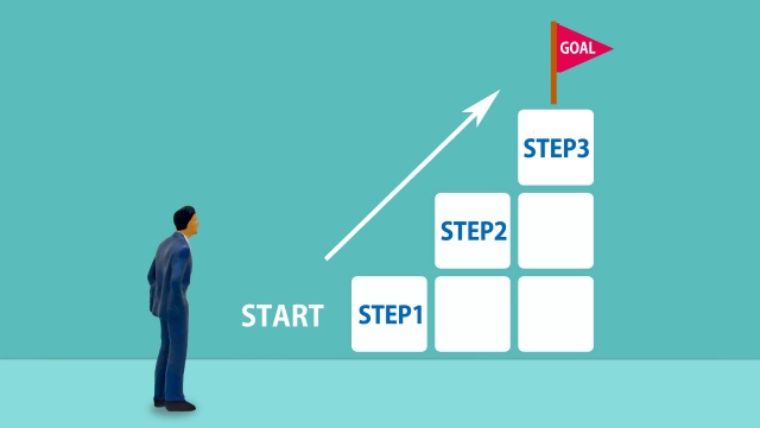
スタート地点、ゴール地点を把握し、各科目の配点や出題形式を何となく把握したら、次は各科目ごとにどういうルートで勉強するべきか調べる必要があります。
たとえば、英語であれば、以下のように勉強するのが王道ルートです。
- 単語、文法の勉強
- 英文解釈の勉強
- 長文読解の勉強
- リスニングや英作文の勉強
- 過去問演習
入試で長文ばかり出題されるからといって、最初から長文読解の勉強をしても、文法や単語が頭に入ってないと勉強が全く前に進みません。
効率的に前に進むためのルートは確実に存在しています。
各科目ごとにどういった教材をどういった順に勉強していけばいいのかは必ず調べてから勉強するようにしましょう。
ちょっと面倒ですけど、全科目とも勉強ルートを確認しておいてください。
以下に全科目分の参考になるページを貼っておきます。
年間計画、週間計画を立てる
ある程度、基礎知識もそろってきたところで、計画を具体的に立てていきましょう。
ここまでの知識をより補強するためにも、
「○○大学 英語 参考書」
などのように志望校名、科目名を入れて参考書のルートを改めて検索してみてください。
上で紹介したページでもおすすめの参考書を紹介していますが、情報は出来るだけ多くの人から集めておくべきです。
ここまでで、何年計画で勉強すれば、合格できそうかの計算も終わっているはずなので、以下のような年間計画を作ってみましょう。
ここで重要なのは以下の5点です。
- 最初の2~3ヵ月は助走期間と考える
- 一般的な受験生よりも過去問演習期間を長めに設定する
- 必ず後ろ倒しされることを想定する
- 1ヵ月=28日のつもりで設定する
- 計画は修正を繰り返す
最初の2~3ヵ月は助走期間と考える
受験勉強を始めるといっても最初の数か月はまともに勉強習慣もついていないので、フルで予定通りに勉強できることはまずありません。
1週間の勉強可能最大時間の20%くらいから始めて、次の週は30%くらい、その次の週は40%くらいと、徐々に勉強時間を伸ばしていってください。
最初からフルで勉強していっても99%の人は失敗しますし、失敗を積み重ねると
と勘違いしてしまいます。
真面目な人ほど、こういうもったいない諦め方をしてしまうので、そうならないためにも最初から全力を出し切らずに徐々に体を慣らしていきましょう。
一般的な受験生よりも過去問演習期間を長めに設定する
一般的な受験生だと、受験年度の10月くらい(遅くとも11月)から過去問を始めて、そこからは過去問演習メインの生活になる人が多いんですが、大人がこれに合わせていると失敗します。
というのも、高校生・浪人生は1日に10時間以上、受験勉強に時間を使えますが、ふつう大人はこれほど時間をさけないはずです。
受験で1番大事なのは過去問演習と言っても過言ではないので、過去問演習期間は一般的な受験生の倍程度、具体的には受験年度の5月~7月には始められるようなペースを想定しておくことをおすすめします。
必ず後ろ倒しされることを想定する
かなり長めに過去問演習の期間を設定しておいても、年間計画は全体的に後ろ倒しされるものです。
素人が最初に考えた計画が、そう簡単に計画通りに進むことはありません。
ましてやプロが計画を作っても、やはり基本的には後ろ倒ししていくものです。
全体的に余裕を持ったペースを意識して計画を立てておいてください。
1ヵ月=28日のつもりで設定する
1ヵ月は30日もしくは31日ありますが、基本的に28日=4週間で計算しておくのがおすすめです。
28日計算にしておいて、残った2日~3日は計画通りに進んでいない部分の補習期間にしましょう。
正直、この期間を入れておいても、それでも後ろ倒しされていくものなのですが、月末の2日3日の計画修正のための追い込みを設定しているだけでも、少しはマシになります。
計画は修正を繰り返す
計画は必ず後ろ倒しされていくので、毎月のように修正していく必要があります。
特に、最初に立てた計画は大雑把なものになっているのが普通です。
みたいなことは頻発するものです。
修正や改善の方法はこの記事の最後の方にまとめておきます。
週間計画を立てる
年間の大雑把な計画が立てられたら次は週間計画です。
「学校の時間割」を思い出して曜日ごとに計画を立ててみましょう。
まずは睡眠、食事、家事、仕事を全て計算して、フリーな時間を出していきます。
最初のうちは「25分勉強5分休憩」を基本の1セットとして、そこから自分に合った1セットを探っていくといいでしょう。
具体的なイメージはこんな感じです。
毎週記録をつけて反省できるように、確実に計画は書き上げておきましょう。
計画を細かく覚えられてる人なんて一人も見たことないですから、ちゃんと書き出してくださいね!
毎週完成系を作っておいて、それを使いながら反省して、次回の分を作るというルーティンを作っておくのがおすすめです。
周りの理解を得る

計画を立ててみると、思ったよりも時間がかかってしまって、「もっとなんとかならないかな?」と思う可能性は高いはず。
周りの理解を得て、時間をもっと確保できないかは確認してみてもいいでしょう。
具体的には
- 家族の理解を得る
- 会社の理解を得る
の2つの要素がありますので、そちらを簡単に説明していきます。
家族の理解を得る
家族の理解を得られれば、
- 家事の負担の分担
- 受験勉強に使えるお金が増える
- モチベーション維持に役立つ
などのメリットがあります。
家事の負担の分担
具体的には、炊事、洗濯、掃除、子育て系業務が少しでも減れば、それだけ分の勉強時間が確保できます。
もし家族やパートナーに受験したい旨を説明して、多少なりとも応援してくれるのであれば、まずは時間を確保するための協力を申し出るといいでしょう。
受験勉強に使えるお金が増える
次にお金の問題です。
こちらはどこかのタイミングで確実に相談が必要になる話です。
もちろん、受験料から卒業までにかかる授業料なども必要になりますが、もし余裕があるのであれば、時短に役立つ家電やサービスが使えるとかなり勉強は有利に出来るようになります。
例えば、
- 乾燥機付き洗濯機
- 自動掃除機
- 食洗器
などがあれば、家事の時間は随分減ります。
また、宅配サービスや家事代行サービスなども利用できれば、こちらもやはり家事の時間を減らすことができますよね。
勉強効率を上げるために、塾や家庭教師を利用することもできるかもしれません。
勉強環境を整えるために自習スペースやコワーキングスペースを借りるのもおすすめできるお金の使い方です。
このように家族と相談して、お金の折り合いがついていれば、受験勉強を有利に進めるために使える選択肢はかなり広がりますので、ぜひ早い段階で1度相談してみてください。
以下の記事にも詳しいことは書いています。
モチベーション維持に役立つ
そして、身内に受験勉強を頑張る旨を伝えておけば、自分自身の退路を断つのにも役立ちます。
合わせてサボっているときには、喝を入れてもらう約束を取り付けておいてもいいでしょう。
会社の理解を得る
会社の理解を得るのも、社会人受験生にとっては大事なことです。
具体的には
- 定時退社、有給消化の徹底
- 進学後の相談
などができるといいかなと思います。
定時退社、有給消化の徹底
社会人が大学の一般入試に受かろうと思ったら、1番大変なのは時間とモチベーションを管理することになりますが、どちらにも邪魔をしてくるのが「残業」です。
圧倒的に残業がなく、毎日定時退社できる環境の方が受験には有利になりますので、定時退社だけは理解を得られるように確実に交渉することをおすすめします。
ってなっちゃうもんなんですよね。
また、有給も消化していますか?
有給1日分をまるまる勉強にあてられれば、それだけでも12時間以上勉強することができます。
消化できていないのであれば、こちらも出来るだけ使っていきましょう。
可能であれば、リモートワークも週に1日だけでも入れられれば、通勤時間分の勉強時間を確保できますし、
車やバイクで出勤するよりも、電車やバスを利用した方が、移動中に勉強もできるのでおすすめです。
こういった細かいことも可能ならば相談してみるといいですね。
進学後の相談
仮に進学できたとして、という話も合格が見えてきたら、会社と相談をしておきたいところです。
そのまま会社を続けながら、大学に通うのであれば、会社にはかなり融通をきかせてもらう必要があります。
時短勤務とかフレックス勤務のようなシステムがないとかなり厳しいかもしれません。
休職も4年間となるとかなり厳しいことが多いと思いますので、そのあたりも含めて話をしておくのがいいでしょう。
もちろん大学に進学できたら仕事を辞めるというのであれば、相談が必要なら相談しておいてください。
相談できないなら転職もあり
勉強時間の確保もままならないくらいにブラックな会社だったり、ブラックではないけど、大学受験の話を上司に相談するような雰囲気ではないような会社の場合は、転職を考えるのもありでしょう。
転職することはリスキーに思えるかもしれませんが、転職活動をすること自体にリスクはほとんどありません。
意外に、転職してしまったらいい会社に出会えて大学受験に対するモチベーションがなくなってしまうかもしれませんが、それはそれで人生が豊かになっていいことかなと思います。
少しでも転職が頭をよぎったら、転職「活動」だけはしてみることをおすすめします。
勉強時間が増えたら、計画も修正を
周りの理解を得られて、無事勉強時間を増やすことが出来たら、計画も上方修正することができるかもしれません。
再度、計算をしてみて、計画を修正してみましょう。
実際、この記事のラストのあたりでも触れますが、計画の修正はかなり頻繁に行うべきことです。
と思ってるうちは大学に受かることはありません。
計算し直す方が、勉強するよりも断然楽ですからね。
勉強法の勉強

計画もある程度完成系が見えてきたら、まずは少し時間を取ってでも「勉強法の勉強」をしましょう。
特に社会人の場合は、高校生や浪人生と違って、勉強に使える時間が限られています。
勉強法に関しては大きく分けて次の2つ。
- 全科目に共通の勉強法
- 各科目の勉強法
この2つを学ぶ必要がありますが、ここではメインに全科目に共通の勉強法を軽く紹介して、以降は「勉強法の勉強」をどうやってするのか解説します。
ちなみに、ここで、この記事の残りはあと3分の1くらいです。
全科目に共通の勉強法
まずは全科目に共通の勉強法についてです。
例えば、次のようなことは1度はどこかで考えたこともあるのではないでしょうか?
- 短期間で一気に進めた方がいいのか、少しずつコツコツ進めた方がいいのか
- 書きながら覚えた方がいいのか、読んで覚えるのがいいのか
- 朝勉強がいいのか、夜勉強がいいのか
- 1時間置きに休憩した方がいいのか、3時間くらい一気に進めた方がいいのか
などなど。
こういった勉強の作戦や手段を考えるのは非常に重要なことです。
自分にあった勉強法は自分で探すしかない部分もありますが、塾講師としては「やってほしくない勉強法」はあります。
勉強効率が著しく悪くなるような手段を避けるだけでも大きいので、ここではそういったことを簡単に解説します。
そのあと、より集中して勉強するためのテクニックも紹介しますから、ぜひそこまで今この瞬間にしっかりインプットしてもらえればと思います。
勉強効率を上げるコツ
今すぐにでも使えるようになってほしい、勉強効率を上げる方法は以下の通り。
- 分かることではなく分からないことに時間を使う
- 手を動かす時間をできるだけ長く作る
まずは分かることではなく、分からないことに出来るだけ長い時間を使っていきましょう。
例えば、「ノートまとめ」などはテスト勉強の手段としてこれまでに使ってきたことがあるかもしれませんが、ノートまとめをするときには、
「教科書を読んで理解できたこと」
をもう1回書いていませんでしたか?
勉強が得意な人は、同じノートまとめをするにしても(ノートまとめ自体をあまりおすすめしませんが)、
- 覚えていない部分を書き出す
- 理解できていない部分を後で調べるためにまとめる
などのように分からない部分に時間を割きます。
分かる部分ではなく、出来る限り「分からないこと」を「分かること」にするために、
あるいは「覚えていないこと」を「覚えていること」にするために時間を割くようにしましょう。
またその時間を長くするためには、出来るだけ問題を解く時間を増やすのが1番手頃です。
ノートにまとめたり、授業を聞いたり、というのは、「わかること」にあてる時間を絶対にゼロすることはできません。
一方で、問題演習の2周目以降に関しては、「分かっていること」「覚えていること」に使う時間を限りなくゼロに近づけることができます。
出来るだけ問題を解くなどの手を動かす時間を多くとるようにしましょう。
集中して勉強に取り組むコツ
次に集中して勉強に取り組むためのコツについて。
- 脳を疲れさせずに勉強をする
- 休憩を制御する
の2点を徹底的に意識してもらいたいところ。
脳を疲れさせる行為は、例えば
- 休憩と称してスマホを眺める
- BGMをかけながら勉強する
- 次に何を勉強するか考える
あたりは全てNGです。
スマホはいじっているだけで脳は疲れますし、BGMを聞きながらの勉強も脳は疲れてしまいます。
また次に何を勉強するか、考えるだけでも脳は疲れてしまうので、事前に計画を立てた状態で勉強するのがおすすめです。
また、休憩を上手くとれば、集中力を出来るだけ高い状態で維持しながら、次の勉強に移ることができます。
具体的には
- 中途半端でも時間で区切って休憩する
- 短時間の勉強と短時間の休憩を繰り返す
- 勉強の復帰を阻害するものと物理的に距離を取る
などは早い時期から徹底できるといいでしょう。
そこから復帰するのが難しくなるので、時間で区切って、短時間の勉強と短時間の休憩を繰り返すのがおすすめです。
また休憩中はスマホを触らない方がいいのは上述の通りですが、それだけでなくもちろん、
- テレビ
- 本、マンガ、雑誌
- ゲーム
- ベッド
などからも物理的に距離を取っておくのがおすすめです。
誘惑に打ち勝つ努力をするよりも、そもそも誘惑のない状況を作り出す方が圧倒的に簡単です。
各科目の勉強法
改めて、各科目の勉強のルートを確認しましょう。
そのうえで、それぞれの科目の参考書をどのように進めていくのが効率的なのか調べてみてください。
具体的には「単語帳 勉強法」などと調べる具合です。
さすがにここから全ての参考書のパターンを書いていくと長すぎてそれだけで一冊の本以上の分量になってしまう可能性があるので、ここでは省略しますが、やはりここでも調べものをしていくのは重要です。
調べれば調べるほど、いろんな勉強法が出てきて
などと混乱してしまう可能性はあると思いますが、そのときの対処法は2つです。
- 事前に科学的に正しい方法をインプットしておく
- 迷ったらまずは試して評価する
事前に科学的に正しい方法をインプットしておく
事前にある程度、正しい方法をインプットしておくのがおすすめです。
こちらについてはこの後すぐにおすすめの書籍などを紹介するので、そちらを本格的な勉強を始める前に読んでおくようにしましょう。
勉強法の本程度が読みこなせないくらいでは、さすがに受験勉強を最後まで頑張り切るのは不可能なので、そういったテクニックはサッサとインプットして、自分の中に判断基準を作っておくといいでしょう。
迷ったらまずは試して評価する
本を読んで判断基準を作ってもなお迷いが生じることはあるはずです。
といったことは全然あり得ます。
迷ったときには、まず試す、そしてどっちが良いか判断する
ということを繰り返して、自分に合った方法を探していくしかありません。
最初から完璧な勉強スタイルで勉強を進められるような人間は日本中探しても一人もいません。
みんな迷いながら勉強しているので安心してください。
みんなが迷っている間にあなたはAとBの両方を試して正解を引き当てればいいだけです。
勉強法の勉強の仕方
判断軸を作るために勉強法の勉強の手順についておすすめ書籍も合わせて簡単に紹介します。
具体的な手順は以下の通り。
- 本を何冊か読む
- 科目ごと、参考書ごとに勉強法を調べる
- 試して選択&改善を繰り返す
それぞれ説明します。
本を何冊か読む
まずは手始めに本を何冊か読んでみるといいでしょう。
これまで本を読んで来なかった人も大勢いらっしゃると思いますが、普通に英語や数学の勉強をするよりは勉強法の本を読む方が楽なので、構えずに気楽にチャレンジしてみてください。
とりあえず何か1冊というのであれば、こちらの本がおすすめです。
辞書的にこちらの本も置いておくのもありですね。
また、勉強法に関しては、このブログの中でも詳しい記事が1つありますので、そちらもぜひ参考にしてみてください。
科目ごと、参考書ごとに勉強法を調べる
勉強法一般のことを書いた本はたくさんありますが、各科目、各参考書の使い方を網羅的にまとめた本はなかなかありません。
単語帳の使い方、青チャートの使い方などの各科目各参考書の具体的な勉強法は各自が丁寧に調べるのがおすすめです。
具体的には
「参考書名 勉強法」
とググって出てくるものを10サイト程度は眺めてみましょう。
どうせ大学に進学して調べものをしなくてはいけなくなったときは、10程度の文献にあたるのは別に普通のことです。
その中で、1番良さそうなものを選んでやってみましょう。
試して選択&改善を繰り返す
調べて出てきたもので、
「AとBのやり方どちらにすべきか迷う」
というときはとりあえず、2週間はAで、次の2週間はBで、というように期間を決めて試してみましょう。
それで上手く進んだほうを選択すればOKです。
場合によっては、組み合わせて自分なりにアレンジするのもいいでしょう。
勉強&改善

最後は勉強と改善です。
ここまで読んでくださって、さらにこの記事に書いてあることもしっかり実践してくださったあなたなら、後は勉強するだけの状態です。
ですが、勉強も最初から上手くいくことはありません。
- 思っていた分の勉強時間が確保できない
- 思っていた通りのペースで進まない
- 難しすぎて挫折しそう
- モチベーションが下がってしまった
など、いくらでも障害は出てきます。
そのたびに何かしら乗り越える必要が出てきます。
そのコツは以下の3点です。
- 計画を立てること
- 記録すること
- 改善点を書き出すこと
計画を立てること
勉強は毎週の計画を立てつつ進めましょう。
毎日計画を立てているとさすがに時間を取られすぎるので、1週間単位くらいで大丈夫です。
計画を立てて勉強する理由は
- 反省をしやすい
- 自分のペース感がつかみやすい
の2点になります。
まず、計画を立てないと今週の勉強がどうだったのか数字を使って判断することが出来なくなってしまいます。
では、成長するのに時間がかかりそうな気がしますよね?
計画と比べて
などと数字で判断出来る方が圧倒的に、勉強の改善が早く進みます。
また、毎週計画を立てていると、「だいたいこの参考書は1時間で5ページくらい進むな」と自分の勉強のペースが分かってくるようになります。
ペースが分かってくれば、計画はより確かなものになりますし、1週間ごとだけでなく、1年を通しての見通しもだんだんと立ちやすくなります。
記録すること
計画を立てて、勉強するのと同時に、記録をつけていきましょう。
最低限、「時間」と「量」は記録しておきたいですね。
記録をしておけば、「1時間あたりに何問、あるいは何ページ進むのか」が分かることが大事なのは上述した通りです。
毎日記録を正しくつけられる人は受験勉強をかなり有利に進められます。
改善点を書き出すこと
計画を立てて、記録をつけていれば、反省すべきことは自然と見えてくるはず。
反省すべきことは
- 勉強時間が短くなかったか?原因は?
- 予想の量と違っていないか?原因は?
を軸に考えていけばいいでしょう。
必ず原因とセットにして考えるようにしてください。
原因としては例えば、
- 難易度が適切でなかった
- 朝起きるのが遅かった
- 体調が悪かった
- 休憩が長かった
- 急な予定が入った
などなどいくらでも出てくるはずです。
出来るだけ具体的に、上手く行かなかった原因を思い出してみましょう。
改善点は思いつくたびに、スマホやメモ帳に書き貯めておくのがおすすめです。
逆に言えば、そのくらいは失敗をするものと最初から覚悟しておくと、少し気持ちは楽かもしれませんね。
毎週最大5個くらいを目標に、改善点を見つけて普段の勉強に取り込んでいきましょう。
最後に
かなり長い記事になってしまいましたが、ここまで読んだのであれば、後はこの記事に書かれてあることを確実に実行して、やめなければ合格できます。
やめないことも合格に非常に重要な要素の1つなので、忘れないようにしておいてもらえればと思います。
こちらの記事をさらに加筆グレードアップしたkindle本も出版したので、興味があればこちらからどうぞ!
さらに、「大人のための受験相談」や「家庭教師」もやってます。
受験相談は、大学受験に関することはなんでも聞いてもらってOK。
次のような方にお勧めです。
- まだ大学受験するかどうか決めきれない
- 大学受験までにやるべきことがわからない
- 目指す大学、学部を決められない
- 入試形式を決められない
- 中卒でも高卒でもOK
- 大卒の再受験もOK
興味があれば、こちらから。
また、オンラインの家庭教師もやっています。
いちおう、指導可能な生徒さんの条件は絞っています。
- 中学教科書レベル〜大学受験レベルの勉強を指導してほしい方(ただし現状の学力は問いません。基礎中の基礎からの指導もOKです。)
- 毎日10時間以上コンスタントに勉強できる方(学校+自習の合計時間でOKです。社会人の方は「仕事+自習=10時間」でOKです。)
- 言われた課題は全てこなそうとする根性のある方(自分の好きなように指示を曲げる方は向いていません。)
その他、詳細は以下のページに書いているので、興味があればご確認ください。