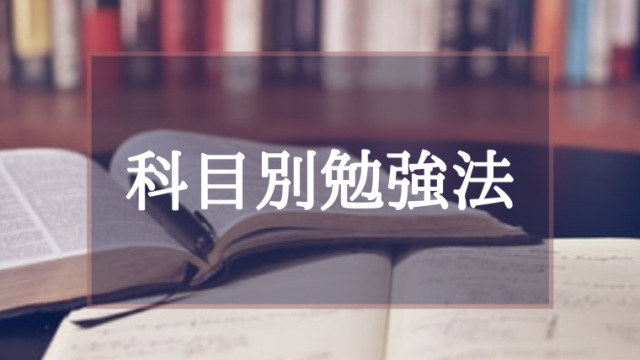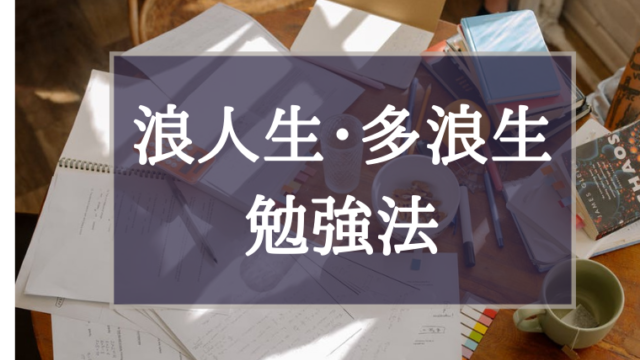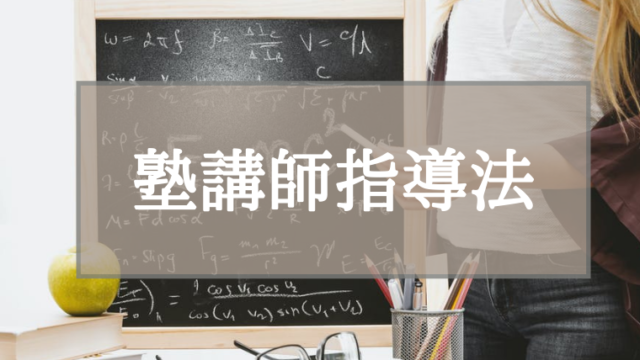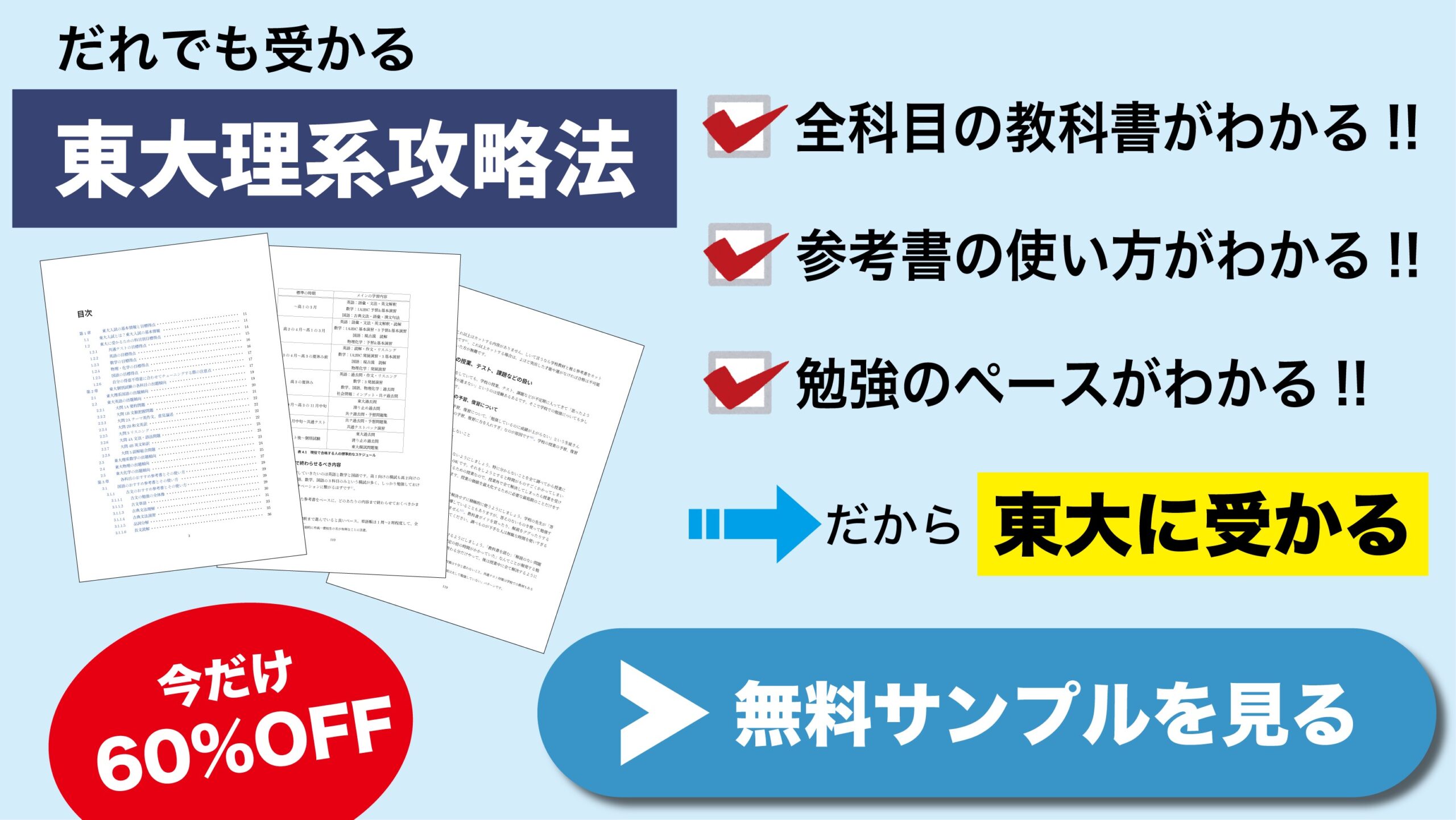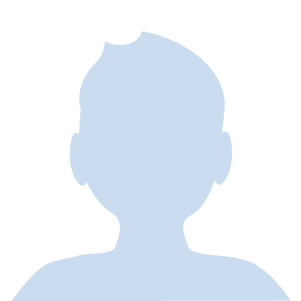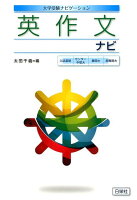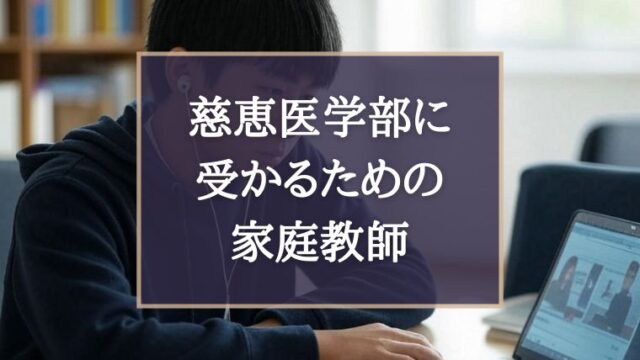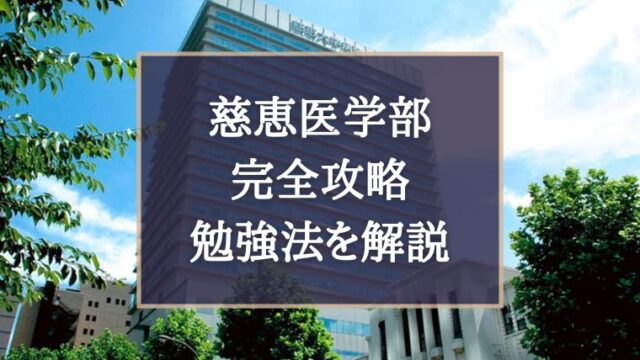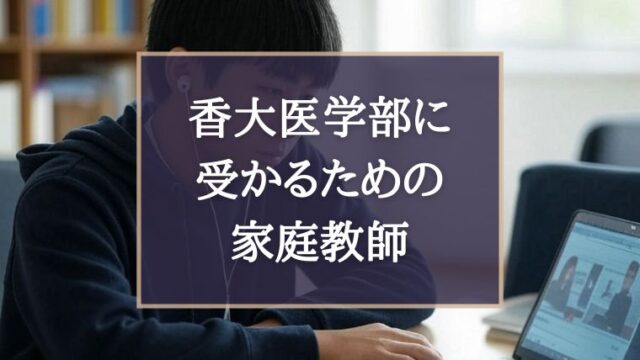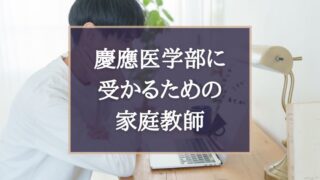【15年のプロが徹底分析】慶應医学部合格への最短ルート!科目別対策、参考書、勉強法を完全網羅

ども、ぽこラボ所長です!
今回は慶應の医学部対策について。
個別指導歴15年の私が5時間以上かけて、過去問などを分析し、自分が今受験するならどうやって勉強するかをまとめました。
その結果をどうせなら、他の受験生にもシェアしようと思います。
ちなみに東大の滑り止めで受験していた学生も数年前に1次試験は通ったので(2次試験は辞退)、そのときの経験も参考にしています。
この記事を読めば、具体的な参考書名やその使い方、勉強のスケジュールなど、合格に必要な内容は全てわかります。
あとは、必死に勉強してこなし切るだけの状態になりますから参考にしてくださいね!
目次
慶應医学部に合格するための目標得点を過去の入試から検討

どの大学を目指すにせよ、まずは合格最低点の確認と、合格最低点を超えるために各科目で何点ずつを取っていくかのチェックが必要です。
合格最低点の推移
慶應医学部の1次試験の合格最低点は次のように推移しています。
- 2024:63.8%
- 2023:63.0%
- 2022:61.6%
- 2021:50.2%
- 2020:60.6%
さらに遡っても63%を少し超えるくらいが最大となっています。
とはいえ、1次合格者の半分くらいが2次合格、それに少し追加で補欠合格が出るくらいなので、もう少し高めの70%くらいの得点率は目指したいところです。
過去問を解く際には70%を目標に勉強を進めるといいでしょう。
科目別の配点と目標得点
慶應医学部の配点は次のとおりです。
数学 150点
理科 100点×2科目
英語 150点
+
2次試験で小論文と面接
合計が500点なので、70%だと350点あたりが目標になるということですね。
各科目の難易度も考慮した目標点数は次のとおりです。
- 数学:105点~120点
- 理科:130点~140点
- 英語:105点~120点
問題の難しさだけ見れば、どの科目も大差ありませんが、明らかに理科が分量的に厳しいです。
その厳しい理科の配点が200点分あるので、そこが大変な部分だと思います。
数学と英語は70%を切らないように、理科は65%を切らないように、というイメージで演習をするのがいいでしょう。
慶應医学部の過去問分析を科目別に紹介!

それでは、次に過去問を分析すると分かる各科目の特徴を確認していきましょう。
慶應医学部の英語の特徴
英語は大問3問構成。試験時間は90分です。
大問1は長文問題で、「英語→日本語」「日本語→英語」の両方の訳の問題が複数問出題される比較的重めの問題です。
長文の語数はそれほど多くはありませんが、ガッツリ記述問題だらけなので、時間がかかる大問です。
大問2も長文読解問題ですが、こちらは問題としては、穴埋め問題や選択問題が多くなるので、大問1よりはやや短時間で解き終えられる問題です。
とはいえ、どちらも800語を超えるような長い文章なので、それなりに長文読解の演習は必要になりますね。
大問3は自由英作文の問題。テーマが設定されていて、自分の意見を100語程度の英語で記述します。慣れればそれほど難しくはない問題でしょう。
時間配分としては、大問1に35〜40分。大問2に25〜30分。大問3が20〜25分といった所ですね。
慣れれば大問3の英作文は15分くらいで書き切れる受験生も多いかもしれません。
また、文章の内容を問われる問題で間違えるわけにはいかないので、吟味の時間を確保するためにも、作文をスラスラ書けるようになる必要があります。
日本語→英語の作文も、自由英作文も「減点のない」答案を素早く書けるようにトレーニングする必要がありますね。
- 2問長文読解、1問自由英作文
- 日本語→英語、英語→日本語の問題が多い
- 大問1:35~40分、大問2:25~30分、大問3:20~25分
- 和文英訳、自由英作の問題を素早く解いて、文章内容問題に時間を使う
慶應医学部の数学の特徴
数学は大問4問構成。試験時間は100分です。
数学で高得点を取って差をつけたい受験生にとっては、やや時間制限が厳しめですが、7割あたりを狙うのであれば、時間的な厳しさはそれほどではありません。
解答形式としては、ほぼすべて穴埋め問題になっています。
大問1は小問集合で、独立した小問が3問程度出題されます。大問1は簡単なので、合格者のほとんどは全問正解しているはずです。
大問2〜4は、それぞれ1つずつが独立した大問になっています。
大問2はほとんど毎年のように確率・場合の数の単元から出題されるので、これが安定して解けるようになっておくことは大きいですね。
また、残りの大問も数3・Cの単元からの出題の可能性が非常に高いので、しっかり演習して得意分野としておきましょう。
大問2〜4は、穴埋め前後に文章があるので、ちゃんと読めば誘導を感じられます。なので、ものすごく発想力を必要とするわけではありません。
合格最低点を考えると、大問1つをまるまる落としてしまうと、それだけでかなり大きなダメージになるので、どの問題も最低でも半分以上は解きたいところです。
大問1、2は全問正解し、大問3、4はどちらも半答以上あたりが目指すラインかと思います。
- 小問集合+大問3問
- 大問2は確率・場合の数から出題の可能性大
- 大問3、4は数3・Cからの出題の可能性大
- 大問1、2は完答、大問3、4は半答以上を目指したい
慶應医学部の化学の特徴
慶應医学部の理科は2科目を120分で解くので、化学は60分を基準として、±5分~10分程度が化学に使える時間と考えるといいでしょう。
正直、かなり時間的にはシビアだと思います。
化学の面倒な所は年度によって、出題傾向だったり難易度だったりにバラつきがあるところですね。
大問は3問構成になっていることが多いですが、そうでない年もあります。
小問集合が入っている年もあれば、そうでない年もあります。
難しい問題(問題集では見かけない内容)が出ることも多いですが、大問全体が難しいということはないので、ちゃんと勉強すれば7割を狙うのは難しくはありません。
解答形式としては、選択肢を選ぶ問題よりは、自分で記述する問題が基本です。
頻出分野はこれと言ってありませんが、ざっくり言えば、理論から大問1つ、有機(高分子含む)から大問1つは確定で良いと思いますが、無機はそれ単体で出る感じの問題は少ないです。
結局70%以上を狙うのであれば、どの単元が苦手でもダメなので、ヤマを張らずに全部勉強しておくしかないですね。
- 時間的には厳しい
- 大問全体が難しいものはほとんどない
- 選択問題はほとんどないので記述に慣れなければいけない
慶應医学部の物理の特徴
物理も時間配分としては、60分±5分~10分と言った所です。
こちらは比較的、出題形式は安定はしていて、小問集合の大問が1題と、そうでない大問が2題の計3つです。
完答できる問題です。
残りの大問2、3は問題集で見かける可能性の低い問題が割と出るので、見たことある問題じゃないと対応できない人は全滅しかねません。
逆に慣れていれば、7割までは狙えるはずなので、過度にビビる必要はないでしょう。
ただし出題単元としては、力学と電磁気がそれぞれ1題ずつ、といった感じではなく、波動から1題、電磁気+原子から1題、といった感じで、どこから出るかはわかりません。
苦手単元が出題されると大問1つまるまる落とす可能性があるので、苦手単元がある状態はさすがに危険すぎます。
- 時間的には厳しい
- 小問は完答を狙いたい
- 大問2と3はどこから出題されるか分からないからヤマは張れない
慶應医学部の生物の特徴
※生物は自分の指導対象外の科目なので、リサーチしたことをベースに書いていることをご承知おきください。
生物は理科の中では最も時間的にはハードです。
生物選択の場合は、生物に70分くらいはかかるものと思って、化学は50分くらいで解き切りたいですね。
大問は3題。基本的にどの問題も初めて見る実験の考察になっていると思っておくのが無難です。
文章中には簡単な穴埋め問題や、簡単な用語の説明などの易しい問題も割と含まれているので、3割くらいまでは基本的な知識だけで解けます。
とはいえ、受かるためには70%くらいを狙いたいですから、厄介な考察問題系も、最低でも大問2つ分は飛ばさずしっかり立ち向かう必要がありますね。
数行程度の論述だったり、図を描かせる問題だったりも出るので、問題集や過去問で演習を詰んでおかないと、生物が得意でも時間的にはかなり厳しいはずです。
- 理科の中では最も時間的にシビア
- 簡単な穴埋めや用語説明などは完答必須
- 実験考察系の演習は十分に積む必要がある
慶應医学部の小論文の特徴
慶應医学部の小論文は公表されていないようです。
いちおう
- テーマとなっている文章を読んで
- それに対する自分の意見を
- 600字程度で書く
- 60分の試験
であることは間違いなさそうです。
試験時間内にそれなりにまともなことが書けさえすれば、ほとんど他の受験生と差がつくことはないはずです。
ほとんどの受験生の合否は、英数理で決まっているものと思って、勉強しておくのが無難です。
とはいえ、普通に読んで、違和感のないくらいには普通のことが書けないといけないので、その練習は必要です。
ときどき、突飛なことを書こうとして、意味不明な文章が出来上がってる人がいるので要注意です。
- テーマ文を読んで60分で600語
- まともなことを時間内に書ききる練習は必要
慶應医学部の面接の特徴
面接も特に特徴的なことはありません。
受験生1人に対して面接官が2人の、10分の面接が2回あります。
慶應医学部を志望する理由や、医師を目指す理由など、割と普通の質問がされるようです。
圧迫面接的な雰囲気もなさそうな口コミが多いので、時間をかけて対策するほどではないでしょう。
ただし、これまでの指導経験上、「慶應医学部を目指す理由」は答えられない人が多い印象です。
- 受験生1人、面接官2人の10分程度の面接が2回
- 普通の面接対策をすればOK
慶應医学部に合格するためのおすすめ参考書を全科目解説!

それでは続いて、慶應医学部に合格するためにやるべき参考書を全科目解説していきます。
予備校や塾で教わっている方も多いと思いますが、部分的に独学でやっている人も多いと思うので、自分で勉強している科目だけでも参考にしてもらえればOKです。
英語おすすめ参考書と学習スケジュール
英語を独学でやるのであれば、最も参考書の数としては多くなります。
それぞれ軽く説明してからスケジュールの説明をします。
単語:ターゲット1900
まず単語は、大学受験用の単語帳であれば正直なんだっていいです。
何も持ってないなら「ターゲット1900」をおすすめしますが、「システム英単語」だろうが、なんだろうがOKですね。
ただし、個人的には「速読英単語」はあまりおすすめはしません。
と勘違いする人を生んじゃうからですね。
その程度では全然足りてません。
あと医学部系の単語帳や、大学受験以上の難易度の高い単語帳も必要ありません。
単語帳の暗記に使う時間があるなら、1つでも長文を多く読んで、そこに出ている単語を全部覚える方が得点には繋がります。
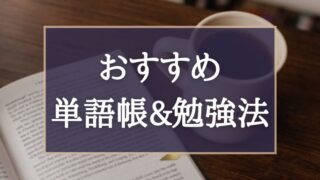
文法:入門英文法問題精講、Scramble
文法が分からないと、その他の勉強が何もできないので、最低限の勉強は必要です。
「入門英文法問題精講」は学校の授業後すぐに解けるくらいの易しいレベルの問題集。
学校のテキストや予備校のテキストがあるのであれば、それを使って、自力で全部解けるようにするのでも構いません。
「スクランブル英文法・語法」は4択系の問題集。こちらはどちらかというと、基本事項の暗記のために何周も解くものですね。
「NextStage」「Vintage」「アップグレード」などを持っているのであれば、それでもOKです。
何を使っても大差はありません。
こういう4択系の問題集は読んでるだけの人も多いですけど、ちゃんと解くのがコツです。
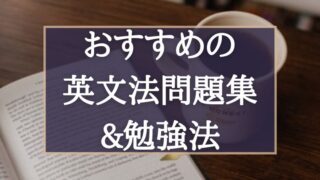
英文解釈:基本文法から学ぶ英語リーディング教本、基礎英文解釈の技術100
英文解釈はSVOCだったり、○○句、○○節だったりをちゃんと自力で説明できるようにするための訓練です。
最近は「基本文法から学ぶ英語リーディング教本」がちょっとぶ厚いけど、おすすめです。
用語をしっかり理解できると思います。
しっかり理解できたら「基礎英文解釈の技術100」みたいな少し骨のある参考書で実践的に和訳の訓練をするのがいいでしょう。
「英文熟考」などでも構いません。
予備校とか塾とかで授業を受けてる人も多いかもしれませんが、初見の文章を自力で解釈できるようになるための練習は絶対に必要なので、覚えておきましょう。
難しいものもけっこう売ってるんですけど、ある程度、演習を積んだら、やはり長文の演習を1回でも多く積むことが高得点を取るためのコツです。
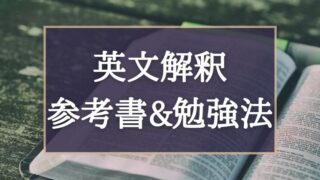
長文読解:基礎英語長文問題精講、英語長文ポラリス2、英語長文プラス記述式トレーニング問題集
長文読解は300語くらいのものから始めて、徐々に長いものにもチャレンジしていきましょう。
「基礎英語長文問題精講」は、そこそこ短い文章からそこそこ長い文章まで、1冊でかなりたくさん収録されているのでおすすめです。
「英語長文ポラリス2」は長めの演習としておすすめ。解説も分かりやすいですね。同シリーズの「英語長文ポラリス3」もやってみてもいいでしょう。
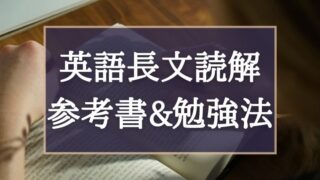
「英語長文プラス記述式トレーニング問題集」は記述の練習としては、かなり訳に立つと思います。
割と記述がしっかり出題されている問題集は多くないので、記述が苦手な人は練習してみるといいでしょう。
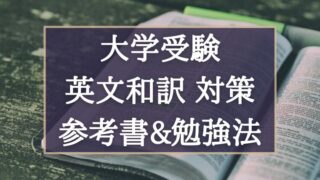
とはいえ、慶應医学部の英語の記述は「読めれば解ける問題」ばかりなので、まずはしっかり読めるようになることが大事ですね。
解説された文章を音読したりするのも有効ですが、ちゃんと実力を伸ばしたいなら初見の文章をガンガン読む訓練も必須です。
学校・塾・予備校の授業を受けるだけで満足しないようにしましょう。
英作文:減点されない英作文、英作文ナビ、英作文のトレーニング自由英作文編
英作文は「減点されない英作文」がおすすめです。
とにかくまずは減点されないことが重要ですからね。この参考書には、そのコツが書かれています。
余裕があれば、「英作文ナビ」のようなガッツリ和文英訳のトレーニングができる参考書で練習して暗記もしておけば怖いものなしです。
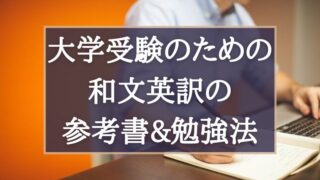
ちなみに自由英作文については、和文英訳ができればそれほど難しくはないと思いますが、もし苦手であれば、「英作文のトレーニング自由英作文編」もやってみてもいいでしょう。
作文はできれば添削をしてもらうようにしましょう。
だいぶ慣れないと、自力で間違いに気づくことができないですから、過去問20回分くらいの文量は添削してもらうイメージで勉強をすすめるのがおすすめです。
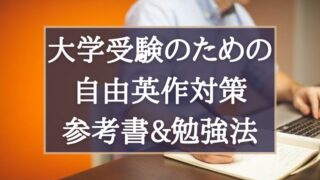
スケジュール
次にスケジュールについて。
ここでは理想のスケジュールを解説しますが、そこから遅れている場合は基本的に勉強量でカバーするつもりで勉強してください。
単語、文法、解釈はできるだけ高2のうちに全て終わらせましょう。
基礎が入ってなければ、模試でも点が取れないですし、解説を読んでも理解できない部分が残ってしまうからですね。
遅くとも高3のGWには解釈まで終わらせて、そこから先は長文と作文の勉強に全集中です。
そして10月頃からは過去問を始められるとベストですね。
同じレベルの大学や、滑り止めもいくつか受ける人が多いはずなので、10月頃には始めないと十分な演習をできないまま入試に突入してしまいます。
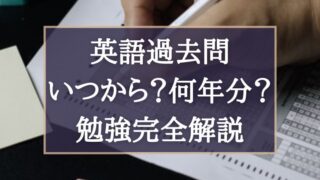
数学おすすめ参考書と学習スケジュール
理系科目は英語と比べれば必要な参考書は多くありません。
数学のおすすめ参考書は以下の通りです。
基本的には「青チャート」と「上級問題精講」ができれば問題はありません。
高校の授業が遅ければ、独学あるいは塾などで予習が必要になるかもしれません。
独学でやる場合は「スタディサプリ」などを使うのがおすすめです。
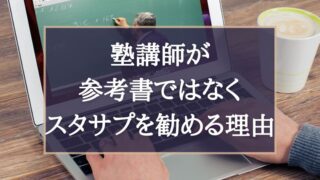
ちなみに「青チャート」の代わりに、「フォーカスゴールド」や「赤チャート」、「ニューアクションレジェンド」などを使うのもOKです。
このあたりはどれを使っても大差ありません。
「黄チャート」は若干、慶應レベルを目指すには易しすぎる気もしますが、ギリギリ許容範囲といった所です。
この他、「1対1対応の演習」や「標準問題精講」などを利用しても構いませんが、問題数が少ない分、易し目の問題は収録されていないことに注意してください。
計算力に自信がない人や、数学が苦手な人は分厚くても青チャートをやった方がいいです。
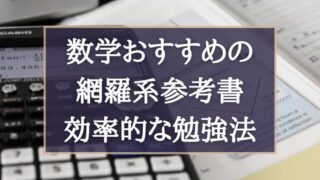
「青チャート」などで標準的な問題が解けるようになったら、発展的な問題集で演習です。
おすすめは「上級問題精講」ですが、これ以外にも
などを選んでも大体同じレベルまでは到達できます。
これ以上の問題集もありますが、そこまでやってる暇がある人は少数派だと思います。
ここまでやり切って、過去問を併願校まで含めて10年分満点を取れる状態を目指してから、次の参考書を考えるので十分です。
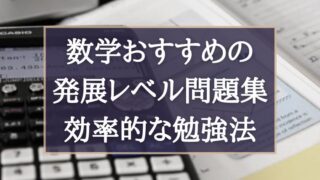
青チャートのような網羅系問題集は、高3のGWあたりまで、数3も含めて全ての例題を自力で解ける状態にしましょう。
発展的な問題集は9月末までに仕上げるのを目標にして、10月から過去問演習に入れればかなり良いペースです。
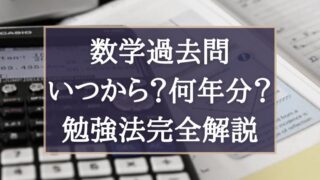
もし1ヶ月くらい余裕があれば、「解法の探求確率」で大問2対策ができるといいですが、別にこれはなくても大丈夫です。
物理おすすめ参考書と学習スケジュール
次は物理について。
物理のおすすめ参考書は以下の通りです。
まずは「セミナー物理」のような学校で配られる分厚い問題集を全問題解ける状態にしましょう。
発展問題、総合問題まで解けるようにすれば、慶應医学部は難しくても、もう少し低いレベルの大学までなら医学部でも対応できます。
セミナー以外にも「リードα」「センサー」「アクセス」「ニューグローバル」など400問〜600問くらい載ってるものであれば、なんでもかまいません。
学校で1冊指定されていることが多いのではないでしょうか。持っていなければ、「エクセル」を使うといいでしょう。
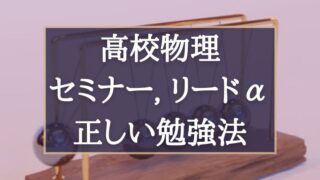
それが終わったら次は「重要問題集」です。
こちらも学校で指定されるパターンが多いと思います。
「重要問題集」のB問題まで解けるようになれば、過去問でも半分以上は解けるようになるはずです。
あとは過去問演習だけでも十分ですが、余裕があれば、「名問の森」もやっておくとより安心できるかと思います。
「難問題の系統とその解き方」というレベルの高い問題集もありますが、ここまで全部できる人は現役生にはほとんどいませんし、これをやるくらいなら先に過去問を入手できるだけ全て満点を取れる状態にする方がおすすめです。
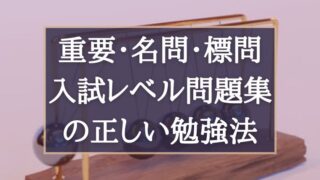
スケジュールとしては、セミナーレベルを夏休み前くらいまでに卒業して、重要問題集レベルを夏休み〜9月を使ってやり切るイメージで進めましょう。
学校の授業が遅いなら物理も「スタディサプリ」などで予習が必要になることもあります。
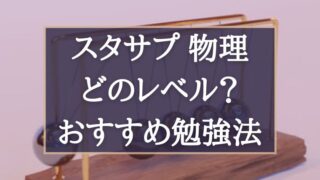
10月頃から過去問演習に入れれば順調です。
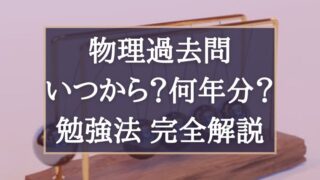
化学おすすめ参考書と学習スケジュール
化学のおすすめ参考書は以下の通りです。
- セミナー化学
- 重要問題集
- (化学の新演習★3のみ)
基本的には物理と同じく「セミナー」レベル、「重要問題集」レベルができれば十分です。
「セミナー」の代わりに「リードα」「センサー」「アクセス」「ニューグローバル」など400問〜600問くらい載ってるものであれば、なんでもかまいません。
学校で配られている場合が多いと思いますので、まずはそれを発展問題や総合問題まで全て解けるようにしてください。
持っていなければ「エクセル」を使ってください。
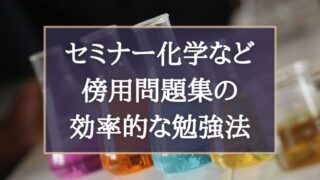
次に「重要問題集」です。
こちらも学校で使う場合が多いはずです。
化学の場合は、物理や生物よりも若干「重要問題集」が易しいので、余力があれば「化学の新演習」の★3(難易度の高い問題)を解いておくのもおすすめです。
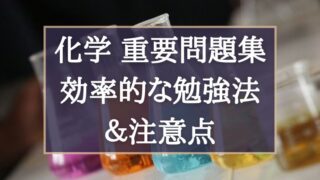
セミナーレベルを夏休みまでに終わらせて、重要問題集レベルを9月末までに終わらせられれば順調です。
学校の授業スピードが遅い場合は、「スタディサプリ」などを使って独学で予習が必要になることもありますね。
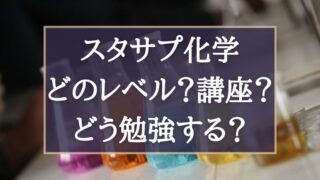
過去問は10月から入れると良いペースです。
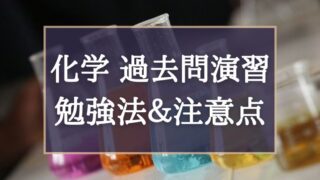
生物おすすめ参考書と学習スケジュール
生物のおすすめ問題集はこちらです。
- セミナー生物
- 重要問題集
まずは「セミナー」からですね。
基本的には化学と同じで、「リードα」「センサー」「アクセス」「ニューグローバル」などの学校で指定されている問題集をまずは攻略しましょう。
生物は化学、物理と比べると暗記事項も多いので、用語の穴埋めをするだけの問題もちゃんとこなしておきたいですね。
持っていなければ「エクセル」を使ってください。
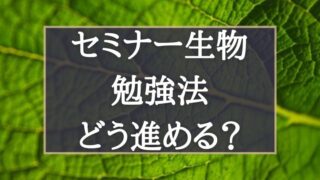
終わったら「重要問題集」です。
「重要問題集」までやり切ったら、あとは過去問をやるのがおすすめです。
難易度の高い問題ばかり集めている問題集が割とないので、過去問を解きながら練習するのが1番ですね。
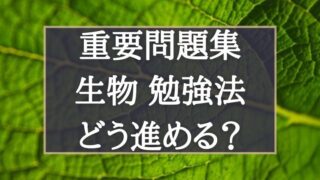
セミナーレベルを夏休み前まで、重要問題集を9末までに終わらせるのも同じ。
10月に過去問演習に入れるとかなり順調なペースです。
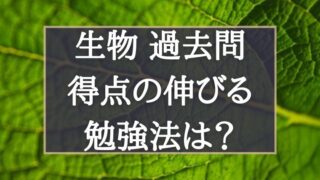
過去問演習のスケジュール
ここまでに説明してきた通り、過去問は10月からスタートできれば最高です。
現役生は実際にはもう少し遅めのスタートになる科目も出てくると思います。
浪人生の場合は逆にもっと前倒しになることもありますが、前倒しになる分にはいくらでも前倒ししてしまっても構いません。
第1志望は10年以上は満点を取れる状態を目指してください。
第2志望以下も5年以上は演習しておきたいところですね。
理科や数学は過去問演習をしないと身につかない思考力がありますし、英語のスピード感も過去問を使わないとなかなか身につきません。
ある程度の量は必要だと思っておきましょう。
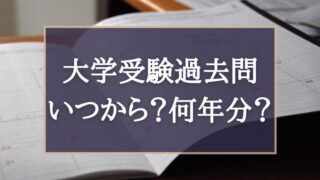
小論文おすすめ参考書と学習スケジュール
小論文は、医学部系の小論文の参考書を1冊こなせば十分です。
頑張れば、個別試験が終わってからでも十分間に合いますが、苦手意識がある人は夏休みに少しまとめて勉強しておくのがおすすめです。
例えば、次のような参考書を使うのがいいでしょう。
最初から時間内に600字程度書ききれるようなら、個別試験後にスタートでも十分間に合います。
面接対策おすすめ参考書と学習スケジュール
面接対策は最低限、面接のマナーを身につけたり、想定される質問の答えを準備しておくだけで十分です。
上述したように面接で大きな差がつくことはないと思って構いません。
とはいえ、準備無しで挑むとひどいやり取りをしてしまう人も多いと思います。ちゃんと準備しましょう。
とりあえずこちらを一通り読んで、自分なりに面接の準備をできれば問題ないはずです。
可能であれば、学校や塾の先生と模擬面接を何度か繰り返して、フィードバックをもらっておくのをおすすめします。
特に志望動機がフワッとした人が多いので、要注意です。
受験すべき模試

次に受験すべき模試について、まとめておきます。
受験するのがおすすめなのは、次の3種類ですね。
- 駿台全国模試(記述):6月初旬、9月下旬あたり
- 河合全統記述模試:5月初旬、8月下旬、10月初旬あたり
- メディカルラボ私立医学部模試:6月、9~10月あたり
基本的に駿台と河合の記述の模試は全部受けるといいでしょう。
医学部受験をする人なら全員受けてます。
※駿台のベネッセと共同で実施している記述模試は簡単なので、受ける必要はありません。
医学部系の模試としては、メディカルラボの模試が河合塾グループが運営しているので、おすすめです。
他の医学部模試もありますが、現役生は少なくともこれ以上受けるのは現実的ではないと思います。
進研模試あたりを必須で受けなければならない人も多いですからね。
模試を受けるだけ受けて、復習しないというのはさらに不合格を引き寄せる勉強法なので、そちらも注意してくださいね。
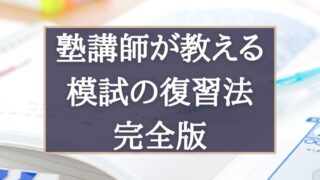
浪人した場合の学習方針とスケジュール

慶應医学部レベルになると浪人する人もそこそこいて、年によっても違いますが、大体20%〜40%ほどは浪人生です。
そこで、浪人した場合の学習方針とスケジュールも見ていきましょう。
模試でB判定以上の場合
浪人の前年度に、模試でB判定以上の成績を取れているのであれば、基本的には過去問演習をメインに、苦手科目だけ参考書を使う形でも十分合格できます。
予備校を使う場合
予備校を利用する場合は、授業を真面目に受けすぎないように注意してください。
知っている部分の説明をしているときは自習して、知らない部分の解説をしているときだけ集中して授業を聞くようなスイッチングをするのが重要です。
授業とは別に、3月から週1以上で過去問を解き続けて、10月ごろには10年分以上は満点を取れる状態を目指しましょう。
苦手単元は参考書や授業を使って勉強し、夏休み前くらいの時期にはすべて処理しきっているのが理想です。
滑り止め校や、似たレベル(慈恵医科、順天堂、日本医科)の大学の過去問も10年分以上、満点を取れる状態に仕上げれば、まず間違いなくどこかには引っかかります。
時間を計ってちゃんと解き、しっかり復習することをくり返していけば、自然と点数は上がっていきます。
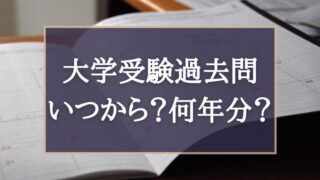
予備校の授業では、苦手単元や科目を集中してフォローしていき、苦手がなくなった段階で、合格最低点を超えることも難しくなくなっていくでしょう。
- 3月から週1以上で過去問
- 夏休み前には苦手単元をすべて処理
- 最終的に滑り止め、近いレベルの大学の過去問を10年以上
予備校以外の選択肢の場合
B判定以上が出ているのであれば、得意科目は独学でも勉強可能です。
予備校以外の選択肢としては、
- 個別指導塾や家庭教師で苦手科目の指導をしてもらう
- 学習管理系の塾や家庭教師に全体の勉強方針を調整してもらう
などがおすすめです。
苦手科目だけ個別指導塾や家庭教師に教わって、その他の科目は、過去問演習メインで進めるのでも十分力はつきます。
独学が不安な場合は、塾や家庭教師に「学習管理」を依頼するのも良いでしょう。
毎週の勉強計画や、年間の勉強計画を作ってくれる塾や家庭教師も増えているので、定期的に面談をしつつ、勉強内容や勉強方法が間違っていないかチェックしながら進めれば、安心して勉強することも可能です。
こちらもスケジュールとしては、3月から週1以上で過去問を解き続けて、10月ごろには10年分以上は満点を取れる状態を目指すのがいいですね。
苦手単元は、参考書や授業を使って勉強して、夏休み前くらいの時期にはすべて処理しきっているのが理想です。
A判定が出ていて、勉強がものすごく好きな方なら、宅浪でも成功することはありますが、それでも週に1回くらいは学習管理系の面談を入れるのがおすすめです。
どうしても素人とプロでは、受験勉強の計画に対する精密さが全然違いますからね。
- 3月から週1以上で過去問
- 夏休み前には苦手単元をすべて処理
- 最終的に滑り止め、近いレベルの大学の過去問を10年以上
模試でC判定以下の場合
次は模試でC判定以下の場合について。
C判定以下の場合は、まだまだ実力不足の科目の方が多いはず。
科目指導の授業も活用しつつ、勉強するのが良いでしょう。
予備校を使う場合
予備校を使う場合は、大筋カリキュラム通りに進めれば問題はないはずです。
ただし、現役生より学習進度が遅いのはさすがに問題なので、10月には過去問演習には入りたいですね。
予備校を活用する場合は、スケジュール感よりも、勉強の方針について、注意してほしい点が3点あります。
- 予習・復習はバランスを見つつ万全に
- 模試の復習は手を抜かない
- 授業関連の問題だけでは演習不足
授業の予習・復習は科目のバランスを見つつ、万全にやっていきましょう。
英語が重いからと言って、英語ばかり予習復習をしていると、科目のバランスが崩壊して合格から遠ざかります。
授業の予習・復習だけしっかりやってればいいかというと、そうでもなくて、模試の復習だったり、参考書での追加の演習も必要です。
授業だけしっかりやって失敗する人もいるので、こちらの記事も参考にしてもらえればと思います。
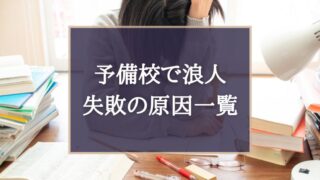
- 予備校のペースに合わせればOK
- 10月には過去問演習に入る
予備校以外の選択肢の場合
C判定以下の場合も、予備校ではなく個別指導塾や家庭教師で浪人するのも可能です。
本当に大きく成績を伸ばさないといけないのであれば、むしろ、個別指導を活用するのがおすすめです。
集団授業だと、「分かっている」~「分かっていない」の濃淡を授業につけることができません。
個別指導であれば、「分かってないけど、この部分までは分かってる」とか「完全に分かってない」とか、「分かってない」の中にもグラデーションをつけて解説することも可能なので、そりゃ伸びるのが速いのは当たり前です。
個別指導の場合は、5月末くらいまでに、基本的な内容を終わらせたいですね。
英語なら単語・文法・解釈、数学ならチャート、理科ならセミナーのレベルは5月末で卒業、6月~8月くらいまでで、過去問以外の参考書はすべて片づけて、9月以降は過去問演習に全振りくらいのイメージで勉強するのがおすすめです。
- 5月末までに各科目の基礎
- 6月~8月で発展的な参考書
- 9月以降は過去問演習
医学部受験に失敗する人の共通点

慶應医学部を目指している方の多くは、やる気はあって、ある程度は勉強するはずなので、「モチベの維持に困る」とか「勉強時間が少なすぎる」とか、そういった失敗はあまり多くはないはずです。
そこで、これまでの指導経験上、勉強はそこそこしてるけど、失敗する人の共通点についても簡単に触れておきます。
- 暗記ばかりしてる
- 手を動かす時間が短い
- 新しい問題に触れる頻度が少ない
※もちろん「受験勉強のスタートが遅かった」みたいなパターンはありますが、それはどうしようもないのでここでは省きます。
暗記ばかりしてる
まず最初は暗記ばかりしているパターンですね。
もちろん、単語帳に載っているものはすべて覚えた方が良いですし、化学や生物の資料集に載っていることもすべて覚えるに越したことはありません。
ですが、暗記に使っている時間が長くなればなるほど、合格からは遠ざかってしまいます。
できれば、問題演習をメインに進めて「解いているうちに自然と覚えられた」状態を目指してもらうのがいいかなと思います。
というのも、暗記って100%じゃなくても、問題の流れから思い出せたり、問題の流れから推測できたり、あるいはそもそも細かい所は出題頻度が低かったりするわけですから、合格最低点まではたどり着けるものなんです。
1%から90%まで行くところまでは、知識を詰め込む勉強も大事ですけど、90%から100%はけっこう時間の無駄になっていることも多いものです。
手を動かす時間が短い
次は手を動かす時間が短いパターンですね。
1番問題なのは「解けない問題の解説を読んで理解した」状態で終わっているパターン。
特に理系科目は、解説を読んで理解したのであれば、「解説を閉じて解き直す」癖をつけましょう。
何周しても自力で解けるようにならない人も同じですね。
解説を「理解する」のと、問題を「自力で解ける」のは別物です。
理解したものを再現できるかの確認は必ず入れるようにしてください。
新しい問題に触れる頻度が少ない
最後は新しい問題に触れる頻度が少ないパターン。
授業は真面目に聞いて、復習までしっかりやっていたとしても、自力で初見の問題に触れる時間が短いと、模試や入試では点を取れません。
授業で1回聞いた問題を、自力で解けるのはもちろん大事なことですが、それは当たり前中の当たり前のこと。
そんなのは当たり前のこととして当然やって、さらに初見の問題も解けるようにならないといけないんです。
できるだけたくさん初見の問題に触れて、その問題を徹底的に復習しつくす勉強をしましょう。
その他、よくある失敗例はこちらのページにもまとまっていますので、参考に。
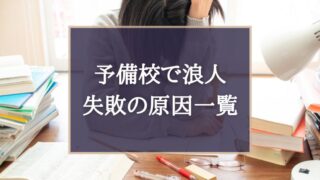
最後は勉強時間がものをいう!最後まで必死に勉強やり切って合格を掴みとろう!

この記事では、独学でも慶應医学部に受かるくらい丁寧に受験勉強の方針について解説しました。
この記事に書かれていることを参考にして勉強すれば、少なくとも合格するために必要な学力を身につけることは可能です。
ただし、ここで書かれたことをやり切るためには、必死に勉強時間を確保しないと難しい場合の方が多いと思います。
最低でも毎日10時間。可能なら12時間でも14時間でも(体調を崩さない程度に)勉強してもらえると嬉しいです。
これまで約15年塾講師をしていますが、受験は結局、勉強量がものをいう世界です。
応援しています!
もし、家庭教師に興味があれば、私も例年数名ずつ指導をしています。
人数を絞っているので、興味がある人はこちらの詳細ページを早めにご覧ください。
慶應医学部に合格するために私にできることはなんでもサポートします。